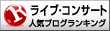フランク・マッコム@COTTON CLUBへ参戦。COTTON CLUBは初めて。ブルーノートと同様のシステム。2ndセットで、まぁ中央真ん中くらいの座席をゲット出来た。
フランク・マッコム@COTTON CLUBへ参戦。COTTON CLUBは初めて。ブルーノートと同様のシステム。2ndセットで、まぁ中央真ん中くらいの座席をゲット出来た。セオドア“トレズ”ギルバート(ベース)、“ジョイ”ウィリアムス(ドラム)、ジミー・ヤング(パーカッション)の3人とフランク・マッコムによる4人編成。フランクは、エレピ2台(フェンダーローズとウーリッツァー)と生ピアノを駆使。終盤に、上部のカヴァーを取り外して、エレピの調律をしながら即興演奏するというハプニングも(でも無事に演奏)。
今回は、ジャズ・セッション・ライヴ風に、フランクのヴォーカル・パート以外は、即興風にバンドと絡むというスタイルだったので、ヴォーカルが少なめ、1曲が長めで、曲数としては10曲もいかなかったが、発想力あふれるセッション・プレイが堪能出来た。
赤いベースボールキャップ被っていた。以前観に行った時も赤いものを身に着けていたような。
赤が好きなんだろうか。それともクリスマス仕様なのか。それは謎だった。
◇◇◇
伸びやかな声。たゆたう音の滴。
彼が吸収してきた音の数々が、声や鍵盤を通して沁み込むように届いてくる。
それが、ダニー・ハサウェイやスティーヴィー・ワンダーを彷彿とさせる声だったりするんだから、たまらない。
しかし、彼はその2人の真似で終わるという訳ではなく、しっかりと「個」を持っていることも確か。
雰囲気は似ているが、キーボードに向かう姿勢や佇まいは、やはりマッコムのオリジナルの世界だ。
主役はあくまでも素晴らしい楽曲だ、ともいわんばかりに配慮された演奏。
実体は見えない「音」が創り出すメロディに対して、最大限の敬愛を表しながら鍵盤を叩く、いや、叩くというより触れるといった方がいいかもしれない。その情景は、おもちゃを与えられて夢中になって喜ぶ子供のようだ。
無邪気に演奏する姿をみると、彼が商業的を嫌い、純粋に音楽に触れていたいという心境が解かるような気がした。
ただ、ビジネスとして成功していくことも、アーティストとしてやっていくためには必要なこと。
彼の演奏は素晴らしいが、それを理解したうえでいうなら、もう少しヴォーカルを増やして、コンセプトを決めたライヴやセット・リストでのステージということも、必要なのではと思った。
新譜を出したなら、そのアルバムを中心にセット・リストを組むとか、カヴァー曲だけで構成するとか、ソウル・クラシックスをやり遂げるとか。
贅沢なのかもしれないが、演奏やヴォーカルが素晴らしいだけに、それをもっと活かしたステージ構成を期待してしまうのだ。
また、今回は、高速ドラムが観客を沸かせていたが、ちょっと音が乾いていて硬い感じがした。
フランクのピアノの音色をちょっと吸収してしまった気がして、個人的にはフランクの楽曲には合わないドラミングかなと思ってしまった。ドラマーの質が悪いという訳ではなく、曲との相性というか、アレンジの問題で。
ダニーの「Little Ghetto Boy」のフレーズが流れた時は、観客も「Oh~」の声。
もちろん、嬉しい。
ただ、いつまでもダニーはないだろう、とも思う。
もちろん、聴けることは嬉しいが。
どうせなら、ダニーのカヴァー・ライヴをレイラ・ハサウェイとデュエットしてやるとか、そういうテーマを掲げてやった方が、すんなり観られる気がする。
オリジナルのマッコムをもっと体験したいという、個人的な希望が強いからかもしれないが。
とはいえ、ジャム・セッションのようなスタイルが多かった今回でも、彼の幅広さや懐の深さは充分堪能できたし、シルクのようになめらかで、雲のような浮遊感あるピアノの音の上を泳ぐようなヴォーカルは、言うまでもなく一級品だった。
上質な時間と幻想的な空間を作り出す魔術師。
歌い切ったという姿が次には観てみたいものだ。
◇◇◇
<SET LIST>
01 One Block Past(*)
02 Shine
03 Left Alone(*)
04 Keep Pushing On(*)
05 Little Ghetto Boy
06 The Christmas Song
07 Cupid's Arrow
≪ENCORE≫
08 Do You Remember Love
(*)記憶再生中