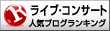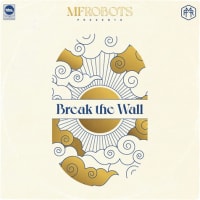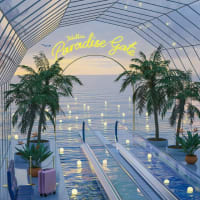南アフリカ人の父とドイツ人の母を持つ、南アフリカの言葉で“輝く星”を意味するデナラーニの名を持つアフロ・ジャーマン・フィメール・シンガーの2nd。
南アフリカ人の父とドイツ人の母を持つ、南アフリカの言葉で“輝く星”を意味するデナラーニの名を持つアフロ・ジャーマン・フィメール・シンガーの2nd。 前作『ママーニ』も質の高い作品で、アフリカン・ミュージックとドイツ語の融合させる、出自に拘ったアルバムだったが、今作は英語によるR&B/ヒップホップ・ミュージックで勝負してきた。
とはいえ、元来英語で歌うことの多かった彼女としてみれば、前作『ママーニ』が新たな挑戦であって、実はその挑戦で開拓した新境地が約4年ものあいだしっかりと身体に沁み込んで、現在の彼女として自然体の全作品が英詞というものになったと言った方がいいのかもしれない。
彼女の最大の武器は何かといえば、エネルギッシュなヴォーカリゼーションに他ならない。時には今にも水面から飛び出しそうな魚のように、時には獲物を見据えたジャガーのように、瑞々しくも隆々としたダイナミズムが歌声に漲っているのだ。
一聴すると、声質もスタンスもかなりメアリー・J.ブライジに近い。メアリー・Jは波乱な人生経験の中で得た生き抜く力を、歌声や全身から伝えてくるアーティストだが、ジョイもその出自ゆえの偏見やベルリンでの東西統合(ベルリンの壁崩壊)などの社会的環境、さらに退学経験(3校!)、そして母親となるなどという苦難や挫折の中で生き抜いてきた。それゆえ、その声にあふれんばかりの生命力が漲っているのは、メアリーもジョイも当然なのかもしれない。
当然といえば、声質ばかりかジョイ自身がメアリー・J.ブライジをリスペクトしている。リスペクトというより、憧れに近いか。それが如実に出たのが「セヴン・イヤー・イッチ」で、メアリー・Jのヒット曲名を織り込んだものとなっている。
生命力の強さ、それは楽曲にしなやかで揺るぎない核を持った“ソウル”を植えつけた。ジョイにとってのスター、いやソウル・メイトと言った方がいいかもしれないが、それがメアリー・Jだったのは、ジョイの琴線を揺らしたからだ。共鳴する、そして共鳴させるということがジョイの楽曲にはよく表われている。「ストレンジャー・イン・ディス・ランド」などはその白眉で、情感が知らずとこぼれてしまうというばかりに、こちらの魂に訴えかけてくるような迫力のあるヴォーカルを披露してくれる。
ここまでいうと、単なるメアリー・Jのフォロワーと思われるかもしれない。もちろん、自身がメアリーをモデルとして位置づけていることは動かし堅い事実だ。敢えて違いを挙げるのであれば、楽曲に対する安定感と変化に対応するバランス力ということになろうか。
もちろん、メアリーにそれがないという訳ではないが、メアリーを手本に、ベルリンからさまざまな土地へ移っても動じない精神力を培ってきたジョイ。それが、環境の変化、すなわち、さまざまな楽曲でもサラリとした身のこなしでやり遂げてしまうタフネスさとバランス力に繋がったのではないだろうか。
インプレッションズ「Man On Man(I Want To Go Back)」をネタ使いし、ルーペ・フィアスコをフィーチャーした、エネルギッシュなヒップホップ・ソウル「チェンジ」は、まさに鼓動高鳴るようなオープニングにピッタリのナンバーで、艶のあるパワフルなホーンのアクセントが光っている。
これに続くのは、ジェイク・ワンのプロデュースによる「レット・ゴー」。
スライ・スリック&ウィックトの「Love Gonna Pack Up(AndWalk Out)」のフレーズ・ループのなかで、“ガットゥ・レッゴー”というキャッチーなフックが飛び出すグルーヴィなヒップホップ・ソウルで、これを聴けば彼女の魅力にハマること必至だ。
その他、ウータン・クランのレイクウォンのソロ・ヒット曲をレイクウォンをフィーチャーしてカヴァーした「ヘヴン・オア・ヘル」、ガヴァナーとの共演した、ゆるやかな時の流れとぬくもりを感じるストーリー性を感じるスロー「サムシング・スターリン・アップ」など、どの客演であっても、エモーショナルであろうとメロウであろうと、歌唱表現は多少異なるとはいえ、そのどれにおいても確固たる生命力が宿っているのである。
メアリー・J.ブライジが好みの人はもちろん、ソウル、R&Bなどジャンルを問わず、体内の血が騒ぎ出すような体験をした人には、オススメの作品だ。