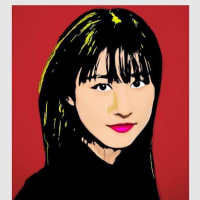エキセントリックとポップネスを自在に操る、色彩豊かな独創的ステージ。
カナダ・トロントを拠点とするマルチな才女、メイリー・トッドが『エスカポロジー』以来となるアルバム『アクツ・オブ・ラヴ』を完成させ、再び来日公演を開催。前回、2013年の来日(その時の記事はこちら→Maylee Todd@Billboard Live TOKYO)では、ギター、ベース含む5人体制で、イヴリン“シャンペン”キング「ラヴ・カム・ダウン」のカヴァーなどのディスコ、ファンク曲で盛り上げた印象があったが、今公演では新作『アクツ・オブ・ラヴ』のムードを基軸にしたのか、ディスコやファンクというよりもオルタナティヴ/アンビエントR&B趣向が強かった気がする。前回公演にも帯同したラナイ・ガブリエルのキーボードと、チノ・デ・ブジャのドラムというミニマルなリズム隊を従えて、サンプラー/シーケンサーによる打ち込みにハープを奏でるという斬新なスタイルで、時にサイケデリックに、時にポップにパフォーマンスを展開していく。

“ドレイク以降”という言葉が適切かどうかはさておき、コンテンポラリーな米R&Bシーンのスタンダード・フォーマットになっているエレクトロ志向の音質を意識したような作風、たとえば、ジ・インターネットやキング、ムーンチャイルド、ライあたりに顕在化する音数の多くないアンビエント・ソウルを奏でてきた『アクツ・オブ・ラヴ』の世界観をそのまま踏襲したようにステージは始まった。静謐と甘美が交互に訪れるとともに、観客の胸の内なる炎を勢いづかせる実験性に溢れた刺激的な演目が次々と眼前に現れる。一見すると派手さはなく、内省的な世界観が背後のスクリーンの映像とともにフロアに降り注ぐアーティスティックな空間は、場合によって“わかりにくさ”をもたらしたりもするが、メイリー・トッドの奇抜さは一辺倒ではなく、しっかりとポップネスにも振り戻す軽快なフットワークがあるゆえ、退屈というネガティヴな要素は生まれない。

心をえぐるようなシリアスな作風がヒシヒシと浸透してきたかと思うと、ハープを離れてマイクを握り、ハウシーなダンサー「ロンリー」や80年代ポップスを模したシンセ・ポップ「アイ・トゥ・アイ」でフロアの興奮を高めていく。エスニックな薫りを漂わせる70年代ディスコ・マナーの「ディスコ・ディックス・5000」ではミステリアスでエキセントリックなサウンドとダンスで、メイリー・トッドでしか可能たりえない多彩な表情を降り注いでいく。
そうかと思えば、フロアに躊躇なく飛び込むと、観客とハイタッチやハグをしながら練り歩き、観客の熱を自ら体感していくという人懐こさも。“アリガト、アリガト”と曲毎に話すカタコトの日本語や曲間の屈託のない笑い声なども相まって、演奏時の独創的なパフォーマンスとのギャップが人間的な親しみを沸かせる。そのあたりもエキセントリックなパフォーマンスながらも飽きさせないことの要因の一つになっているのかもしれない。難解な世界観をも好奇心へと変えてしまう、ユーモアやシニカルなどの心情豊かな人間性、モダンかつアーティスティックな表現力。猫の目のように表情を変えるカラフルなスタンスこそメイリー・トッドの真骨頂といえるだろう。知的欲求や本能的欲求をてらいなくステージの上で曝け出す天真爛漫さは彼女の大いなる武器で、それに観客も知らずのうちに惹き込まれてしまうのだ。
アンコールでは彼女の名を広めた人気曲「ベイビーズ・ゴット・イット」「ヒエログリフィクス」をセレクトしてきたが、単に馴染み深いだろうヒット曲を続けたのではなく、ややテンポを落として曲調に変化をつける演出に。この日のみのアレンジを駆使して、彼女の音楽性が深化している姿を見せるとともに、音楽の波を受けて全身で五感で愉しむスタイルを提示してくれたような気がした。
当初は“レディー・ガガ・ミーツ・ノラ・ジョーンズ”とも称された彼女だが、奇抜さという意味では“レディー・ガガ”なのだろうが、それはどちらかといえばあまり当てはまらず、アーティスティックなセンスなどで言えば、UAあたりに近い気も。“イリュージョン・ポップ”とはよく称したもので、音楽性とともに表情をクルクル変えるその様はまさにイリュージョンといっていい。
ただ、残念だったのは、ウィークデーとはいえ、観客席が思った以上に埋まってなかったこと。神出鬼没のオルタナティヴなR&Bを体感したいなら、次回こそ二の足を踏まずに、ライヴ会場に足を運んでもらいたい。彼女が持つ引き出しはまだまだ枯渇を知らないはず。まずは、新作『アクツ・オブ・ラヴ』でその世界観を堪能して、次回の来日を待ちたいところだ。

◇◇◇
<MEMBER>
Maylee Todd(vo)
La-Nai Gabriel(key)
Chino De Villa(ds)

◇◇◇