(1) 「なぜその年で合気道なんだよ?」
たいがいの中高年はそう思いますよね。なにが面白くてさ・・と。
周囲のそんな声をよそに楽心館の門をたたいたのは、還暦目前の昨年春。
健康のためとか、体力づくり、護身のため・・なんてことは考えず、(何となく、合気道が気になっていて・・)という、説得力のないノーテンキな動機でした(むろん、時間が多少自由になったことがある)。今から思えば、(何となく気にかかる)というある種の感覚は間違っていなかったと思う。
さすがに、この髪の薄い前記高齢者を前にすると、普通の道場は、(稽古中に脳卒中でも起こされては困る)と腰を引いてしまうらしく、「シニアや女性の入門も歓迎する道場」の噂を頼りに、おそるおそる楽心館中野道場の稽古をのぞかせていただいたのがきっかけでした。
稽古はさぞやバタンバタン投げ飛ばされているかと思いきや・・私同様、還暦から始めて黒帯になったという先達や女性もいて、予想よりは粛々として穏やかな稽古風景を拝見。これなら私も足手まといにならずについていけるかな・・と目を瞑り、清水の舞台から飛び降りたしだい。
とはいえ、酒・タバコにきっちり「律儀」を通してきた私の体は、当初、受身ででんぐり返っただけで目の前に星がちらつく状態からのスタートでした。
それでもどうにかこうにか慣れるものですね。以来1年半、私にとって合気道は、生活に不可欠な時間といっても過言ではありません。理由は三つあります。
一つは、「師を持つことの喜び」です。当たり前ですが、実社会ではたいがい教導する側に立たされる中高年には新鮮なマインドセットになります。稽古の間はひたすら先生の指導に自分を預け、頭を空っぽにしてついていくのみ。小学生が先生の話を白紙のアタマに刻んでいくのと変わりありません。
むしろ、この歳だからこそ、頭を空っぽにできる貴重な時間です。
二つ目は、「身体で考える時間を創れる」こと。
世の中どこもかしこも情報ツールで覆われると、頭で考えることばかりが肥大し、どうしても、身体の声に耳を貸せなくなります。心身のバランスが無意識のうちに極端に頭に偏っているのです。稽古で最初に気付くことは、頭で考える自分の身体と実際の身体の動きに大きなズレのあることです。手の動き、足さばき一つとっても、「ありゃりゃ」の連続。稽古はいわば、楽器のチューニングのようなもの。等身大の世界を身体で実感するにはもってこいです。稽古後のさっぱりとした心身で家路につくと、ビールの旨さもまた格別だし・・
三つ目は、これが一番大きいのですが、合気道が稽古場の身体運用だけでなく、人間関係の生じるところすべからくに通じる、“高度な汎用性”があることを知ったことでした。一言で言えば、(人間関係を術理として身につけ、相手の心を動かす技)であり、今流行の言葉で言うと、「人とつながる」技の集大成だったのです。
これは、良くも悪くも人生経験を重ねてきた中高年にこそ、ピンとくることです。人間関係の数々の頓挫、失敗は、「つながり方」の術理にあまりに無知だったのだ・・とわかります。いまさら気付いても遅いじゃないか、と思うむきもおられるでしょうが、家族や友人との人間関係は死ぬまで続きますし、それまでの未整理なデータがすっきりとインデックスがつけられるのですから、心の整理をして晩年は清々としたい方々にはどんぴしゃです。なぜならば、合気道が身体運用を通じて相手としっかりつながってこそ技がかかる・・言い換えれば、「人と同期する技」だからだと僕は思います。独りよがりでは決して技がかからないのです。創始、開拓し、磨いてこられた先達は、よくぞ、こんな技の集大成を積み上げてこられたものです。
むろん、日常生活で相手の身体を制するわけじゃありません。我々は毎日、言葉を通じて相手に伝え、人の心を動かし、動かされているわけです。
その基本原理は、夫婦間でも仕事の場でも、人間関係の生じるところ、会話の生じるところすべてに通じます。言葉もまた身体の一部。相手と同期し、つながらなければ何もアクセスできません。同じです。相手を無視して一方通行で発信したり、声高に叫んだり、「俺のいうことをわかれよ!」と怒鳴ってみても、伝わるどころか反発を招くだけで、相手を動かすことはできません。逆に、トツ弁であっても心のこもった言葉は、相手に耳を傾けさせ、人の心を揺さぶり、心を打つものです。相手が家族、友人であっても、きちんとこちらの意思や思いを伝えるということは、さほど容易ではないものです(体験的に)。合気道の基本どおり、相手としっかりつながり、同期できてこそ伝わります。受信も同様です。
言葉も磨きがかかれば活字であってもしっかりと相手とつながり、俳句、短歌の秀句のように万人の心を感動させることができます。音楽でも絵画でも、表現すること自体、技をかけることに他なりません。このへんは追々述べてみたいと思っています。
基本稽古を重ねるにつけ、術理の多くが、「人間関係に生じるあらゆる場面に応用できる」ということを感じます。相手とつながる力=他者との共生力といってもいいかもしれませんね。
若いうちはなかなか「つながる」ことの意味や術理を考えることなどないかもしれません。人生のひきこもごもを経て、失敗を繰り返してきた熟年世代なればこそ、合気道が語りかけている妙味を、理解し楽しめると僕は思います。
「なぜその歳で合気道なんだよ?」の問いに、「この歳だから合気道なんだ」と答えたいと思います。
次回以降、熟年合気道の妙味を具体的にとりあげてみたいと思います。
たいがいの中高年はそう思いますよね。なにが面白くてさ・・と。
周囲のそんな声をよそに楽心館の門をたたいたのは、還暦目前の昨年春。
健康のためとか、体力づくり、護身のため・・なんてことは考えず、(何となく、合気道が気になっていて・・)という、説得力のないノーテンキな動機でした(むろん、時間が多少自由になったことがある)。今から思えば、(何となく気にかかる)というある種の感覚は間違っていなかったと思う。
さすがに、この髪の薄い前記高齢者を前にすると、普通の道場は、(稽古中に脳卒中でも起こされては困る)と腰を引いてしまうらしく、「シニアや女性の入門も歓迎する道場」の噂を頼りに、おそるおそる楽心館中野道場の稽古をのぞかせていただいたのがきっかけでした。
稽古はさぞやバタンバタン投げ飛ばされているかと思いきや・・私同様、還暦から始めて黒帯になったという先達や女性もいて、予想よりは粛々として穏やかな稽古風景を拝見。これなら私も足手まといにならずについていけるかな・・と目を瞑り、清水の舞台から飛び降りたしだい。
とはいえ、酒・タバコにきっちり「律儀」を通してきた私の体は、当初、受身ででんぐり返っただけで目の前に星がちらつく状態からのスタートでした。
それでもどうにかこうにか慣れるものですね。以来1年半、私にとって合気道は、生活に不可欠な時間といっても過言ではありません。理由は三つあります。
一つは、「師を持つことの喜び」です。当たり前ですが、実社会ではたいがい教導する側に立たされる中高年には新鮮なマインドセットになります。稽古の間はひたすら先生の指導に自分を預け、頭を空っぽにしてついていくのみ。小学生が先生の話を白紙のアタマに刻んでいくのと変わりありません。
むしろ、この歳だからこそ、頭を空っぽにできる貴重な時間です。
二つ目は、「身体で考える時間を創れる」こと。
世の中どこもかしこも情報ツールで覆われると、頭で考えることばかりが肥大し、どうしても、身体の声に耳を貸せなくなります。心身のバランスが無意識のうちに極端に頭に偏っているのです。稽古で最初に気付くことは、頭で考える自分の身体と実際の身体の動きに大きなズレのあることです。手の動き、足さばき一つとっても、「ありゃりゃ」の連続。稽古はいわば、楽器のチューニングのようなもの。等身大の世界を身体で実感するにはもってこいです。稽古後のさっぱりとした心身で家路につくと、ビールの旨さもまた格別だし・・
三つ目は、これが一番大きいのですが、合気道が稽古場の身体運用だけでなく、人間関係の生じるところすべからくに通じる、“高度な汎用性”があることを知ったことでした。一言で言えば、(人間関係を術理として身につけ、相手の心を動かす技)であり、今流行の言葉で言うと、「人とつながる」技の集大成だったのです。
これは、良くも悪くも人生経験を重ねてきた中高年にこそ、ピンとくることです。人間関係の数々の頓挫、失敗は、「つながり方」の術理にあまりに無知だったのだ・・とわかります。いまさら気付いても遅いじゃないか、と思うむきもおられるでしょうが、家族や友人との人間関係は死ぬまで続きますし、それまでの未整理なデータがすっきりとインデックスがつけられるのですから、心の整理をして晩年は清々としたい方々にはどんぴしゃです。なぜならば、合気道が身体運用を通じて相手としっかりつながってこそ技がかかる・・言い換えれば、「人と同期する技」だからだと僕は思います。独りよがりでは決して技がかからないのです。創始、開拓し、磨いてこられた先達は、よくぞ、こんな技の集大成を積み上げてこられたものです。
むろん、日常生活で相手の身体を制するわけじゃありません。我々は毎日、言葉を通じて相手に伝え、人の心を動かし、動かされているわけです。
その基本原理は、夫婦間でも仕事の場でも、人間関係の生じるところ、会話の生じるところすべてに通じます。言葉もまた身体の一部。相手と同期し、つながらなければ何もアクセスできません。同じです。相手を無視して一方通行で発信したり、声高に叫んだり、「俺のいうことをわかれよ!」と怒鳴ってみても、伝わるどころか反発を招くだけで、相手を動かすことはできません。逆に、トツ弁であっても心のこもった言葉は、相手に耳を傾けさせ、人の心を揺さぶり、心を打つものです。相手が家族、友人であっても、きちんとこちらの意思や思いを伝えるということは、さほど容易ではないものです(体験的に)。合気道の基本どおり、相手としっかりつながり、同期できてこそ伝わります。受信も同様です。
言葉も磨きがかかれば活字であってもしっかりと相手とつながり、俳句、短歌の秀句のように万人の心を感動させることができます。音楽でも絵画でも、表現すること自体、技をかけることに他なりません。このへんは追々述べてみたいと思っています。
基本稽古を重ねるにつけ、術理の多くが、「人間関係に生じるあらゆる場面に応用できる」ということを感じます。相手とつながる力=他者との共生力といってもいいかもしれませんね。
若いうちはなかなか「つながる」ことの意味や術理を考えることなどないかもしれません。人生のひきこもごもを経て、失敗を繰り返してきた熟年世代なればこそ、合気道が語りかけている妙味を、理解し楽しめると僕は思います。
「なぜその歳で合気道なんだよ?」の問いに、「この歳だから合気道なんだ」と答えたいと思います。
次回以降、熟年合気道の妙味を具体的にとりあげてみたいと思います。










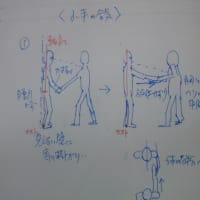


二つ目は、「身体で考える時間を創れる」こと。
三つ目は、一言で言えば、(人間関係を術理として身につけ、相手の心を動かす技)であり。
明確な目的意識をお持ちで、良く理解できました。
どうにも三つ目は、当方がお教えいただきたいです。
到らぬ自分です。
省みて
己に羞じよ
為す技の
言の葉に
つゆも似ぬ身を