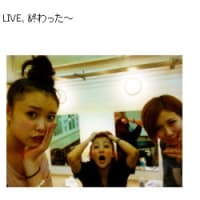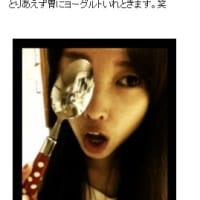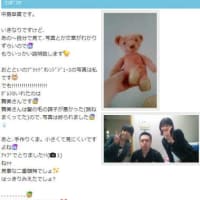カブス監督、交流戦名物の「シカゴ対決」削減を要望(MAJOR.JP編集部)
メジャーリーグでは今週末からインターリーグ(これを「交流戦」と呼ぶのは違和感を感じる上に「交流」という言葉に
真剣勝負な感じが伝わらない)が始まります。最初に導入されたときには、例えばアメリカンリーグのイースト対
ナショナルリーグのイーストという感じで、同じ地域にあるチーム同士の対決ばかりでしたが、改善を重ねて、
今ではリーグ・地域を越えた対決も見られるようになりました。だから今年はヤンキーズ@カーディナルスという、
1964年のワールドシリーズ以来初めてヤンキーズがセントルイスで試合をする、ということもあるのです。
しかしインターリーグが成功している要因の一つは、毎年必ずある目玉の試合に他ならないかもしれません。
つまりそれは、ニューヨークのサブウェイシリーズ、シカゴのウィンディシティシリーズ、ロサンゼルス/アナハイムの
フリーウェイシリーズというような、その地域のライバルチーム同士が当たる対決です。これらのシリーズでは
選手だけでなく、同じ都市であるにもかかわらずファン層や気質も違うファンが、試合当時の順位以上に応援に
熱が入る対決になります。
特に伝統チーム同士の対決であるシカゴのウィンディシティシリーズのある6日間は、シカゴ市民にしてみれば、
ものすごい盛り上がりになると思います。シカゴではカブスの熱狂的ファンはホワイトソックスは大嫌いという人が
かなりいるようです(その逆もあり)。
しかし、今年は圧倒的な強さのホワイトソックス、けが人続出もあり既に呪いに縛られているカブスという対決に
なってしまいそうです。そこでカブス監督のダスティ・ベイカーが「ちょっと不公平だしうちには不利なのだが」という趣旨の
発言をした模様です。これはベイカーの私見ではなく、どうも今年いや昨シーズン末あたりから出てきている
弱気なカブスを象徴している発言に思えてきます。
確かに「今年に限れば」ホワイトソックスは目を覆いたくなるほどにに弱い同地区のロイヤルズとの試合がある一方、
カブスはMLBの中でも圧倒的に強い同地区のカーディナルスとの試合があり、強いもの同士の狭間でカブスは
静かに沈んでいく運命にあるのかもしれません。しかし、ウィンディシティシリーズはインターリーグが始まって以降、
毎年必ずリグレーフィールドとUSセルラーフィールドで計6試合組まれているわけで、何も去年おととし始まった
ものではないのです。それに2003年は当然ウィンディシティシリーズがあった中、ベイカーがカブスをプレイオフへ
率いており、ワールドシリーズまであと一歩まで勝ち上がったのです(負けたのはスティーブ・バートマンのせい?)。
だからこそ、この発言はカブスの置かれている状況を代弁もしくは勝てない言い訳にしか聞こえない空しい
発言とも考えられてしまいます。これでは、リグレーフィールドに押しかける、カブスをバカにしたメッセージ入り
Tシャツを着たホワイトソックスファンは、行き帰りのレッドラインでも思いっきり胸を張れることでしょう。それも3日間連続で。
ただこの発言は、真意はともかく、インターリーグまたは少なくともウィンディシティシリーズが大成功である
証ともいえるし、その副作用とも言えるでしょう。今年から日本でも「交流戦」(これをインターリーグというのも
何かしっくりこない)が始まり現在進行中です。1年目それもまだ全試合終わっていない段階で評価を下すのは
酷なことかもしれませんが、日本の交流戦でここまで盛り上がる対決が表れるかと考えると、難しいのではないかと思います。
そこには、今のプロ野球はまだ地域密着でなければ、ファン層及びその気質の違いがあまり出ていないという
ところ行き着いてしまうのです。もし阪神タイガースと南海ホークスが全盛期だった1960年前後に交流戦があれば、
ファンも盛り上がらざるを得なかったと思うし、かなり面白い対決になったことでしょう。その頃の方が、
地域密着と言えるかは別にして、ファン気質は今より明確に違っていたと思うのです。タイガースとオリックス・バッファローズでは、
ファン層・気質の違いは、正直言って薄いのではないかと思います。
日本の交流戦の成功も、どれだけ観客が来たかではなく、いかにして今後もファンの間に根付くかによると思います。
そしてそこには日本プロ野球自体の改革も同時に進めていく必要があるのです。
※文中の「1964年ワールドシリーズ」についての名著といえばやはりこれでしょう。
アメリカの1960年代を語らせたら右に出るものがいないデイビッド ハルバースタムの綿密な取材が光ります。
メジャーリーグでは今週末からインターリーグ(これを「交流戦」と呼ぶのは違和感を感じる上に「交流」という言葉に
真剣勝負な感じが伝わらない)が始まります。最初に導入されたときには、例えばアメリカンリーグのイースト対
ナショナルリーグのイーストという感じで、同じ地域にあるチーム同士の対決ばかりでしたが、改善を重ねて、
今ではリーグ・地域を越えた対決も見られるようになりました。だから今年はヤンキーズ@カーディナルスという、
1964年のワールドシリーズ以来初めてヤンキーズがセントルイスで試合をする、ということもあるのです。
しかしインターリーグが成功している要因の一つは、毎年必ずある目玉の試合に他ならないかもしれません。
つまりそれは、ニューヨークのサブウェイシリーズ、シカゴのウィンディシティシリーズ、ロサンゼルス/アナハイムの
フリーウェイシリーズというような、その地域のライバルチーム同士が当たる対決です。これらのシリーズでは
選手だけでなく、同じ都市であるにもかかわらずファン層や気質も違うファンが、試合当時の順位以上に応援に
熱が入る対決になります。
特に伝統チーム同士の対決であるシカゴのウィンディシティシリーズのある6日間は、シカゴ市民にしてみれば、
ものすごい盛り上がりになると思います。シカゴではカブスの熱狂的ファンはホワイトソックスは大嫌いという人が
かなりいるようです(その逆もあり)。
しかし、今年は圧倒的な強さのホワイトソックス、けが人続出もあり既に呪いに縛られているカブスという対決に
なってしまいそうです。そこでカブス監督のダスティ・ベイカーが「ちょっと不公平だしうちには不利なのだが」という趣旨の
発言をした模様です。これはベイカーの私見ではなく、どうも今年いや昨シーズン末あたりから出てきている
弱気なカブスを象徴している発言に思えてきます。
確かに「今年に限れば」ホワイトソックスは目を覆いたくなるほどにに弱い同地区のロイヤルズとの試合がある一方、
カブスはMLBの中でも圧倒的に強い同地区のカーディナルスとの試合があり、強いもの同士の狭間でカブスは
静かに沈んでいく運命にあるのかもしれません。しかし、ウィンディシティシリーズはインターリーグが始まって以降、
毎年必ずリグレーフィールドとUSセルラーフィールドで計6試合組まれているわけで、何も去年おととし始まった
ものではないのです。それに2003年は当然ウィンディシティシリーズがあった中、ベイカーがカブスをプレイオフへ
率いており、ワールドシリーズまであと一歩まで勝ち上がったのです(負けたのはスティーブ・バートマンのせい?)。
だからこそ、この発言はカブスの置かれている状況を代弁もしくは勝てない言い訳にしか聞こえない空しい
発言とも考えられてしまいます。これでは、リグレーフィールドに押しかける、カブスをバカにしたメッセージ入り
Tシャツを着たホワイトソックスファンは、行き帰りのレッドラインでも思いっきり胸を張れることでしょう。それも3日間連続で。
ただこの発言は、真意はともかく、インターリーグまたは少なくともウィンディシティシリーズが大成功である
証ともいえるし、その副作用とも言えるでしょう。今年から日本でも「交流戦」(これをインターリーグというのも
何かしっくりこない)が始まり現在進行中です。1年目それもまだ全試合終わっていない段階で評価を下すのは
酷なことかもしれませんが、日本の交流戦でここまで盛り上がる対決が表れるかと考えると、難しいのではないかと思います。
そこには、今のプロ野球はまだ地域密着でなければ、ファン層及びその気質の違いがあまり出ていないという
ところ行き着いてしまうのです。もし阪神タイガースと南海ホークスが全盛期だった1960年前後に交流戦があれば、
ファンも盛り上がらざるを得なかったと思うし、かなり面白い対決になったことでしょう。その頃の方が、
地域密着と言えるかは別にして、ファン気質は今より明確に違っていたと思うのです。タイガースとオリックス・バッファローズでは、
ファン層・気質の違いは、正直言って薄いのではないかと思います。
日本の交流戦の成功も、どれだけ観客が来たかではなく、いかにして今後もファンの間に根付くかによると思います。
そしてそこには日本プロ野球自体の改革も同時に進めていく必要があるのです。
※文中の「1964年ワールドシリーズ」についての名著といえばやはりこれでしょう。
アメリカの1960年代を語らせたら右に出るものがいないデイビッド ハルバースタムの綿密な取材が光ります。
|
|












![[短評]感謝の念](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/46/52/7102007b8dd5e319bdf1a8751a29f717.jpg)