「あーた、なんてお名前でらっしゃるの?」
どーも、デヴィ夫人ことデヴィ・スカルノ(80)です!
日本での名字の始まりは今から900年ほど前、
平安時代(794-1185)の終盤からです
最初は公家や武士だけのものでしたが、
室町時代(1336-1573)には農民にも広まりました
ところで、「西田」 ← どう読みますか?
「にしだ」とも「にした」とも読めます
なぜ濁る、濁らないの違いがあるのか疑問だったので調べました
これは「東日本と西日本で分かれている」という理由が一番しっくりきました
ではその境目はどこか?
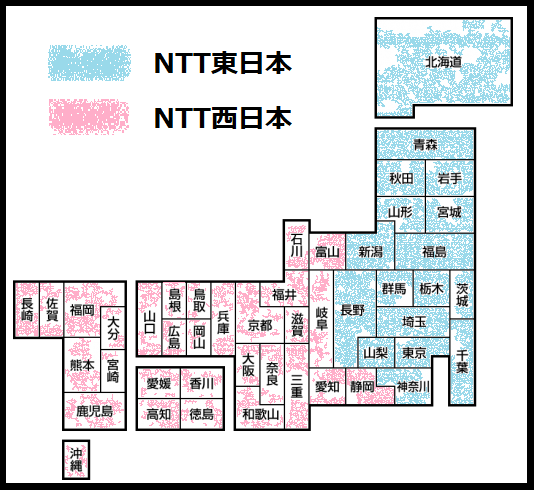
「NTT」では↑の図のように分かれています
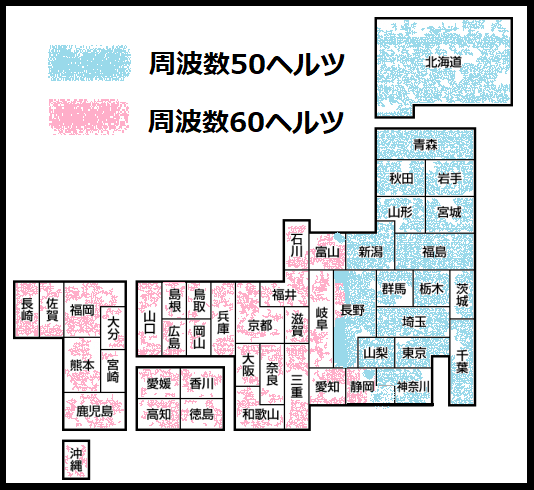
「電源周波数」では↑の図のように分かれています
日本を東西で分ける場合はこの2パターンがメジャーでしょう
ところが姫路市(兵庫県)あたりからガラッと変わるという研究家の意見もありました
東西の境目はこのくらいにして濁る濁らないの違いですが、
東日本は連濁(濁る)、西日本は清音(濁らない)発音を古来からしていたためらしい
だから「にした」という読みの人はルーツが西日本にあるかもしれません
「なかしま」「やまさき」「たかた」なども同様です










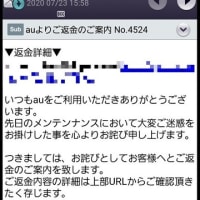

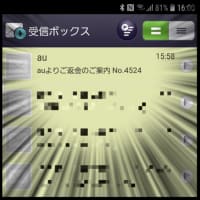
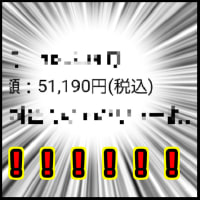
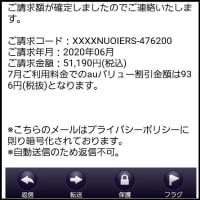
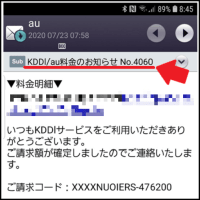
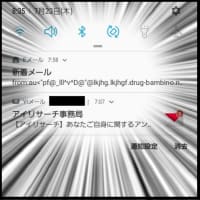

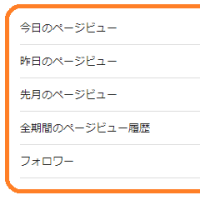
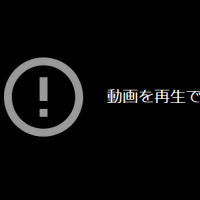
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます