つづき…
この日一人の参加者の方が南相馬市が募集した復興計画にパブリックコメントとして提出された資料を持参されていました。
その内容は「研究機関であり教育機関である大学・大学院を設置し、復興に向けての放射能、産業、地域コミュニティなどの
状況を継続的に研究し発信する」というご意見。この提案をされたのはボランティア活動からここ南相馬市にご夫婦で移住さ
れてこられたMさんの奥様です。奥様は財政破綻で暫く世間の注目を浴びる事となってしまった炭鉱の街、夕張のご出身。
当時ご自分が住民として味わった現状を交えながら復興に対する思いと意見をお話し下さいました。大学誘致、この提案に
対し地元でボランティアをしながら活動を続けているW沢さんからこんな意見がでたのです。

「若い人達を引き戻すために大学誘致など何かがあればいいと思う。そしてその情報を発信する。大学を誘致すれば若い方
がくる可能性はあると思うが研究をしそのまま雇用へとつながるのか?仕事に生かせるか?人材育成のシツテム作りも必要
です。でも…現実、人材が必要で募集してもほんとにこない。いくら地元の人達が安全だ安心だといっても放射能があるか
らだめなんです。専門的に活動されている方はいますが、マスクをして活動するなどストレスもかかっている。
何らかの同意書も必要だと思う。この地元で一生働いて生きて行く為に何が必要なのか?本当に必要なものは何なのか?
ここで生きていくメリットは何なのか。5年後10年後にはまちがいなく高齢者の方が増え逆ピラミッドになってしまう。
学校施設の耐震、期間限定の雇用問題、医療福祉関係など課題が多い中んで安心しながら安定した生活環境の整備が性
急に必要です。言葉や文字で子供達にも意見を聞いてみたらいいと思う。
今ここから地元の声を聞き、ニーズを拾い情報を全国に発信してほしい…」(一部抜粋)
参加者から大きな拍手がおきました。誰もがみな真剣でした。
この日集まってくださった参加者の声をここで全部お伝えできないのは本当に残念であり心苦しいですが
いくつかご紹介したいと思います。
 埼玉県から来られたKさん。現在も市内各地で活動中。
埼玉県から来られたKさん。現在も市内各地で活動中。
阪神大震災の時にはボランティアとして参加できなかった。その思いを抱えて3/27にバイクで東北をめざし
た。その後車に乗り換え1か月の半分は車中泊し、原町二中の避難所に落ち着きそこで支援活動を行い、現
在は又、埼玉県と南相馬市を往復しながら車中泊でボランティア活動をしている。
「私の宿泊所はそのカーテンの向こうです」と道の駅南相馬の駐車場を指差しながら笑顔でおっしゃった。
「ボランティアのニーズをもっときちんとしてほしい。情報の発信が欲しい。」
 茨城県からこられたHさん。23歳 画家 南相馬市で個展開催
茨城県からこられたHさん。23歳 画家 南相馬市で個展開催
南相馬市にきたのは何か大きな決意があったとい事ではない。南相馬市は安全だから…という問いかけに
応えただけです。ここで出会った方は本当に事をちゃんと話してくれる大人がとても多かった。
自分の言葉では表現できない事を作品で表現するアーティストをすんなり受け入れてくれる体制もよかった。
幼稚園でワークショップをやってるのを見たが子供達がほんとに楽しそうだった。今後は子供の成長を見守
っていける活動がしたい。
 会津若松市から来られたKさん。美術関係者
会津若松市から来られたKさん。美術関係者
アーティストの方を当地に連れてこられその方の作品と通して被災地からの情報発信を推進されている。
自分の目で見て感じるのは支える柱をしっかりさせないとだめという事。風化させないで忘れないようにす
るのが大切で、その輪を大切にするのが今の福島だと思う。マスコミ情報を見て情報の発信をするのではな
くここにきて何かを感じてもらって情報を発信してほしい。その手助けとなり伝道者になりたい思っている。
興味本位できてる訳では決してない。今は一人一人感情が違うので、人と人とのコミュニティ、感情の作り
方がとても大切だ。心のくい違いや差別などで苦しむかもしれない子供達をどうやって守れるか。
大人が考えないと…。
 東京からお水の支援活動をされているMさん。
東京からお水の支援活動をされているMさん。
福島県から岩手県まで保育園などに一人あたり1リットルの水を届ける支援活動をしている。被災地から遠
ければ遠いほどまだ余力がある。まだ活動ができる。遠慮なく色々なアイディアをだすべきだ。
大学誘致の問題はまだ早いのではないかと感じる。ピンとこない。今は心のケアを色々と織り交ぜながらや
っていく必要がある。また、この復興会議は土日で開催して頂きたい。時間も長くとって気軽に参加できる
ように…。また意見がぶつかる事は相互理解を深める事でもあり、地域性もある。好き勝手言ってどんどん
やって頂きたい。
地元の方からも子供達の問題に関し、今の現状やこんな本音もでました。
 市内農家
市内農家
小学校で農業体験の訪問した時の事、先生から今日はクラス全員の父兄が参加していると言われたが19人
しかいないのを見て愕然とした。今は農業ができないので代替用地を捜し5ヵ所位見て歩いた。そこで分
かった事それはこんなにいい地域はない!という事。これだけは本当に心から言える。
放射能が収まらないと駄目だが。
 鹿島区在住
鹿島区在住
今は親の決断でここにいるが、子供がいなければここにはいないと思う。放射能と共存しながらやっていく。
その方法はないのか?教えて欲しい。
 保育園児のお母さん
保育園児のお母さん
田舎は暮らしにくいと思っていたがふるさとを失くしたくない。だがこの9ヶ月間小さい子をもつ親として答
えがでない。未来を語ることができない。もうくたびれた…。でも、力を貸して頂きながら頑張っていきたい。
教育に関しての要望だが学区の自由化をお願いしたい。放射線量が高いからとはいえなぜわざわざ
遠くの学校までバスで行かなければならないのか?住民側の要望に沿って支援をして頂きたい。
今回のふるさと復興会議には都合がつかず参加できなかった方からもメールなどでご意見や南相馬市に来られた感想が数件
寄せられました。その中で二つご紹介させて頂きます。
まずこちら…
昔の話で恐縮ですが、関東大震災の復興計画に「同潤会アパート」というのがありました。
質の高い耐震性のあるアポートを建設しその後60年以上にわたり共同住宅の模範として活用されました。
現在でもその形跡は青山、表参道に残っています。
この度の東日本大震災の復興モデル住宅は如何なものか?
「過疎地市街地活性化復興モデル」とか「高齢化社会対応モデルとか様々な模範を検討して早急に建設に
着手するべきと考えます。(一部抜粋)
そしてもう一つ…千葉県からこんなメーセージが届けられました。
津波で何もかも失い悲しいけれど どうか 海を嫌いにならないでほしい
土も放射能に汚染されてしまったけれど 愛しつづけてほしい
山、川、森も見捨てないでほしい
人は自然に守り助けられ今があるのだから
愛し続ければ きっときっと自然は喜び また ふたたび人を助け 守り 人間を豊かにしてくれる
ず~っと ず~っと 自然を見捨てることなく愛しつづけてほしい
人間の手は1メートルしかないけど 心は広く世界中まで広げることができる
福島のみなさま 私はいつもこのような気持ちで心から祈り応援しています
これからも忘れることなく応援しつづけたいと思っています
この詩は当日参加された移住者の方により朗読披露されました。
自分の心の中を見透かされたようで目がしらが熱くなりました。
>>南相馬市ふるさと回帰支/援センターHPへ
この日一人の参加者の方が南相馬市が募集した復興計画にパブリックコメントとして提出された資料を持参されていました。
その内容は「研究機関であり教育機関である大学・大学院を設置し、復興に向けての放射能、産業、地域コミュニティなどの
状況を継続的に研究し発信する」というご意見。この提案をされたのはボランティア活動からここ南相馬市にご夫婦で移住さ
れてこられたMさんの奥様です。奥様は財政破綻で暫く世間の注目を浴びる事となってしまった炭鉱の街、夕張のご出身。
当時ご自分が住民として味わった現状を交えながら復興に対する思いと意見をお話し下さいました。大学誘致、この提案に
対し地元でボランティアをしながら活動を続けているW沢さんからこんな意見がでたのです。

「若い人達を引き戻すために大学誘致など何かがあればいいと思う。そしてその情報を発信する。大学を誘致すれば若い方
がくる可能性はあると思うが研究をしそのまま雇用へとつながるのか?仕事に生かせるか?人材育成のシツテム作りも必要
です。でも…現実、人材が必要で募集してもほんとにこない。いくら地元の人達が安全だ安心だといっても放射能があるか
らだめなんです。専門的に活動されている方はいますが、マスクをして活動するなどストレスもかかっている。
何らかの同意書も必要だと思う。この地元で一生働いて生きて行く為に何が必要なのか?本当に必要なものは何なのか?
ここで生きていくメリットは何なのか。5年後10年後にはまちがいなく高齢者の方が増え逆ピラミッドになってしまう。
学校施設の耐震、期間限定の雇用問題、医療福祉関係など課題が多い中んで安心しながら安定した生活環境の整備が性
急に必要です。言葉や文字で子供達にも意見を聞いてみたらいいと思う。
今ここから地元の声を聞き、ニーズを拾い情報を全国に発信してほしい…」(一部抜粋)
参加者から大きな拍手がおきました。誰もがみな真剣でした。
この日集まってくださった参加者の声をここで全部お伝えできないのは本当に残念であり心苦しいですが
いくつかご紹介したいと思います。
 埼玉県から来られたKさん。現在も市内各地で活動中。
埼玉県から来られたKさん。現在も市内各地で活動中。阪神大震災の時にはボランティアとして参加できなかった。その思いを抱えて3/27にバイクで東北をめざし
た。その後車に乗り換え1か月の半分は車中泊し、原町二中の避難所に落ち着きそこで支援活動を行い、現
在は又、埼玉県と南相馬市を往復しながら車中泊でボランティア活動をしている。
「私の宿泊所はそのカーテンの向こうです」と道の駅南相馬の駐車場を指差しながら笑顔でおっしゃった。
「ボランティアのニーズをもっときちんとしてほしい。情報の発信が欲しい。」
 茨城県からこられたHさん。23歳 画家 南相馬市で個展開催
茨城県からこられたHさん。23歳 画家 南相馬市で個展開催南相馬市にきたのは何か大きな決意があったとい事ではない。南相馬市は安全だから…という問いかけに
応えただけです。ここで出会った方は本当に事をちゃんと話してくれる大人がとても多かった。
自分の言葉では表現できない事を作品で表現するアーティストをすんなり受け入れてくれる体制もよかった。
幼稚園でワークショップをやってるのを見たが子供達がほんとに楽しそうだった。今後は子供の成長を見守
っていける活動がしたい。
 会津若松市から来られたKさん。美術関係者
会津若松市から来られたKさん。美術関係者アーティストの方を当地に連れてこられその方の作品と通して被災地からの情報発信を推進されている。
自分の目で見て感じるのは支える柱をしっかりさせないとだめという事。風化させないで忘れないようにす
るのが大切で、その輪を大切にするのが今の福島だと思う。マスコミ情報を見て情報の発信をするのではな
くここにきて何かを感じてもらって情報を発信してほしい。その手助けとなり伝道者になりたい思っている。
興味本位できてる訳では決してない。今は一人一人感情が違うので、人と人とのコミュニティ、感情の作り
方がとても大切だ。心のくい違いや差別などで苦しむかもしれない子供達をどうやって守れるか。
大人が考えないと…。
 東京からお水の支援活動をされているMさん。
東京からお水の支援活動をされているMさん。福島県から岩手県まで保育園などに一人あたり1リットルの水を届ける支援活動をしている。被災地から遠
ければ遠いほどまだ余力がある。まだ活動ができる。遠慮なく色々なアイディアをだすべきだ。
大学誘致の問題はまだ早いのではないかと感じる。ピンとこない。今は心のケアを色々と織り交ぜながらや
っていく必要がある。また、この復興会議は土日で開催して頂きたい。時間も長くとって気軽に参加できる
ように…。また意見がぶつかる事は相互理解を深める事でもあり、地域性もある。好き勝手言ってどんどん
やって頂きたい。
地元の方からも子供達の問題に関し、今の現状やこんな本音もでました。
 市内農家
市内農家小学校で農業体験の訪問した時の事、先生から今日はクラス全員の父兄が参加していると言われたが19人
しかいないのを見て愕然とした。今は農業ができないので代替用地を捜し5ヵ所位見て歩いた。そこで分
かった事それはこんなにいい地域はない!という事。これだけは本当に心から言える。
放射能が収まらないと駄目だが。
 鹿島区在住
鹿島区在住今は親の決断でここにいるが、子供がいなければここにはいないと思う。放射能と共存しながらやっていく。
その方法はないのか?教えて欲しい。
 保育園児のお母さん
保育園児のお母さん田舎は暮らしにくいと思っていたがふるさとを失くしたくない。だがこの9ヶ月間小さい子をもつ親として答
えがでない。未来を語ることができない。もうくたびれた…。でも、力を貸して頂きながら頑張っていきたい。
教育に関しての要望だが学区の自由化をお願いしたい。放射線量が高いからとはいえなぜわざわざ
遠くの学校までバスで行かなければならないのか?住民側の要望に沿って支援をして頂きたい。
今回のふるさと復興会議には都合がつかず参加できなかった方からもメールなどでご意見や南相馬市に来られた感想が数件
寄せられました。その中で二つご紹介させて頂きます。
まずこちら…
昔の話で恐縮ですが、関東大震災の復興計画に「同潤会アパート」というのがありました。
質の高い耐震性のあるアポートを建設しその後60年以上にわたり共同住宅の模範として活用されました。
現在でもその形跡は青山、表参道に残っています。
この度の東日本大震災の復興モデル住宅は如何なものか?
「過疎地市街地活性化復興モデル」とか「高齢化社会対応モデルとか様々な模範を検討して早急に建設に
着手するべきと考えます。(一部抜粋)
そしてもう一つ…千葉県からこんなメーセージが届けられました。
津波で何もかも失い悲しいけれど どうか 海を嫌いにならないでほしい
土も放射能に汚染されてしまったけれど 愛しつづけてほしい
山、川、森も見捨てないでほしい
人は自然に守り助けられ今があるのだから
愛し続ければ きっときっと自然は喜び また ふたたび人を助け 守り 人間を豊かにしてくれる
ず~っと ず~っと 自然を見捨てることなく愛しつづけてほしい
人間の手は1メートルしかないけど 心は広く世界中まで広げることができる
福島のみなさま 私はいつもこのような気持ちで心から祈り応援しています
これからも忘れることなく応援しつづけたいと思っています
この詩は当日参加された移住者の方により朗読披露されました。
自分の心の中を見透かされたようで目がしらが熱くなりました。
>>南相馬市ふるさと回帰支/援センターHPへ

















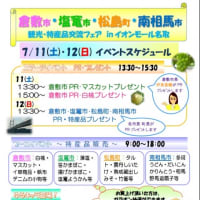



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます