個の能力を維持するには補う者と補われる者を完全に必要とします。原因や影響、結果や繁栄の維持は「協調」そのものなのですね。そして無数にある個がそれを完全に可能にすることのできる世界なのですね。逆に言えば、無数の個の能力は全体があってこそ、それぞれの能力と認められることができるのですね。つまり能力とは、補う者と補われる者が知っている事実を意味します。両者が知っていなくては物語の一つもできないのです。だから能力は進化することができるのです。国(生命体)のどこかに穴の開けるにせよ、穴の開けることを分かるものがいなければ行為も生まれてきません。もちろんここには感覚能力を持つものの説明があるのですが、感覚を持つ者の知性も偶然の産物としの知性であったのではありません。ここで言う知性は受継がれているものを意味します。受継がれているものは「偶然の産物」としではなく、その世代では一定の能力でも補う者と補われる者、つまり交配による円環の中で「協調の産物」として次世代へ受け渡すのですね。
その昔、感覚能力を持つ者たちは各街を結び付けるための幹線(神経細胞)を建設し、さらにスマートインター(シナプス)をあらゆる箇所に建設しました。その建設にも各街の協力や理解が必要でした。そこにも「協調の産物」としての知っていることが必要となります。ひょっとして、感覚能力を持つ者は国(生命体)の中で漂う風来坊だったのでしょうか?様々な街で様々な者と出会い、少し活動を共にしてはまた流れてゆくようなことを繰り返していたのではないのでしょうか?「産物」としてあるためには知っていることが大切ですからね。知らないことを大切にすることなど、思い起こすことなどできません。知っていることは個が吸収した何かしらの感覚的経験です。そして運動能力は感覚能力に相関します。つまり、知っていることは何かしらの自動的な運動能力に『反応』するということなのですね。生命は円環の中で「協調の産物」を次世代へ受け渡しているのです。人間の知ることへの欲求もこの感覚能力を持つものから始まったのではないのでしょうか?今もなお続いているとしたなら、私としても知りたい情報です(^^)
またまた脱線しますが、『反応』と言うと思いだすことがあります。人の寿命が延びた訳と、死亡率の低下のお話です。
古いお話ですけど、お付き合いのほどを(^^)・・・・・宜しく申し上げますm(__)m・・・・・つづく。

















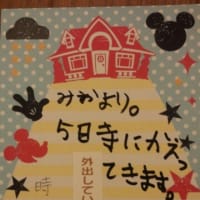


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます