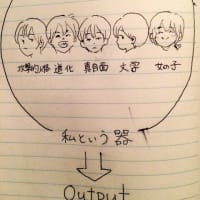「一旦寝付いても夜中に何度も目覚めてしまう」というのが中途覚醒。
しかしこの定義はちょっと曖昧。
「何時間で目覚めたら中途覚醒なのか」
「夜中に何回目覚めたら中途覚醒なのか」
などといった基準はある。
実はこれははっきりとは決まっていない。
強いて言うならば、
夜に目覚めてしまい、その後なかなか寝付けない
これによって苦しい思いをしている、生活に支障が出ている
これらの状態が一定期間続いているというのが、治療が必要な中途覚醒になる。
そのため、「夜中に〇回以上目覚めてしまったら中途覚醒」「夜中に目覚めた後に〇分以上で寝付けなければ中途覚醒」と機械的に考えるのではなく、
「それによって苦しい思いをしているか」」「夜中に目覚めることで生活に支障が生じているか」といった視点で判断する事が大切。
しかしそれだと自分の中途覚醒は治療が必要なものなのか判断できないという方もいると思うので、おおよその判断基準を書きます。
臨床的な感覚で言えば、
・夜中にしっかりと目が覚めてしまい、再入眠に30分以上かかる
・中途覚醒によって、日中の集中力や精神状態に悪影響が出ている
ような時は治療の必要性がある事が多いと感じる。
例えば年配者が、「若い時と比べると眠りが浅くなっている。もう少しぐっすりと眠りたい」と言った場合、
たとえ中途覚醒があって再入眠に時間がかかっていたとしても、別に日中の生活に支障を来たしていないようであれば、
それは加齢に伴う正常な睡眠の質の低下と判断する。
このような場合は無理に睡眠薬を使っても思うような効果が得られないばかりか、
ふらつきや転倒といった危険性が高まってしまう事があるため、基本的には治療はしない。
一方で、若い人が夜中に何度も中途覚醒してしまい、それで日中に眠気が出てしまって仕事のミスが増えているという事であれば、
これは「生活への支障が生じている」と判断して治療を行うことも・・・。
また「中途覚醒が一定期間続いている」の「一定期間」というのはどのくらいの期間か?
アメリカ精神医学会が発刊しているDSM-5、米国睡眠医学会が発刊しているICSD-3という診断基準いずれも
「週に3回以上が3か月以上持続する状態」と定義している。