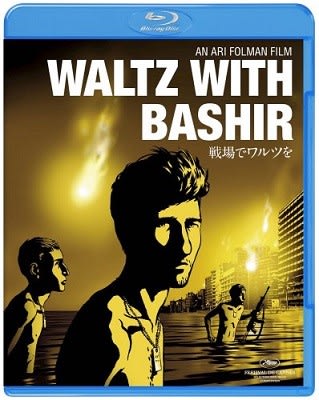
『戦場でワルツを』は、アリ・フォルマン監督の実体験を描いたノンフィクションである。ゴールデン・グローブ賞をはじめ各国の映画賞を総なめにし、本年度米国アカデミー外国語映画賞では『おくりびと』の対抗馬として注目を集めた話題作。戦場で体験したあまりの絶望から一度封印した過去の記憶を、今再び取り戻そうと立ち上がるアリの姿を通して、本作は"人間の強さ"を描いた魂の記録である。記憶や幻想が織り成すめくるめく映像は、アニメーションの枠を超え真の芸術の輝きを放っている。
あらすじ:冬のバー。映画監督のアリは、旧友とひさしぶりの再会を果たした。
会話の途中。アリはふいにあることに気付く。ある戦時中の記憶が自分にはまったくないということに...。抜け落ちた過去。なぜ俺は覚えていない―?失った過去を求めて、アリは当時を知る戦友たちを訪ねていく。(作品資料より)

<感想>2008年度の、あの「おくりびと」とアカデミー外国語映画賞を競った話題のアニメーション作品です。どちらかというと、本作の方がオスカー本命だったそうです。ここで扱われている虐殺事件は、1982年9月16日から約3日間、イスラエル軍によるレバノン侵攻が進められ、サブラとシャティーラ地区のパレスチナ難民キャンプで大量虐殺が起きたことを題材にしています。

サブラ・シャティーラ地区はほぼ全滅状態で、本当に酷かった。この時の作戦コードネームが“カサチ”アラビア語で「切り刻む」という意味。もう言葉を失います。サブラ・シャティーラの難民キャンプに攻めて来たのは、レバノンのキリスト教マロン派右派で、ファランヘ党。命令を下して後押ししてやらせていたのが、アリエル・シャロン。当時の国防相アリエル・シャロンは、この虐殺事件で解任され、のちに2001年、イスラエルの首相に就任する。

このサブラ・シャティーラ地区の虐殺の首謀者として、シャロンは国際戦争法廷に告訴されます。彼はメチャクチャで、2000年東エルサレムのイスラム聖地に数百人の武装護衛を伴って訪れ、「エルサレムはすべてイスラエルのもの」と宣言し、和平の機運を壊し、パレスチナ側の抵抗運動を激化させてしまったのです。そのシャロンも2006年に、脳卒中で倒れ、いろいろ病を重ねて、今では政界を引退したそうです。時の流れを感じさせます。(上部の部分は資料より引用しています)
そんな中、本作はアニメーションとドキュメンタリーを融合させた斬新な手法で登場したわけですが、・・・1982年当時、19歳だった監督のアリ・フォルマン自身の実体験が基になっているそうです。従軍したはずなのに、まったくその記憶がないという。実際、そういう記憶の後遺症は有り得るから。
現地で虐殺を受けた人々にとっては、消したくても消えないトラウマが残っただろうし、また、フォルマン監督みたいに思い出したくても思い出せない場合もあるだろう。その悲惨な記憶をドラマや映画にするには、あまりにも難しく、幻想も含めて内省の旅を描いていくのに“アニメーション”という手法を選んだのは良く分かりますね。

レバノンの海岸、海辺に並んでいる建物、海兵隊のあったところなどは、かつては“中東のパリ”と言われた風景が精密に描かれて、もちろん戦闘シーンも印象的でした。ただし、この“アニメーション”で描かれている場面はちょっと踏み込みが足りないような気がした。
戦場から戻って、いつまでも消えずに残る記憶は、視覚的なものよりも、死体が腐っている臭い、焼け焦げている臭い、そういうものを感じ取れれば、なお良かったのでは。実写でも難しいことなので、そこまで望むのは残酷かもしれませんけど、見ているものにそういう刺激的な“五感”に飛びこんでくる戦場の生々しさ、残酷さも描いて欲しかったと思います。
抜けおちた記憶、自分自身の真実を見つけるため、監督はこの映画を作ったのでは、と感じました。イスラエル兵が、鬼畜のごとき存在ではなく、彼らも人間として深く悩んでいる、ということを示したあたりが、作品として評価されたのでしょう。驚くことに、それがアニメでデフォルメされていた戦場の光景が、一気に現実となるラストシーンです。アニメで観ていたのに、油断をすると突然嫌―な感じがして、圧倒的に戦場のシーンが映し出されて、ただただ悲惨な光景が広がっていくのですから。
2017年DVD鑑賞作品・・・11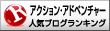 映画(アクション・アドベンチャー) ブログランキング/
映画(アクション・アドベンチャー) ブログランキング/
あらすじ:冬のバー。映画監督のアリは、旧友とひさしぶりの再会を果たした。
会話の途中。アリはふいにあることに気付く。ある戦時中の記憶が自分にはまったくないということに...。抜け落ちた過去。なぜ俺は覚えていない―?失った過去を求めて、アリは当時を知る戦友たちを訪ねていく。(作品資料より)

<感想>2008年度の、あの「おくりびと」とアカデミー外国語映画賞を競った話題のアニメーション作品です。どちらかというと、本作の方がオスカー本命だったそうです。ここで扱われている虐殺事件は、1982年9月16日から約3日間、イスラエル軍によるレバノン侵攻が進められ、サブラとシャティーラ地区のパレスチナ難民キャンプで大量虐殺が起きたことを題材にしています。

サブラ・シャティーラ地区はほぼ全滅状態で、本当に酷かった。この時の作戦コードネームが“カサチ”アラビア語で「切り刻む」という意味。もう言葉を失います。サブラ・シャティーラの難民キャンプに攻めて来たのは、レバノンのキリスト教マロン派右派で、ファランヘ党。命令を下して後押ししてやらせていたのが、アリエル・シャロン。当時の国防相アリエル・シャロンは、この虐殺事件で解任され、のちに2001年、イスラエルの首相に就任する。

このサブラ・シャティーラ地区の虐殺の首謀者として、シャロンは国際戦争法廷に告訴されます。彼はメチャクチャで、2000年東エルサレムのイスラム聖地に数百人の武装護衛を伴って訪れ、「エルサレムはすべてイスラエルのもの」と宣言し、和平の機運を壊し、パレスチナ側の抵抗運動を激化させてしまったのです。そのシャロンも2006年に、脳卒中で倒れ、いろいろ病を重ねて、今では政界を引退したそうです。時の流れを感じさせます。(上部の部分は資料より引用しています)
そんな中、本作はアニメーションとドキュメンタリーを融合させた斬新な手法で登場したわけですが、・・・1982年当時、19歳だった監督のアリ・フォルマン自身の実体験が基になっているそうです。従軍したはずなのに、まったくその記憶がないという。実際、そういう記憶の後遺症は有り得るから。
現地で虐殺を受けた人々にとっては、消したくても消えないトラウマが残っただろうし、また、フォルマン監督みたいに思い出したくても思い出せない場合もあるだろう。その悲惨な記憶をドラマや映画にするには、あまりにも難しく、幻想も含めて内省の旅を描いていくのに“アニメーション”という手法を選んだのは良く分かりますね。

レバノンの海岸、海辺に並んでいる建物、海兵隊のあったところなどは、かつては“中東のパリ”と言われた風景が精密に描かれて、もちろん戦闘シーンも印象的でした。ただし、この“アニメーション”で描かれている場面はちょっと踏み込みが足りないような気がした。
戦場から戻って、いつまでも消えずに残る記憶は、視覚的なものよりも、死体が腐っている臭い、焼け焦げている臭い、そういうものを感じ取れれば、なお良かったのでは。実写でも難しいことなので、そこまで望むのは残酷かもしれませんけど、見ているものにそういう刺激的な“五感”に飛びこんでくる戦場の生々しさ、残酷さも描いて欲しかったと思います。
抜けおちた記憶、自分自身の真実を見つけるため、監督はこの映画を作ったのでは、と感じました。イスラエル兵が、鬼畜のごとき存在ではなく、彼らも人間として深く悩んでいる、ということを示したあたりが、作品として評価されたのでしょう。驚くことに、それがアニメでデフォルメされていた戦場の光景が、一気に現実となるラストシーンです。アニメで観ていたのに、油断をすると突然嫌―な感じがして、圧倒的に戦場のシーンが映し出されて、ただただ悲惨な光景が広がっていくのですから。
2017年DVD鑑賞作品・・・11









