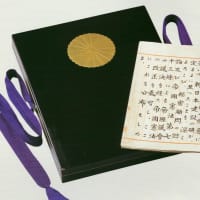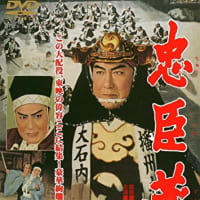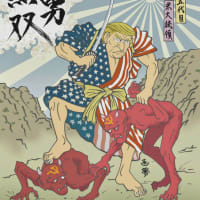元禄期に描かれた「燕子花屏風図」は傷みがひどくなり補修復元作業のため足掛け5年に渡って公開されませんでした。ようやく昨年秋に完成して、異例の秋の公開がありました。しかし今月からは美術館が改築工事に入るため、また3年半は見られなくなりそうです。
根津美術館は日本庭園も素晴らしく、現在庭園の池には「杜若」(かきつばた)の花が美しく咲き誇っています。関東にお住まいの方は是非この機会にご覧になってはいかがでしょうか。
今回はこの「燕子花屏風図」について少し書いてみたいと思います。
■「燕子花屏風図」
この作品は「国宝」に指定されており、左右二隻からなる屏風図です。伊勢物語の「八橋」の段を題材に描かれているとされています。八橋の図柄でお馴染みの板橋や人物は一切描かれておらず、燕子花(かきつばた)の花だけが描かれています。絵は金箔地に緑青(緑)群青(青)と三色のみで表現されています。
■「尾形光琳」
尾形光琳は京都の「雁金屋」という禁裏出入りの京都の呉服商に生れ、三十歳にして家督を継ぎますが、趣味の能楽や遊蕩三昧に明け暮れ、莫大な財産を湯水のように使い果たしてしまい、やがて借金生活を送るようになってしまいます。中年期以降に積極的に創作に励んだのも、借金を返す為でもあったようですが、貧窮が天賦の才能を花開かせたようです。
光琳の家系は「本阿弥光悦」や「俵屋宗達」等とも姻戚関係がある芸術一家であり、祖父の代に始めた「雁金屋」は多くの染物屋や織物屋にオリジナルのデザインを発注するような大店でしたから、幼少の頃から花鳥風月など、当時最高のデザインに囲まれて育ったことが光琳のアート感覚を培ったようです。また成人してからの豪奢な遊興生活がさらに、光琳の美的センスに磨きをかけたようにも思われます。
屏風図の構図を良く見ていると判で押したようなリズミカルな同じ構図の花がいくつかあるのに気がつきます。これは呉服地を染める際に使う「型紙」の手法を使用しているのが分かります。さすが京を代表する呉服商という光琳の出自を感じさせる部分です。
当時最も高価な画材を惜しげもなく使用した、絢爛豪華な屏風図を見ていると、『なるほど。並の絵師には絶対にこんな絵は描けないぞ!』といった言葉が思わず漏れてしまいそうになります。
しかし華麗ではあるが決して下品ではなく、花だけで構成されたシンプルな図柄から都会的で洗練された感覚が伝わってきます。光琳は絵画だけでなく、蒔絵や工芸など多彩な分野での作品があり、『元禄時代最高のアートディレクター』でありました。
続く
Copyright:(C) 2006 Mr.photon All Rights Reserved
 | 尾形光琳―江戸の天才絵師ウェッジこのアイテムの詳細を見る |