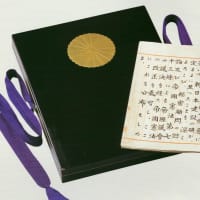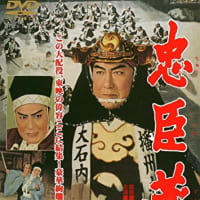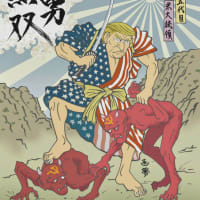■身分標識としての刀
図説 「大江戸さむらい百景」渡辺 誠 著 株式会社 学習研究社
( P234~P235)より転載
―― 豊臣秀吉と徳川家康の影響 ――
「刀は武士の魂」という精神的習俗が生まれるに至った経緯について考える時、少なくとも二つのことに注目する必要がある。一つは豊臣秀吉による「刀狩り」、さらに、秀吉に代って天下人となり武家政権を築いた徳川家康と初期将軍後継者たちの尚武策である。
刀狩りは、天正13年(1858)から同20年(文禄元年)までの七年間にわたって継続的に実施された、秀吉の重要政策の一つだった。実は刀剣を中心とする武器・武具は、中世においては武士のみならず、農民を含む一般庶民も所持していた。
ことに大小の刀を帯びることは、成人男子の「証」とされていた。秀吉は、この刀を農民・庶民が所持するのを禁じ、かつ没収したのだが、その主目的は何だったか。
一つには、民衆の一揆予防の手段として武装を解除すること。第二には、兵農分離をもって武士による民衆支配を強化すること。さらには、将士に対する恩賞用の名刀・良刀を徴収する、という目的もあった。
こうして庶民の武装解除、兵農分離を推進した秀吉の刀狩りは、徳川家康の創業になる江戸幕府にも、形を変えて踏襲され、進められた。二代秀忠、三代家光の治世に、相次いで発せられた刀剣についての禁令は、治安にかこつけた巧妙な刀狩りであった。
これによって農民・町人の帯刀は、限られた人間以外には免許されないことになった。日本刀は、そして武士の占有せる身分標識となっていった。刀には武士の霊魂が宿る、という習俗が形成された、これが一つの背景だったのである。
さて、もう一つの背景について述べるには、徳川家康が日本刀、およびその操法である剣術に、自ら身をもって深い関心を示した、ということが重要である。そもそも「力の信者」たる家康は、武を重んじ、剣術に優れた兵法者を優遇したが、このようなことは織田信長にも、豊臣秀吉にもないことだった。
そういう家康が天下を掌握する。それは剣術の価値を、大名歴々に認めさせる気運を喚起した。剣を好み、刀剣を尊んだ家康の遺風は、秀忠・家光の尚武策に継承された。
そして、かれらによって確立されていった幕藩体制化の武士にとっての「刀は武士の魂」感が習俗として定着していったのである。こうしてみると、汪戸期のさむらいと、刀との関わりは、政策と分かちがたく結ばれているといえる。
(転載終了)
続く

【今日のミコトノリ】
恋の鞘当てという言葉はすっかり死語になったニャン!