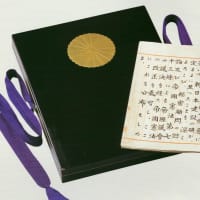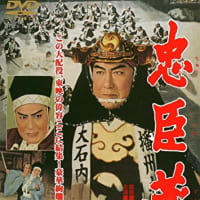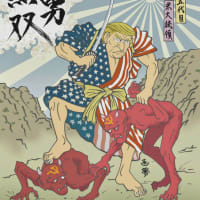以前はあまり訪れる人もなく、ゆったりとと思う存分に刀剣を鑑賞出来たのだが、最近は刀剣乱舞の影響もあって、平日でも若い女性で賑わっているのには驚かされる。刀剣は美術工芸品としての美しさもさることながら、その刀に纏わる歴史上の人物の物語が面白い。その辺りの話題は多くの方がブログやホームページで紹介されているので、刀剣に纏わる話をもう少し広げ、武士と刀という内容で、数回に分けてご紹介してみたいと思う。
■「武士の魂」 (P236~P237)より転載
「図説 大江戸さむらい百景」渡辺 誠 著 株式会社 学習研究社
― 刀を力と勇気の表徴とした武士たち ー
「武士道は刀をその力と勇気の表徴となした」とは、たびたび引いている新渡戸稲造(矢内原忠雄訳・岩波文庫)の第13章「刀・武士の魂」の冒頭をかざる文章だ。同書はまた、刀は武士の「忠義と名誉の象徴」である、とも述べる。だから、刀は武士の「魂」といえる。
―― 大小二本の刀 ―― 大刀小刀、もしくは刀脇差と呼ばる ーー は決して彼の身辺を離れず、家にありては書斎客間のもっとも目につきやすい場所を飾り、夜は容易に手の届く所に置かれて彼の枕頭を守る。刀は不断の伴侶として愛せられ、固有の呼び名を付けられて愛称せられ、尊敬のあまりほとんど崇拝せられるに至る。となるのである。
武士は昼も夜も四六時中、刀を身辺から離すことがなかった。旧仙台藩士・小野清は、その剣道の師匠である山田善速が、来客と応対している時はもちろんのこと、家族と食小をする時でも、小刀を自分の左側に、すぐにも抜きつけられるように刃を左に向けて置いていた、と述懐している。
ところで、「刀は武士の魂」と新渡戸がいうその刀とは、その文章に明記されているように大小、すなわち刀と脇差である。 しかし、武士が台頭した平安時代中期からの歴史でいえば、彼らが刀・脇差を腰に差すようになったのは、そんなに古いことではない。武家政権700年のうち、大小を差すことが儀礼とされていたのは、後期のおよそ260年間の江戸時代に限られている。
武士の魂たる「刀」は、正しくは「打刀」といい、日本刀の長い歴史の上では限定された刀といわねばならない。それ以前には、刀といえば、刃を下にして刀身を金具や紐で腰に佩用する「太刀」のことであった。「打刀」という用語は、古くは鎌倉時代の史料に見えるが、これは卑賤の者や雑兵が帯用するものとされ、したがって作りが粗悪のものが多かった。
それが室町時代になると、太刀の差添えとして用いる武人が多くなったようである。そうして桃山時代となると、太刀は全くすたれて打刀がそれに取って代り、かつての打刀の如く今度は脇差が差添えとなり、ここに「大小」の風習が生まれる。
下って江戸時代に至り、かくて大小が武士の儀礼的習俗として定着するのである。腰の刀・脇差が、武士の精神の宿る、かけがえのないものとして尊ばれるようになったのは、それ以後のことである。
(転載終了)
続く

【今日のミコトノリ】
猫川海老ぞり???