http://nezu621.blog7.fc2.com/blog-entry-3836.html ねずさんのひとりごとさんより
2018年08月01日
よろこびも、たのしさも、もちろん笑顔の連鎖ではありますが、けれども決してそれだけではない。
よろこびも楽しさも、もっとずっと深い意味があるのだということを、純粋な日本人であれば、あるいは政治的に偏向していない魂を持った人間であれば、国籍や民族の如何に関わらず、実は誰もが気付くことができるのです。

我が国の神語(かむかたり)では、創世神であるイザナキとイザナミが「よろこびあふれる楽しい国」を築こうとして、この世をつくられたのだとあります。
これを「豈国(あにくに)」といいます。
ところがそんな「よろこびあふれる楽しい国」に、ヤマタノオロチなど、次々と試練が襲います。
そしてその都度、神々は知恵と勇気をふりしぼり、あるいは力を合わせてその困難に立ち向かって問題を解決していきます。
なぜそのようになるかの答えは簡単に見つかると思います。
毎日がよろこび、毎日が楽しみばかりでは堕落してしまうからです。
苦労があり、その苦労を乗り越える。
その乗り越える知恵と力と勇気と協同にこそ、実はよろこびがあり、楽しさがあるというのが、我が国の神語の教えです。
ですから「よろこびあふれる楽しいクニ」とは、ただ馬鹿騒ぎをしているだけのクニのことではありません。
問題を解決するためには、勤勉でなければならず、日々努力の積み重ねでなければならず、困難に負けず、乗り越えるだけの心も体も鍛えていかなければならず、協調のためにはときに我慢もしなければならず、ときに勇気を振り絞って戦うことも必要です。
そしてそれが、どこまでも神々の御分霊のひとつである、人々のために行われるとき、はじめてそこに「よろこび」があります。
つまり日本的「よろこび」とは、自分だけが良い思いをしたり、自分だけが贅沢をしたり、自己満足のために他人を犠牲にしたりすることの対極、すなわちどこまでも「みんなのために、みんなとともに」よろこびがある、とされているものです。
ここでいうみんなとは、自分を取り巻くごく一握りの家族であったり、王国の貴族たちであったり、特定の民族や国家だけを指すものではありません。
あまねく世界の人々が、ひいては地球規模のあらゆる生命体のみんなが、よろこびあふれる楽しい地球を担っていく。
そのために自分にできることは、ほんの少しの小さなことかもしれないけれど、その小さなことをみんなで積み重ねていく。
それが日本人の日本的よろこびです。
さらにこのよろこびは、日本仏教の考え方ですと、さらに5段階に分けられるのだそうです。
それが、「天界(てんかい)、声聞界(しょうもんかい)、縁覚界(えんかくかい)、菩薩界(ぼさつかい)、仏界(ぶっかい)」で、右に行くほど、位の高いよろこびになります。
専門家ではありませんので、間違いもあるかもしれませんが、ねず式で概略すると、
天界 試合に勝ったとか、物事が成就したときなどの一瞬のよろこび
天にも登るような幸せな瞬間の気持ち
声聞 人の話を聞いたり映画や演劇などを鑑賞したり、
本を読んだりして長く余韻のある感動を得たときのよろこび
縁覚 折に触れて一瞬の悟りを得るような感動のよろこび
菩薩 人にやさしくするよろこび。
仏界 何人にもおかされない無限のよろこび
つまり仏教界においても、実は本当のよろこびとは、馬鹿げた冗談を言い合ってゲラゲラ笑っているだけの、いまどきのテレビのようなものではなくて、生命そのもの、ないしは魂そのもののよろこびのことを言っているわけです。
ちなみに「よろこび」は大和言葉ですが、漢字では
喜び
悦び
歓び
慶び
欣び
熙び
などの文字が充てられています。
「喜」は、上の「壴」の部分が壁掛け型の太鼓で、下に「口」があり、そこから太鼓を叩いて喜び合う象形になっています。
「悦」は旧字が「悅」で、心+八+兄の組み合わせから、八(たくさんの)立派な兄が来てくれたような気分というわけで、たのもしくてうれしい気持ちを表す会意象形文字です。
「歓」は、「欠」があくびを意味することでもおわかりなように、雀を見張っているミミズクがあくびをしているわけです。つまり権力者の見張りが居眠りをしているわけで、その間、人々はうれしいというわけです。いかにも漢字発祥の国のお国柄が出ているようでおもしろいです。
「慶」は廌+心+夂の組み合わせで、廌は穢れた神獣です。
その神獣にやられるところを、間一髪、心臓(心)を逃す(夂)ことができたというわけで、まさに間一髪の僥倖を得た、といったものが字源になっています。
「欣」は、手斧に欠(あくび)で、斧を持って仕事をしている人があくびをしている。つまりのんびりまったりできるということで、うれしい。
「熙」は、巸+火から成り立ちますが、巸というのは、母親が赤ちゃんに母乳を飲ませている象形です。その母子をともに火で炙(あぶ)る。つまり食べてしまうわけですが、それがどうやら彼らにとってはよろこびらしい。ちなにみに日本人は、この字に「ひかる・ひろい・やわらぐ・よろこぶ・たのしむ」といった訓読みを与えました。そうすることで日本人は、この漢字が持つマイナスの部分を取り去っています。
上の6つの漢字のもともとの成り立ちをご覧いただいておわかりいただけると思いますが、漢字文化圏での「よろこび」は、いずれも瞬間的なよろこびであり、自分だけのよろこびでしかありません。
上の日本仏教の考え方に従うなら、瞬間的な満足を意味する天界のよろこびにさえも至らない。
なぜなら自分だけのよろこび、自分だけの満足だからです。
ところが日本的よろこびはそうではなくて、声聞、縁覚、菩薩、仏(しょうもん、えんかく、ぼさつ、ほとけ)と、瞬間だけではない、もっと深い、自他ともにあるよろこびです。
カタカムナによれば、よろこびは
「よ」は、新しいとか陽、
「ろ」は、空間を抜けること
「こ」は、出入り
「び」は、根源
をそれぞれ意味するのだそうです。
つまりよろこびというのは
「既存のコチコチ頭を脱して新しい気持ちで根源に至る」
すなわち陋習(ろうしゅう=古くなった殻)を脱して、新たに新鮮な気持ちでものごとの根源に触れ、それによって新たな道を拓き、未来を築くことを言います。
そのためには当然、自分ひとりだけではなくて、周囲のひとびとみんなの協力や共感が不可欠で、だからこそみんなで力を合わせて、難局を乗り越え、新しい時代を築いていく。
この場合のよろこびは、瞬間的なよろこびではなくて、未来につながり、未来を担う、つまりいま生きている人たちばかりか、これから生まれてくる命にまで至る、壮大なよろこびになります。
それが日本人の日本人的よろこびなのです。
昨今「豈国(よろこびあふれる楽しい国)」のことを書くと、そこで述べているよろこびや楽しさのことが、あたかもテレビのくだらない瞬発芸のお笑いの意味でしかないような捉え方をする人が中においでになると知ってびっくりしました。
昨今の若者たちの、
「人を笑わせたりよろこばせる職業に就きたい」
「災害支援活動に参加してみんなによろこんでもらいたい」
「音楽を通じてみんなによろこばれたい」
等々という気持ちは、日本人の若者であれば、それは単に瞬間芸のお笑いのことを言うのではなくて、いずれも未来にひろがる幸せを届けたいという日本的意味におけるよろこびであろうと思います。
若者たちは、神話教育を受けていなくても、学校で左傾化した日教組教育を受けて育っても、日本的よろこびをちゃんと知っているのです。
これこそ人は魂の乗り物であることの証左です。
よろこびも、たのしさも、もちろん笑顔の連鎖ではありますが、けれども決してそれだけではない。
よろこびも楽しさも、もっとずっと深い意味があるのだということを、純粋な日本人であれば、あるいは政治的に偏向していない魂を持った人間であれば、国籍や民族の如何に関わらず、実は誰もが気付くことができるのです。
お読みいただき、ありがとうございました。

転載、させていただいた記事です
・
ザ・リバティ2018年9月号 ねずさんのひとりごとさんでお馴染み、日本の心を伝える会 代表 小名木善行氏インタビューが記事に (*´∇`*)
・人を右か左かで分ける二分法の怪しさとは ねずさんのひとりごとさんより
・大和心を語るねずさんのひとりごと 血や死や女性の穢れなどという概念は日本にはもともとなかったもの
・急速に目覚めている日本人
・自衛隊反対と掲げた集団に殴りかかった若者











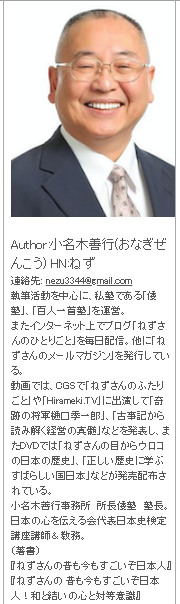






よく似ていた先輩が
死んだちゃん
福耳で、日蓮宗の僧侶めんっきょ
持っていたの・・・