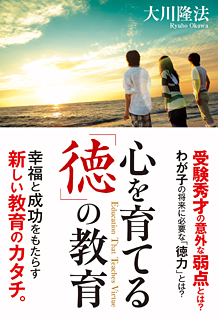書籍「心を育てる『徳』の教育」
【 自制心 】《 自制心は「リーダーになる重要な要件」》
●「目立たなかった子」が意外にリーダーになる
小さいころには親や先生の価値観とは少し違う子が、あとでリーダーとして出てくることが多く、「予想外だった」とよく言われます。そして、「奥手だったのに」「引っ込み思案だったのに」「あまりものを言わない子だったのに」「目立たない子だったのに」などと言われたりするのですが、そういう人が、けっこうリーダーになるのです。‥‥
自分の本能を抑え、自制するなかで、それが、単に「行動を抑制する」ということだけではなく、自分が人に迷惑をかけることを抑止し、他の人々のために、多少なりとも気配りをしたり、「他の人のためになるようなことに、自分の時間やお金、技能などを少しでも役立てよう」という心が働いていたりすると、その人は自然とリーダーになってくるのですが、それについては、「なるほど。そういうことなんだな」と分かります。これは、まっとうなかたちでは、そう簡単には教えてもらえません。そのため、自制心のあるリーダーには、自制心が心の深いところから出てくる場合と、それを経験的に学んでいく場合とがあるのですが、学校教育のようなものでバシッと教わるわけではないのです。
いずれにしろ、自制心は、意外と「リーダーになっていくための重要な要件」なのです。


●「わがままで感情が露骨に出る人」は動物に似ている
欲望のままに突っ走っていくような人は、一見、華やかですし、周りの人たちも「すごいなあ」と思うことはあるのですが、その人についていったら滅びることが多いのです。
「信用かある人」は、たいていの場合、「自制心がある人」です。「信用がない人」の場合を考えてみると、その人は、やはり、わがままで自分中心です。そのため、自分の「喜怒哀楽」の感情が露骨にスッと出てきて、「あれがしたい。これがしたい」と言いますし、自分にとって不利になったらカッと怒ります。また、自分にとって、ものすごくよいことがあったら、猫撫で声になり、とろけるようになってしまいます。
このように、「喜怒哀楽」の感情が、あまりにもストレートに、あっさり出てしまいます。ただ、これは、動物によく見られる傾向ではあるのです。‥‥
そうした、動物としての本能と同じような行動をそのまま取る人間は、自分の感情に非常に忠実なので、偽りはないのですが、そういう人からは、「感情には忠実でも、何らの鍛練や修行、努力がなされていない」という印象を受けます。その意味で、‥自然ではあるのですが、平凡でもあり、特に、リーダーたる要件や資格を満たさないのです。
 画像はイメージ
画像はイメージ
●「状況に合わせて自分を変えていく力」を持とう
(一部抜粋)
長く人を惹きつけるためには、やはり、「そのときそのときの、いろいろな状況、環境の変化や事件に合わせて自分を変えていく力」が必要です。「自分を律して変えていき、状況に適応していく力」が要ります。
その意味で、「自制心」という側面から見た場合のリーダー像があります。本能や感情に揺り動かされ、突き動かされて、それを止めることができない人は、冷静さを欠いており、「全体の幸福」を考えるにはあまりふさわしくないのです。
要するに、自分のことしか考えていないため、その人がリーダーになると、結局は、他の人々を滅ぼしたり、害を与えたりするようなことになりかねないわけです。
● 自制心を養うための「意志を鍛える方法」①・・・勉強
リーダーには自制心が必要ですが、自制心は、一瞬でできたり、一日や二日でできたりするものではありません。それは、長い年月をかけて養成していくものであり、それをつくっていくものは、絶えざる「意志の鍛練」なのです。
現代において、この「意志の鍛練」をするオーソドックスな方法は、だいたい二通りあります。
一つは「勉強」です。‥‥
リーダーになる人は、受験等の勉強を通して自分の意志を鍛えなくてはなりませんし、欲望に流されていては目的を達成できないので、自分が好きなものを、一時期、脇に置き、遊びたい欲望や怠けたい欲望を、一時期、抑えなくてはなりません。夜は早く寝たいし、朝はゆっくり寝ていたいけれども、その思いを抑えて勉強する。天気がよいので外にパッと遊びに行きたいけれども、その気持ちを抑えて、やはり勉強する。‥‥試験の出来が悪ければ、‥心を入れ替え、試験が終わってすぐに勉強を開始する。
これらは、一見、本能に反することですが、大いなる目的や、「自分自身をもっと高める」ということのために、勉強を “使う” 場合があるのです。
● 自制心を養うための「意志を鍛える方法」②・・・スポーツ
もう一つは、やはり「スポーツ」でしょう。
スポーツでも、「ただ体を動かせばよい」ということだったら、「意志の鍛練」まで行かず、刹那的なものかもしれません。
しかし、スポーツで、もう少しきっちりとした目標を持ち、「ある程度のところまで行きたい」と考える人もいます。例えば、「野球のチームで優勝したい」とか、空手や柔道だったら、「段ぐらいは取りたい」とか、「試合で勝ちたい」とか、目標はいろいろあります。そのように、一つの目標を立てて精進していくなかで、「体の鍛練」と同時に「意志の鍛練」がなされるわけです。‥‥
スポーツをすると、筋肉は痛み、一見、苦しい。苦しいけれども、それをやり遂げたあとに来るのは爽快感です。そういう、「将来に来るもの」を喜びとする気持ちを養うことが大事なのです。それは「勉強」と「スポーツ」で養えるのです。
警戒心の強い野生のマーモットにお気に入り認定をされた8歳の少年


・
書籍「心を育てる『徳』の教育」