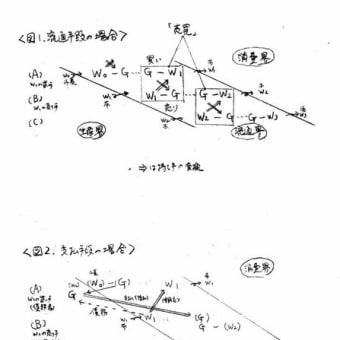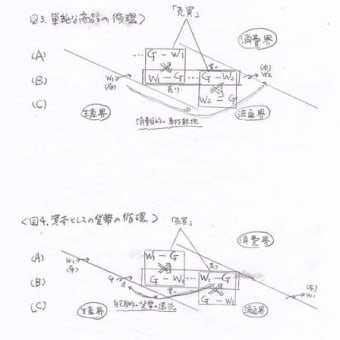「読む会」だより(24年10月用)文責IZ
(9月の議論など)
9月の「読む会」は厳しい暑さが続く中、15日に開催されました。
(7月の議論)の所では、有用労働の結果としての生産物が全面的に交換されることで、生産物が交換価値をもつ(商品になる)ということでよいのか、という質問が出ました。チューターは交換価値とは、それらの中に同質な人間労働が含まれているということが交換を通じて表わされるということなのだから、そういうことでよいのでないかと答えました。
(復習1)の所では、価値が支出労働時間で決まるという点について質問したが、労働時間について直接的な形でだけ考えていたかもしない、という意見が出ました。疑問に答えるものかどうかは分かりませんが、次回、『経済学批判』での説明について紹介することになりました。
また、「社会的な労働が人々によって意識的に組織され、諸個人の労働の同等性が担保される社会であれば……」と触れた点に関連して、そうした共同社会の具体的イメージはどういうものか、という質問が出ました。『資本論』第1章4節では、簡単に「共同の生産手段で労働し自分たちのたくさんの個人的労働力を自分で意識して一つの社会的労働力として支出する自由な人々の結合体」(全集版、P105)と触れられていますが、次回『ゴータ綱領批判』からの一節を紹介することになりました。
説明(1.)については特に質問、意見は出ませんでした。
【『経済学批判』より】(太字は原文、アンダーラインはチューターのものです)
ここでは一か所だけを挙げておきます。資本論の参考になるでしょうから『経済学批判』の冒頭部分(岩波文庫版、A4で6枚)をプリントしておいて、必要な方にはお渡しします。
・「……まず最初に、労働の無差別な単純性とは、さまざまの個人の労働が同質であり、かれらの労働が同質なものとしてたがいに関連しあうということであって、しかもこの関連は、あらゆる労働が同質な労働に事実上還元されることによっておこなわれているのである。各個人の労働は、交換価値で表示されるかぎり、同質性というこの社会的な性質をもち、またあらゆる他の個人の労働にたいして同質なものとして関連させられているかぎりにおいてのみ、かれらの労働は交換価値で表示されるのである。
さらに交換価値にあっては、ひとりびとりの労働時間が直接そのまま一般的労働時間としてあらわれ、また個別化された労働のこの一般的性格が、その社会的性格としてあらわれるのである。交換価値で表示されている労働時間は、個々人のそれではあるが、他の個々人とは何の区別もない個々人の、同質の労働をおこなっているかぎりでのすべての個々人の労働時間であり、したがってあるひとりにとって一定の商品の生産のために必要とされる労働時間は、ほかのだれでもが同じ商品の生産についやすであろう必要労働時間なのである。それは個々人の労働時間であり、かれの労働時間ではあるが、しかしそれはすべての個人に共通な労働時間としてだけそうなのであり、したがってこの労働時間にとっては、それがだれの労働時間であるかはどうでもよいのである。それは一般的労働時間として、ある一般的生産物で、ある一般的等価物、対象化された労働時間のある一定量<つまり貨幣>で表示される。……」(岩波文庫版、P28~29)
【『ゴータ綱領批判』より】
・「生産手段の共有を土台とする協同組合的社会の内部では、生産者はその生産物を交換しない。同様にここでは、生産物に支出された労働がこの生産物の価値として、すなわちその生産物に具わった物的特性として現われることもない。なぜなら、いまでは資本主義と違って、個々の労働は、もはや間接にではなく直接に総労働の構成部分として存在しているからである。「労働収益」という言葉は、今日でも意味が曖昧だからしりぞけるべきものだが、こうして全くその意味を失ってしまう。
ここで問題にしているのは、それ自身の土台の上に発展した共産主義ではなくて、反対に今ようやく資本主義社会から生まれたばかりの共産主義である。したがって、この共産主義社会は、あらゆる点で、経済的にも道徳的にも精神的にも、その共産主義社会が生まれ出てきた母胎たる旧社会の母斑をまだ帯びている。したがって、個々の生産者は、彼が社会に与えたのと正確に同じだけのものを──控除をしたうえで──返してもらう。個々の生産者が社会に与えたものは、彼の個人的労働量である。例えば、社会的労働日は個人的労働時間の総和から成り、個々の生産者の個人的労働時間は、社会的労働日のうちの彼の給付部分、すなわち社会的労働日のうちの彼の持分である。個々の生産者はこれこれの労働(共同の元本のための彼の労働分を控除したうえで)を給付したという証明書を社会から受け取り、この証明書をもって消費手段の社会的貯蔵のうちから等しい量の労働が費やされた消費手段を引き出す。個々の生産者は自分が一つの形で社会に与えたのと同じ労働量を別の形で返してもらうのである。
ここでは明らかに、商品交換が等価物の交換であるかぎりでこの交換を規制するのと同じ原則が支配している。<しかし>内容も形式も変化している。なぜなら、変化した事情の下では誰も自分の労働の他には何も与えることができないし、また他方、個人的消費手段の他にはなにも個人の所有に移りえないからである。しかし、個人的消費手段が個々の生産者の間に分配される際には、商品等価物の交換と同じ原則が支配し、一つの形の労働が別の形の等しい量の労働と交換されるのである。」(国民文庫版、P25~26)
(説明)第6篇労賃第17章労働力の価値または価格の労賃への転化(2回目)
(1.古典派経済学は日常生活から無批判的に「労働の価格」あるいは「労働の価値」という表現を借りてきているが、労働者が商品として売るものは「労働」ではなくて「労働力」である)
前回終了しました。
(2.「労働の価値」という表現では、価値概念<価値の実体としての社会的に同質な抽象的労働>はまったく消し去られて、その反対物<具体的な労働がもつ性格>に転倒される。この表現は、労働日が必要労働と剰余労働とに、あるいは支払い労働と不払い労働とに分かれることを隠蔽して、全ての労働が支払い労働として現れることに役立つ)
・「そこで、我々はまず第一に、労働力の価値と価格が労賃<すなわち労働そのものの価値と価格として現象しているもの>というそれらの転化形態にどのように現われるか、を見ることにしよう。
人の知るように、労働力の日価値は労働者のある一定の寿命を基準として計算されており、この寿命には労働日のある一定の長さが対応する。仮に、慣習的な1労働日は12時間、労働力の日価値は3シリングで、これは6労働時間を表わす価値の貨幣表現だとしよう。もし労働者が3シリングを受け取るならば、彼は12時間機能する彼の労働力の価値を受け取るわけである。今、もしこの労働力の日価値が1日の<支出>労働の価値として言い表されるならば、12時間の労働は3シリングの価値をもつ、という定式が生ずる。@
労働力の価値は、このようにして、労働の価値を、または、貨幣で表わせば、労働の必要価格を規定する。反対に、もし労働力の価格が労働力の価値からずれるならば、労働の価格もまたいわゆる労働の価値からずれるわけである。
<いわゆる>労働の価値というのは、ただ労働力の価値の不合理な表現でしかないのだから、当然のこととして、労働の価値<すなわち本来的には労働力の価値>はつねに労働の価値生産物<生産物の価値のうち不変資本部分を除く、必要労働+剰余労働の部分>よりも小さくなければならない、ということになる。なぜならば、資本家はつねに労働力それ自身の価値の再生産に必要であるよりも長く機能させる<これこそ資本主義的生産の根底である!>からである。前の例では、12時間機能する労働力の価値は3シリングであって、これは、その再生産に労働力が6時間を必要とする<生活手段の>価値である。ところが、この労働力の価値生産物は<3シリングではなくて>6シリングである。なぜならば、労働力は実際には12時間機能しており、そして労働力の価値生産物は労働力自身の価値によってではなく労働力の機能の継続時間によって定まるのだからである。こうして、6シリングという価値をつくり出す労働は3シリングという価値をもっている、という一見して馬鹿げた結論が出てくるのである。
さらに、人の見るように、1労働日の支払い部分すなわち6時間の労働を表わしている3シリングという価値は、支払われない6時間を含む12時間の1労働日全体の価値または価格として現れる。つまり、労賃という形態<労働の価格という現象形態>は、労働日が必要労働と剰余労働とに分かれ、支払い労働と不払い労働とに分かれることのいっさいの痕跡を消し去るのである。全ての労働が支払い労働として現れるのである。@
<これに反して>夫役では、夫役民が自分のために行なう労働と彼が領主のために行なう強制労働とは、空間的にも時間的にもはっきりと感覚的に区別される。奴隷労働では、労働日のうち奴隷が彼自身の生活手段の価値を補填するだけの部分、つまり彼が事実上自分のために労働する部分さえも、彼の主人のための労働として現れる。彼の全ての労働が不払い労働として現れる。賃労働では、反対に、剰余労働または不払い労働でさえも、支払われるもの<労賃>として現れる。前の方の場合には奴隷が自分のために労働することを所有関係が覆い隠すのであり、後の方の場合には賃金労働者が無償で労働することを貨幣関係が覆い隠すのである<このたよりのP5、下線部分を参考ください>。
このことから、労働力の価値と価格が労賃<という現象>形態に、すなわち労働そのものの価値と価格とに転化することの決定的な重要さが分かるであろう。@
<不払労働の隠蔽という>このような、現実の関係を目に見えなくしてその正反対を示す現象形態にこそ、労働者にも資本家にも共通な一切の法律観念、資本主義的生産様式の一切の欺瞞、この生産様式の全ての自由幻想、俗流経済学の一切の弁護論的空想は基づいているのである。
資本と労働との交換は、……最後に、労働者が<労賃と引き換えに>資本家に提供する<労働力商品の>「使用価値」は、実際には彼の労働力ではなくてその機能なのであり、たとえば裁縫労働とか製靴労働とか紡績労働とかいう一定の有用労働である。その同じ労働が別の面<すなわち社会的生産の面>から見れば一般的な価値形成要素<すなわち総労働の一部分としての社会的労働時間>であるということ、この性質によって労働<労働力の使用価値>は他の一切の商品から区別されるのであるが、それは普通の意識の領域の外にある<科学によって発見されねばならない>のである。」(全集版、P698~701)
「労働の価値」という姿では不払労働も支払労働と共に“支払われたもの”として現われるというここでの説明はとても分かりやすいように思われます。労賃(賃金)が、実際には労働支出の後になって支払われるという事情や、それが労働日の長さによって変動するとか、あるいは同じ機能を果たす労働者のあいだでも個人的差異がある等々の事情があるために、私たち労働者ですら個人的な生活や日常的な感覚では、労賃(賃金)は労働の対価、あるいは「労働の価値および価格」であるように見えます。しかしながら第一に、労働力“商品”には普通の商品とは違って、その活動・機能によって「価値」を創造するという特別な使用価値があるのであって、だからこそ労働力商品に対してはその生産に必要な対価を支払ってもそれ以上の価値(労働時間)を生み出すことが可能なのでした(資本と労働との交換の“本質“)。また第二に、実際には労働力の再生産のための“既存の”必要生活手段の価値が労賃として支払われるのであって、それが労賃と労働とが交換されるように見えるのは仮象ないし“現象”なのでした。こうした労賃の意義を理解するためには、ここで触れられているように、社会に対する歴史的な考察が(つまり唯物史観が)不可欠だということと思われます。
(3.労賃は資本家の前貸資本の一部──可変資本部分──であって、それは実際にはすでに生産されている労働者の生活手段として商品資本の一部をなしている)
労賃が「労働」の対価ではなくて「労働力」の対価であるということの他に、労賃についてもう一つ忘れてはならないことがあるように思われます。それは労賃は資本家の前貸資本(貨幣)の一部──可変資本部分──であって、それは実際には労働者の生活手段としてすでに生産されている商品資本の一部分をなしている、あるいはそれらへの転化が前提されている、ということです。労働力の価値の等価である生活手段があらかじめ生産されているからこそ、労働者はその賃金でそれらを購買して自らを再生産できるのであり、同時に全体としての資本はその前貸可変資本部分を“回収”することで自らを資本として再生産できるのです。
これらの点について資本論の草稿(最終的には1巻の本文に吸収されるなどして、独立したまとめの章としては残りませんでした)である『直接的生産過程の諸結果』から引用しておきます。
・「資本の生産過程は、その現実の面を見れば──または、有用労働によって使用価値をもって新たな使用価値を形成する過程としてみれば──、まず第一に、現実の労働過程である。……
第二に。生産手段は、一定の商品として、たとえば綿花や石炭や紡錘などとして、流通から労働過程に入って行く。これらのものは、それらがまだ商品として流通していた時に持っていた使用価値の姿で労働過程に入る。この過程に入れば、次にはそれらの使用価値に対応した、物としてのそれらの物的に属している諸属性をもって、たとえば綿花としての綿花というような諸属性をもって、機能する。@
ところが、資本のうち我々が可変資本と名付ける部分、とはいえ労働能力と交換されることによってはじめて現実に資本の可変部分に転化させられる部分は、そうではない。その現実の姿から見れば、この貨幣──資本家が労働能力を買うときに支出するこの資本部分──が表わしているものは、労働者の個人的消費に入るべき、現に市場にある(またはある期間中に市場に投げ入れられる)生活手段に他ならない。貨幣はただこの生活手段の転化した形態にすぎないのであって、この<貨幣という>形態は、労働者が貨幣を受け取れば、すぐに生活手段に再転化するのである。この<生活手段への>転化も、それからまたこれらの<生活手段>商品の使用価値としての消費も、直接的生産過程とは、より詳しく言えば労働過程とは、直接には関係のない、むしろこの過程の外で行なわれる過程である。@
資本の一方の部分<可変資本部分>は、またそれを通じて総資本は、まさに、一つの不変的な価値量である貨幣の代わりに、またはその貨幣の実現でありうる同様に不変な価値量である生活手段の代わりに、それとは正反対の一要素すなわち価値を創造する生きている労働能力が交換によって受け取られるということによって、一つの可変量に転化させられるのである。そして、この労働能力は、価値を創造する要素として、<その支出量に応じて>より大きいこともより小さいこともあり得る。すなわち、可変量として現われうるのであって、一般にどんな事情のもとでも、すでに生成した量としてではなく、ただ、流動しつつある、生成しつつある──したがって違った限度で含まれている──生成しつつある量としてのみ、生産過程に要因として入るのである。……@
いずれにせよ、労賃に投ぜられた資本部分は、それが現実の姿すなわち労働者の消費に入る生活手段という姿をとったならば、形式的には、もはや資本家にではなく労働者に属する部分として現われる。だから、この部分が生産過程に入る前に商品として──生活手段として──持っている使用価値の姿は、それがこの過程の中でとる姿とは、すなわち活動的に発揮されつつある労働力の、したがって生きている労働そのものの姿とは、全く違うのである。だから、このことは資本のこの部分を生産手段の姿で存在する部分<不変資本部分>から独自に区別するのであって、このことはまた、なぜ資本主義的生産様式の基礎の上では生産手段は特にすぐれた意味において、生活手段からは区別されて、そして生活手段に対立して、それ自体としての資本として現われるのか、ということの一つの理由でもある。@
このような<生産手段がそれ自体としての資本であるかの>外観は──後に展開されることを別にすれば──次のことによって簡単に解消する。すなわち、生産過程の終わりで資本がとる使用価値の形態は生産物の形態であって、この生産物は生産手段の形態でも生活手段の形態でも存在し、したがって両方とも等しく資本として存在しており、したがってまた生きている労働能力に対立して存在している、ということによって簡単に解消するのである。」(国民文庫版、P19~25)
資本の生産過程の全体を見れば、「労賃」も前貸資本の一部である可変“資本”がとる一時的な姿であって、労賃がもつ貨幣形態に、言い換えれば商品所有者としての平等な関係に目を奪われてはいけないと、そう語っているのではないでしょうか。
(4.労賃になぜ大きな個人的差異が生ずるかについての補足)
労賃(賃金)が「労働力」の価値または価格の現象形態であり、したがって市場にある必要生活手段の等価であるとしても、ではなぜそこに大きな個人的な差異があるのか、という疑問を持つ方もいることでしょう。前項と同じく『直接的生産過程の諸結果』から参考になる個所を補足しておきます。
・「奴隷の場合には報酬の最低限は彼の労働には関係のない不変な大きさとして現われる。自由な労働者の場合には、この彼の労働能力の価値も、それに相当する平均労賃も、このような、予め定められている、彼自身の労働には関係のない、彼の単に肉体的な欲望によって規定されている限界の中で現れるのではない。この<労働者の>場合にはこの階級の平均は、すべての商品の価値がそうであるように、多かれ少なかれ不変である。しかし、この平均は個々の労働者にとってはこの直接的な現実性において存在するのではなくて、彼の賃金はこの最低限より高いことも低いこともありうる。労働の価格<すなわち労賃>は、労働能力の価値よりも、ある時は低くなり、ある時は高くなる。さらに、労働者の個性の働く余地が(狭い限界の中でではあるが)あって、それによって、別々の労働部門のあいだでも、同じ労働部門の中でも、労働者の勤勉や技能や体力などに応じて賃金の相違が生ずる。しかも、この相違は、一部分は彼自身の個人的な業績の程度にしたがって定められるものである。だから、賃金の高さは、彼自身の労働の結果およびその労働の個別的な質の結果によって変化するものとして現われる。@
このことは、出来高賃金が支払われる場合に、特に顕著になってくる。出来高賃金は、すでに示したように、資本と労働との一般的な関係を、また剰余労働と必要労働とのそれを、少しも変化させないにもかかわらず、それによってこの関係は個々の労働者にとっては違った仕方で表わされ、しかも彼の個人的な業績の程度にしたがって表わされる。@
奴隷の場合には特殊な体力や技能が彼の身柄の売買価格を高くすることもありうるが、それは彼自身には何の関係もない。自分の労働能力の所有者自身である自由な労働者の場合には、そうではない<彼の労働力の価値に影響する>のである。
この労働能力の<平均より>より高い価値は、<奴隷商人にではなく>彼自身に支払われなければならないのであって、より高い賃金に表わされる。だから、ここ<賃金労働>では、特殊な労働の必要とする労働能力が、より高度に発達したもので、より大きい生産費を必要とするものであるかどうかにしたがって、大きな賃金差が広く存在するのである。@
したがってまた、一方では個人差が物を言う余地が開かれており、他方では特有な労働能力の発達への刺激が与えられているのである。たとえ、大量の労働は多かれ少なかれ技能的でない労働から成っておらざるを得ず、したがってまた大量の労賃も単純な労働能力の価値によって規定されておらざるを得ない、ということは確かであっても、個々人にとっては、特別な精力や才能などによってより高い労働部面に飛躍するということは、やはり可能なのであって、それは、ちょうど、あれこれの労働者が自ら資本家になり他人の労働の搾取者になるという抽象的な可能性は相変わらず存在するのと同様である。@
奴隷は一定の主人のものになっている。労働者は、なるほど自分を資本に売らざるを得ないとはいえ、一定の資本家に売らなければならないのではないから、彼は一定の部面のなかでは自分を誰に売るかの選択権を持っており、自分の雇い主を替えることができる。すべてこれらの変化した関係は、自由な労働者の活動を、奴隷の活動に比べて、強度のより高いものに、より連続的に、より可動的に、より技能的にするのであって、これらの関係が彼自身に一つのまったく別な歴史的な行動への能力を与えるということは別にしても、そうなのである。@
奴隷は彼の生計に必要な生活手段を、種類からみても固定されている現物形態で──使用価値として──受けとる。自由な労働者はこの生活手段を、貨幣の、すなわち交換価値の、形態で、富の抽象的な社会的な形態で、受け取る。賃金はここでは事実上必要生活手段の銀化または金化または銅化または紙化された形態に他ならないのであって、絶えずこれらの生活手段になってしまわなければならず──貨幣は、ここでは交換価値のただ一時的な形態として、単なる流通手段として、機能するのだとはいえ、それでもやはり観念の中では、彼にとって自分の労働の目的であり結果であるものは、抽象的な富、交換価値であって、伝統的および局地的に制限された一定の使用価値ではないのである。労働者自身が、貨幣を任意の使用価値に換え、貨幣で任意の商品を買うのであって、彼は、貨幣所持者としては、商品の買い手としては、商品の売り手に対してすべて他の買い手とまったく同じ関係にあるのである。@
もちろん、彼の存在の諸条件は──彼が手に入れる貨幣の価値の大きさとまったく同様に──彼が貨幣をかなり限られた範囲の生活手段に換える、ということを余儀なくさせる。とはいえ、この点ではいくらかの変化が起きることも可能である。……」(同、P98~101)
(労働力の価値の転化形態としての「労賃」もいまだ抽象的なものであって、だからより具体的な時間賃金や出来高賃金の分析に進まねばならないことについては、必要なら次回触れます。)