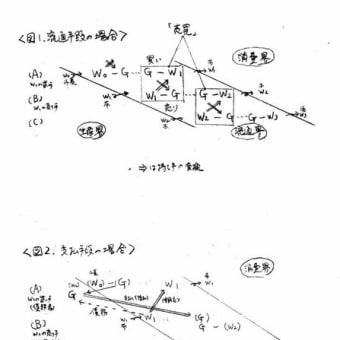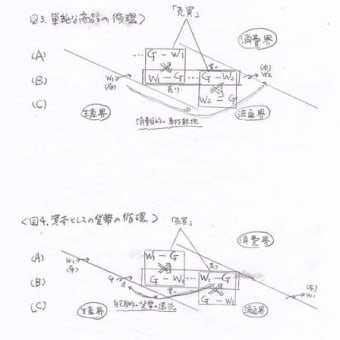「読む会」だより(23年2月用)文責IZ
(1月の議論など)
1月の読む会は22日に開催されました。まずチューターから、「たより」3頁の(前回から頁を付けました)下から17行目の「言い換えれば<新たに加わる社会的労働を>1時間半しか含んでいない」という部分の補足が間違っていたので<新たに加わる>という語句は削除してほしいという発言がありました。
12月の議論の部分には特に意見は出ませんでした。前回持ち越しとなった(2)の部分については、チューターが「資本主義の特徴は、人間が生産手段を使うのではなくて、生産手段が<その価値増殖のために>人間を使うといった、いわゆる人間の“疎外”として現れていると、マルクスはここでは語っている。こうした“疎外”をなくすためには、生産手段を共有することによって<消費手段は共有できるものではないが>、諸個人の労働を資本主義の下で実際にそうであるように社会的な労働として全面的に認め、解放していく必要がある」、と述べた点で意見が出て議論になりました。
一つは「中国などのように国有化されても疎外はなくなっていないのではないか」というもの、もう一つは「国鉄がJRに変わったが、労働者の生活が守られる点では国有化に意義があるのではないか」というものでした。チューターは、生産手段が国有化されていてもそれが労働者を搾取する資本として機能していれば私企業と変わりなかったことは国鉄でもそうだったではないか。労働者の生活がそれなりに守られたというのは、国有化されていたかどうかよりもそれまでの労働運動の遺産のようなものではないか、と答えましたが必ずしも意見は一致しませんでした。生産手段を共有化するということは、人々が社会的に意識的な生産と分配を行うために必要な手段・方法なのであって、それ自身が目的ではないことはすでに明らかのように思われます。
(説明)の部分では、(3)の引用の「12時間の社会的平均労働日の1日は、貨幣価値を不変と前提すれば、常に6シリングという同じ価値生産物を生産するのであって、この価値総額が労働力の価値の等価と剰余価値とにどのように分割されるかにはかかわりなくそうである。」という点について、若干の補足がなされました。商品価値は以前触れたように、投下資本であるC+Vに生産過程での労働者の剰余労働が加えられてC+V’すなわちC+(V+M)になります。しかし、労働力の使用によって商品に付け加えられる新価値の量(V+M)は、そこで支出された労働時間の大きさによって与えられるのであって、それはVとMの比率がどうであるか、言い換えれば労働力の搾取度の程度とはかかわりないし、またCすなわち労働力がそれに対象化される不変資本の価値の大きさにもかかわりはない、と言われているのです。
最後に、相対的剰余価値の生産に関連して「なぜ日本の労働者の賃金が上がらないのか、TVでは日本の企業がイノベーション<技術革新>を怠ってきたからと言っていたがそういうことか」という質問が出て議論になりました。チューターは、確かに空白の20年、30年と言われるようにこの間、企業が利益をもっぱら海外投資や企業内留保に回してきたということは事実だが、賃金に関して言えばむしろ政治的な事情ではないか(第5章の「労働日」で言われたように、労働力の売り手と買い手のあいだの同等な権利では“力”がことを決するのだから)と答えました。参加者からは「労働運動の解体的な状態もあるのではないか」という意見や、「非正規労働者の増大も大きな要因だ」という意見も出ました。なかなかそうした具体的な事象にまで切り込むことができなくて申し訳なく思っています。
(説明)第11章「協業」
前章の最後に、こうありました。
「労働の生産力の発展による労働<時間>の節約は、資本主義的生産ではけっして労働日の短縮を目的としてはいないのである。……労働の生産力の発展は、資本主義的生産のなかでは、労働日のうちの労働者が自分自身のために労働しなければならない部分を短縮して、まさにそうすることによって、労働者が資本家のためにただで労働することができる残りの<剰余労働の>部分を延長することを目的としているのである。このような結果は、商品を安くしないでも、どの程度まで達成できるものであるか、それは相対的剰余価値のいろいろな特殊な生産方法に現われるであろう。次にこの方法の考察に移ろう。」(同、P420~422)
ここで触れられているように、第11章「協業」、第12章「分業とマニュファクチュア」、そして第13章「機械と大工業」では、労働の生産力の発展による労働時間の短縮──それは資本主義の下では相対的剰余価値の生産に結果する──の方法として、協業と工場内(マニュファクチュア的)分業そして機械制大工業が取り上げられます。
分かりにくいのは、「このような<労働時間の短縮・節約という>結果は、“商品を安くしないでも”、どの程度まで達成できるものであるか」という部分と思われます。“商品を安くしないでも”という意味は、普通には──価値と価格が一致していることを想定すれば──商品の単位当たりの支出労働量を減らすことなく、といった意味になるのでしょうが、前章で触れられた2点を振り返ればここではそういう意味ではないことが、分かるでしょう。
一つは、「新しい方法を用いる資本家が自分の商品を1シリング<12ペンス>というその社会的価値で売れば、彼はそれをその個別価値<9ペンス>よりも3ペンス高く売ることになり、したがって3ペンスの特別剰余価値を実現するのである。しかし、他方、12時間の1労働日は、今では彼にとって以前のように12個ではなく24個の商品に表されている。だから、1労働日の生産物を売るためには、彼は2倍の売れ行きまたは2倍の大きさの市場を必要とする。……彼は自分の商品を、その個別価値よりも高く、しかしその社会的価値よりも安く、例えば1個10ペンスで売るであろう。それでもまだ彼は各1個から1ペンスずつの特別剰余価値を取り出す。……」という事情です。
もう一つは、「他方、新たな生産様式が一般化され、したがってまた、より安く生産される商品の個別的価値とその商品の社会的価値との差がなくなってしまえば、あの特別剰余価値もなくなる。労働時間による価値規定の法則、それは、新たな方法を用いる資本家には、自分の商品をその社会的価値よりも安く売らざるを得ないという形で感知されるようになるのであるが、この同じ法則が競争の強制法則として、彼の競争相手たちを新たな生産様式の採用に追いやるのである。……」という事情です。
ここで“商品を安くしないでも”と言われている意味は、諸資本の“競争”という後の第3巻で本格的に取り上げるべき諸事情を考慮に入れない範囲で、という意味に思われます。言い換えれば、労働時間を短縮する(相対的剰余価値の生産に結果する)ためのいくつかの方法を、その歴史的諸形態から切り離して、“純粋に”あるいは“単純なもの”に還元したうえで、まず考察しようと言っているのだと思われます──第5章で価値増殖過程と切り離して、まず労働過程を考察したように、あるいは第1章で「価値は、さしあたりまずこの形態<価値の現象形態としての交換価値>にはかかわりなしに考察されなければならない」と言われたように。
(1.賃金労働者による資本主義的協業は、使用価値の生産としては、“はじめから”社会の物質代謝の諸環の中に取り込まれている社会的な結合労働力として存在する。他方それは、価値の生産・増殖としては、資本の転化した一部分であって、その結合力は資本のもつ私的な力として労働者に対立する)
協業についてマルクスはこう述べます。
・「同じ生産過程で、または同じではないが関連のあるいくつかの生産過程で、多くの人々が計画的にいっしょに協力して労働するという労働の形態を協業という。
騎兵一中隊の攻撃力とか歩兵一連隊の防御力とかが、各個の騎兵や歩兵が個々別々に発揮する攻撃力や防御力の合計とは本質的に違っているように、個別労働者の力の機械的な合計は、分割されていない同じ作業で同時に多数の手がいっしょに働く場合、たとえば重い荷物をあげるときとかクランクを回すとか障害物を排除するとかいうことが必要な場合に発揮される社会的な潜勢力とは本質的に違っている。このような場合には、結合労働の効果は、個別労働では全然生み出せないか、またはずっと長い時間をかけて、またはひどく小さい規模で、やっと生み出せるかであろう。ここではただ協業による個別的生産力の増大だけが問題なのではなく、それ自体として集団力でなければならないような生産力の創造が問題なのである。
多くの力が一つの総力に融合することから生ずる新たな潜勢力は別としても、たいていの生産的労働では、たんなる社会的接触が競争心や活力の独特な刺激を生みだして、それらが各人の個別的作業能力を高めるので、12人が一緒になって144時間の同時的1労働日に供給する総生産物は、めいめいが12時間ずつ労働する12人の個別労働者または引き続き12日間労働する1人の労働者が供給する総生産物よりも、ずっと大きいのである。このことは、人間は生来、アリストテレスが言うように政治的な動物ではないにしても、とにかく社会的な動物だということからきているのである。」(P427)
・「個々別々のいくつもの労働日の総計と、それと同じ大きさの一つの結合労働日とを比べれば、後者はより大量の使用価値を生産し、したがって一定の有用効果の生産のために必要な労働時間を減少させる。与えられた場合に結合労働日がこの高められた生産力を受け取るのは、それが労働の機械的潜勢力を高めるからであろうと、労働の空間的作用範囲を拡大するからであろうと、生産規模に比べての空間的生産場面を狭めるからであろうと、決定的な瞬間に多くの労働をわずかな時間に流動させるからであろうと、個々人の競争心を刺激して活力を緊張させるからであろうと、多くの人々の同種の作業に連続性と多面性とを押印するからであろうと、いろいろな作業を同時に行なうからであろうと、生産手段を共同使用によって節約するからであろうと、個々人の労働に社会的平均労働の性格を与えるからであろうと、どんな事情のもとでも、結合労働日の独自な生産力は、労働の社会的生産力または社会的労働の生産力なのである。この生産力は協業そのものから生ずる。他人との計画的な協業のなかでは、労働者は彼の個体的な限界を脱け出て彼の種属能力を発揮するのである。」(P432)
このように協業(単純な協業ないし協業一般)は、「多くの人々」が、「計画的に(したがって一定の指揮の下で)」、「いっしょに協力して(互いに補い合って)」、労働するという三つの要素・契機で成り立つ労働形態です。協業は、もちろん資本の発明品ではなくて、人間が共同で狩りをしていた太古の昔から存在する労働形態です。
協業による結合労働日が、個々分散したままのその合計よりも高められた生産力を受け取る理由として、ここでマルクスは(1)労働の機械的潜勢力を高める、(2)労働の空間的作用範囲を拡大する、(3)生産規模に比べての空間的生産場面を狭める、(4)決定的な瞬間に多くの労働をわずかな時間に流動させる、(5)個々人の競争心を刺激して活力を緊張させる、(6)多くの人々の同種の作業に連続性と多面性とを押印する、(7)いろいろな作業を同時に行なう、(8)生産手段を共同使用によって節約する、(9)個々人の労働に社会的平均労働の性格を与える、といった例を挙げています。
そして、協業において発揮される集団力=結合労働力は、人間のもつ社会的な潜勢力の発揮であり、「個体的な限界を超えた種族能力の発揮」であって、だからこそその結合労働日は、個々独立的に行われる労働と区別される社会的労働がもつ独自の生産力として機能し、労働時間の短縮によって相対的剰余価値を生産する手段となることができる、と言うのです。
他方で資本の下での協業は、このような単純な協業(協業一般)とは異なった歴史的に独自な性格と形態をもちます。
・「資本主義的生産にあっては、労働条件は労働者にたいして<彼の労働を吸収するために投下された資本の諸形態として>独立して相対するのだから、労働条件の節約もまた、労働者にはなんの関係もない一つの特殊な操作として、したがって労働者自身の生産性を高める諸方法からは分離された操作として、現われるのである。」(P427)
・「およそ労働者は一緒にいなければ直接に協働することができないし、したがって彼らが一定の場所に集まっていることがかれらの協業の条件だとすれば、賃金労働者は、同じ資本、同じ資本家が彼らを同時に充用しなければ、つまりかれらの労働力を同時に買わなければ、協業することはできない。それゆえ、これらの労働力そのものが生産過程で結合される前に、これらの労働力の総価値、すなわち1日分とか1週間分とかの労働者たちの賃金総額が、資本家のポケットの中に一まとめにされていなければならない。……
そして、不変資本についても可変資本の場合と同じことである。……だから、個々の資本家の手の中にかなり大量の生産手段が集積されていることは、賃金労働者の協業の物質的条件なのであって、協業の程度または生産の規模はこの集積の程度によって定まるのである。
最初は、同時に搾取される労働者の数、したがって生産される剰余価値の量が、労働充用者自身を手の労働から解放し小親方を資本家にして<賃労働と資本という>資本関係を形態的につくりだすのに十分なものとなるためには、個別資本のある最小限度の大きさが必要なものとして現われた。いまでは、この最小限度の<資本価値の>大きさは、多数の分散している相互に独立な個別的労働過程が<社会的生産のための>一つの結合された社会的労働過程に転化するための物質的条件として現われるのである。……
すべての比較的大規模な直接に社会的または共同的な労働は、多かれ少なかれ一つの指図を必要とするのであって、これによって個別的諸活動の調和が媒介され、生産体の独立な諸器官の運動とは違った生産体全体の運動から生ずる一般的な諸機能が果たされるのである。単独のバイオリン演奏者は自分自身を指揮するが、一つのオーケストラは指揮者を必要とする。この指揮や監督や媒介の機能は、資本に従属する労働が協業的になれば、<それを統合する>資本の機能になる。資本の独自な機能として、指揮の機能は<社会的生産の調整という>独自な性格を持つことになるのである。
……賃金労働者の協業は、ただ単に、彼らを同時に充用する資本の作用である。彼らの諸機能の関連も生産的全体としての彼らの統一も、彼らの外にあるのであり、彼らを集めてひとまとめにしておく資本のうちにあるのである。それゆえ、彼らの労働の関連は、観念的には資本家の計画として、実際的には資本家の権威として、彼らの行為を自分の目的に従わせようとする他人の意志の力として、彼らに相対するのである。
それゆえ、●資本家の指揮は内容から見れば二重的であって、それは、指揮される生産過程そのものが一面では生産物の生産のための社会的な労働過程であり他面では<個別的な各>資本の価値増殖過程であるというその二重性によるのであるが、この指揮はまた形態から見れば専制的である。……資本家は、産業の指揮者だから資本家なのではなく、彼は、資本家だから産業の司令官になるのである。……
労働者は、自分の労働力の売り手として資本家と取引しているあいだは、自分の労働力の所有者なのであり、そして、彼が売ることができるものは、ただ彼が持っているもの、彼の個人的な個別的な労働力だけである。……それだから、資本家は100の独立した労働力の価値を支払うのであるが、しかし100という結合労働力の代価を支払うのではない。@
独立の人としては、労働者たちは個々別々の人であって、彼らは同じ資本と<賃労働者としての経済>関係を結ぶのであるが、お互いどうしでは<経済>関係を結ばないのである。彼らの協業は労働過程にはいってからはじめて始まるのであるが、しかし労働過程では彼ら<の労働力>はもはや自分自身のものではなくなっている。労働過程にはいると同時に彼らは資本に合体されている。協業者としては、一つの活動有機体の手足としては、かれら自身はただ資本の一つの特殊な存在様式<不変資本に剰余労働を付け加えることによって剰余価値を生む可変資本としての存在>でしかない。それだからこそ、労働者が社会的労働者として発揮する生産力は資本の生産力なのである。労働の社会的生産力は、労働者が<協業を行なうための>一定の諸条件のもとにおかれさえすれば無償で発揮されるのであり、そして資本は彼らをこのような諸条件のもとにおくのである。労働の社会的生産力は資本にとってはなんの費用もかからないのだから、また他方この生産力は労働者の労働そのものが資本のものになるまでは労働者によって発揮されないのだから、この生産力は、資本が生来もっている生産力として、資本の内在的な生産力として、現われるのである。」(P433~)
・「人類の文化の発端で、狩猟民族のあいだで、またおそらくインドの共同体の農業で、支配的に行なわれているのが見られるような、労働過程での協業は、一面では生産条件の共有にもとづいており、他面では個々の蜜蜂が巣から離れていないように個々の個人が種族や共同体の臍帯からまだ離れていないことに基づいている。この二つのことは、このような協業を資本主義的協業から区別する。大規模な協業の応用は古代世界や中世や近代植民地にもまばらに現われているが、これは直接な支配隷属関係に、たいていは奴隷制に、基づいている。@
これに反して、資本主義的<協業>形態は、はじめから、自分の労働力を資本に売る自由な賃金労働者を<したがって彼らの労働力の資本の下での結合や、発展した社会的分業と商品流通などを>前提している。とはいえ、歴史的には、それは、農民経営にたいして、また同職組合的形態を具えているかどうかにかかわりなく独立手工業経営にたいして、対立して発展する。これらのものに対して資本主義的協業が<それらと相並ぶ>協業の一つの特別な歴史的な形態として現われるのではなく、<賃金労働者の結合労働力を発揮させる>協業そのものが、資本主義的生産過程に特有な、そしてこの生産過程を<諸使用価値ではなく価値の生産・増殖を目的とし、相対的剰余価値の取得のために絶え間なくその技術的・社会的諸条件を変革していく>独自なものとして区別する歴史的な形態<工場制度といった>として現われるのである。
<つまり>協業によって発揮される労働の社会的生産力が資本の生産力として現われるように、協業そのものも、個々別々な独立な労働者や小親方の生産過程に対立して<生産手段を労働者の発揮する集団力=結合労働力を剰余労働として吸収させる手段とするという>資本主義的生産過程の独自な形態<工場制度といった>として現われる。それ<労働者が使用価値の生産のために生産手段を使うのではなく、生産手段がその価値増殖のために労働者を使うという独自な形態>は、<使用価値を生産するための>現実の労働過程が<価値の生産・増殖を目的とする>資本への従属によって受ける最初の変化である。@
この変化は自然発生的に起きる。その前提、同じ労働過程での比較的多数の賃金労働者の同時的使用は、資本主義的生産の出発点をなしている。この出発点は、<自己の価値を増殖させる>資本そのものの出現と一致する。@
●それゆえ、一方では、<使用価値ではなく価値の生産・増殖を目的とする>資本主義的生産様式は、労働過程が<社会的生産の一環を担う>一つの社会的過程に転化するための歴史的必然として現われるのであるが、他方では、労働過程のこの社会的形態<工場制度のように生産手段によって労働者が使われるという資本主義的協業様式>は、労働過程をその生産力の増大によっていっそう有利に搾取する<すなわち相対的剰余価値を取得する>ために資本が利用する一方法として現われるのである。
これまで考察してきたその単純な姿では協業は比較的大規模な生産と同時に現われるのであるが、しかし、それは資本主義的生産様式のある特別な発展期の固定的な特徴的な形態をなすものではない。……単純な協業は、分業や機械が重要な役割を演ずることなしに資本が大規模に作業するような生産部門では、つねにその部門の主要な形態なのである。」(P438)
このように賃金労働者による資本主義的協業は、あらかじめ社会の物質代謝の諸環の中に取り込まれている社会的な労働として存在するのですが、しかし他方では、それは他人の資本の一部分としての資本の指揮下での協業であり、労働者が生産手段の価値増殖のために使われるにすぎません。そこでは協業一般が具えている意識性・計画性という要素は、結合労働力を発揮する労働者自身には無縁であるばかりでなく、その結合力は資本に吸い取られ資本が価値増殖する力として彼ら自身に敵対するのです。
マルクスはこの章の最後をこう結んでいます。
・「協業の単純な姿そのものはその一層発展した諸形態と並んで特殊な形態として現われるとはいえ、協業はつねに資本主義的生産様式の基本形態なのである。」(P440)
前半で言われている、より単純なもの(あるいはより普遍的なもの)はより発展した具体的なものと並んで特殊な形態として現れるということは、認識論として重要な指摘でしょうが、ここではその点に深入りはしないことにします。
後半で言われている協業は常に資本主義的生産様式の基本形態である、ということは次章以降で検討される分業とマニュファクチュア、あるいは機械と大工業の理解にとっても重要なことと思われます。先に触れられたように、多数の賃金労働者による資本主義的協業は、一方では(使用価値の生産としては)、“はじめから”社会の物質代謝の諸環の中に取り込まれている社会的な労働として存在します。だからそれが発揮する結合力による生産力の増大は、社会的労働がいっそう社会の全面に拡大していくこと、言い換えれば、生産様式がすでに私的な生産から社会的な生産に変化していることを意味します。資本主義的生産は社会的な労働の力の発展と不可分であるがゆえに、協業は資本主義の基本形態となるのです。しかし同時に、他方では(価値の生産・増殖としては)、それが発揮する結合社会力による生産力の増大は、資本が私的により多くの剰余価値を取得する手段となり、労働者にとっては敵対的な力として現れます。言い換えれば、取得様式は相変わらず私的な生産を前提としているのです。ここに資本主義的な生産の根本的な矛盾が現れることになります。
最後に次章の参考になるであろう所を引用しておきます。
・「われわれは、互いに補い合う多くの人々が同じことかまたは同種のことをするということを強調したが、それは、共同労働のこのもっとも単純な形態が、協業のもっとも発達した形態にあっても一つの大きな役割を演ずるからである。労働過程が複雑ならば、一緒に労働する人々が多数だということだけでも、いろいろな作業を別々の手に分配し、したがってそれらの作業を同時に行ない、こうして総生産物の生産に必要な労働時間を短縮するということを可能にするのである。」(P430)
なお、第13章で触れることになりますが、労働の生産力の増大は基本的に機械の力ではなくて、それを利用する結合した人間力によるものだと指摘しておきたいと思います。
引用の<>内の補足部分は、チューターの理解不足で正しくない点があるかと思います。言葉のイメージを持つための一つの参考程度と考えてください。