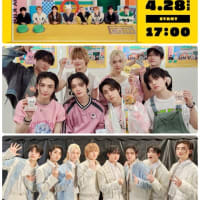前から書道教室の先生から行くようにと勧められていて、早く行かなくてはと思ううちに気がついたら5月6日で終了になってしまうので、ぎりぎりで行ってきました。
まずは上野の東京博物館の方から見ることにしていざ上野公園へ向かいましたが、すごい人込みでびっくり、やはりGW期間中だからなんでしょうね、平日にいくらでも行ける時があったのに、わざわざ混んでる時にしなくても、と思いながらも、まあ、常設館の方は空いてるのでいいんですけど…。
蘭亭序というのは、書道に関係のある人にはおなじみのもので説明するまでもありませんが、いざ説明せよと言われると難しいので、以下、東京国立博物館の説明を自分へのメモ代わりに引用しておきますね。
東晋時代・永和9年(353)暮春の初め、王羲之(おうぎし)は会稽山陰(かいけいさんいん)(浙江省(せっこうしょう))の蘭亭(らんてい)に名士を招いて詩会を催しました。せせらぎに浮かべた杯が流れ着く前に詩を賦し、詩ができなければ、罰として酒を飲む、文人ならではの雅宴です。その日、二篇の詩を成した者11人、一篇の詩を成した者15人、詩を成せず罰杯として酒を飲まされた者は16人でした。王羲之はその詩会で成った詩集の序文を揮 毫(きごう)しました。これが、王羲之の最高傑作と賞賛される蘭亭序です。
王羲之の書をこよなく愛した唐の太宗(たいそう)皇帝は臣下の蕭翼(しょうよく)に命じて、僧・弁才(べんさい)のもとから苦心惨憺(くしんさんたん)の末に蘭亭序を入手し、能書の臣下に臨書を命じました。欧陽詢(おうようじゅん)の臨書が迫真の出来ばえだったので、欧陽詢の臨本を石に刻し、その拓本を皇子、王孫、功臣に特賜しました。しかし、太宗は崩御に際して蘭亭序を殉葬させたため、蘭亭序の原本は伝存しません。
南宋時代、蘭亭序の収集は過熱し、士大夫(したいふ)は家ごとに蘭亭序を石に刻したと言われます。拓本を元に新たな拓本が作られ、実にさまざまな蘭亭序の諸本が現れるようになりました。王羲之傑作の残影が後世に与えた影響はまことに計り知れず、蘭亭信仰とでも言うべき状況の中で、歴代の文人は善本を求め、自らの理想とする蘭亭序像を思い描いてきたのです。
な~るほど、一緒に行った旦那に質問攻めにあったので、これを読むように、言わなきゃ、というか、私も改めて頭に入れておかなくては
上野の方では宋時代の各種拓本や、その影響を受けた清時代の作例を眺めて、書道博物館へと移動、駅でいうと鶯谷ですが、わざわざ上野駅まで行って鶯谷駅で降りるより、国立博物館の裏の方から歩いた方が早いし電車代も節約できるので歩いいきました。
こちらの方でも蘭亭序とその関連資料が展示されていましたが、中村不折の“楷書・蘭亭序”が面白かったです。
というわけで、書道への意欲も充分高まり…って、ただ高まるだけでなく、書かなきゃいけないですよね、頑張ろっと