は
基礎知識 > はじめに
はじめに
1935年(昭和10年)に岡田茂吉が自然農法を提唱した当時、日本の農村はその日に食べる米にさえ事欠くほど貧困にあえいでいました。岡田は農民が豊かになる根本は「大自然を尊重し、その摂理を規範に順応する事」であると考えました。
岡田は「生きている土の偉大な能力を発揮させれば、自然は豊かな恵みを与えてくれる」、こうした考えのもとに実験を繰り返し、今日の自然農法の基本的な理論を構築しました。
地球の歴史は46億年と言われています。その悠久の歴史の中で、自然は多くの生き物を産み、育てて、豊かな海と大地を築き上げてきました。そうした自然の営みを尊重し、その営みに学び、その営みを支えている働きを農業に活用することが、人間の生命の源として好ましい食糧を安定生産するためには欠かせません。
当時から70年、戦後復興、高度経済成長の時代を経て、私たちは豊かな生活を手に入れることができました。その一方で、私たちの生活は自然と大きな隔たりを持つようになりました。
今日、私たちは多くの環境問題を抱えており、食に対する不安も高まる一方です。農薬や化学合成添加物の人体への蓄積がその一因ではないかと疑われる病も現れ、アレルギー性の疾患をもつ人は日本人の約50%、アトピー性皮膚炎を患った小学生は11%に上ると推定されています。
私たちは今一度「自然とは何か」「食糧とは何か」を問いなおす時期に来ているのではないでしょうか。
21世紀どんな環境もんだいがあるの?
21世紀どんな環境もんだいがあるの?
「2002年 子ども環境白書」(環境省)より自然農法とは
農業試験場(松本市)・水稲展示圃場
昭和10年(1935)、創始者の岡田茂吉(1882-1955)は農薬や化学肥料に依存しない自然農法について、つぎのような理念と原理を示しました。
【自然農法の理念】 大自然を尊重し、その摂理を規範に順応する
【自然農法の原理】 生きている土の偉大な能力を発揮させる
つまり、生命を生かし、より豊かにしようとする自然の働きを引き出し、永続的な生産を行うことが自然農法の目標です。 その後、化学肥料や農薬全盛の時代にあっても、創始者の理念に共鳴する人々によって自然農法は実践され、 受け継がれてきました。そして今日、食品の安全性を求める声が高まるとともに、農薬と化学肥料が及ぼす環境破壊への危機感が広く社会で認識されるようになり、自然農法の果たす役割が高く評価されています。
自然農法センターでは、今後の農業のあり方として、これまでの自然農法を新しくとらえ直し、次の5つの条件を設定しています。
1.人間の健康を維持増進する食べ物を生産すること。
2.生産者と消費者の双方に経済的・精神的メリットがあること。
3.誰にでも実行でき、かつ永続性があること。
4.自然を尊重し環境保全に責任を持つこと。
5.人口の増加に伴う食糧生産に責任を持つこと。
IMG_2168基礎知識 > はじめに
はじめに
1935年(昭和10年)に岡田茂吉が自然農法を提唱した当時、日本の農村はその日に食べる米にさえ事欠くほど貧困にあえいでいました。岡田は農民が豊かになる根本は「大自然を尊重し、その摂理を規範に順応する事」であると考えました。
岡田は「生きている土の偉大な能力を発揮させれば、自然は豊かな恵みを与えてくれる」、こうした考えのもとに実験を繰り返し、今日の自然農法の基本的な理論を構築しました。
地球の歴史は46億年と言われています。その悠久の歴史の中で、自然は多くの生き物を産み、育てて、豊かな海と大地を築き上げてきました。そうした自然の営みを尊重し、その営みに学び、その営みを支えている働きを農業に活用することが、人間の生命の源として好ましい食糧を安定生産するためには欠かせません。
当時から70年、戦後復興、高度経済成長の時代を経て、私たちは豊かな生活を手に入れることができました。その一方で、私たちの生活は自然と大きな隔たりを持つようになりました。
今日、私たちは多くの環境問題を抱えており、食に対する不安も高まる一方です。農薬や化学合成添加物の人体への蓄積がその一因ではないかと疑われる病も現れ、アレルギー性の疾患をもつ人は日本人の約50%、アトピー性皮膚炎を患った小学生は11%に上ると推定されています。
私たちは今一度「自然とは何か」「食糧とは何か」を問いなおす時期に来ているのではないでしょうか。
21世紀どんな環境もんだいがあるの?
21世紀どんな環境もんだいがあるの?
「2002年 子ども環境白書」(環境省)より自然農法とは
農業試験場(松本市)・水稲展示圃場
昭和10年(1935)、創始者の岡田茂吉(1882-1955)は農薬や化学肥料に依存しない自然農法について、つぎのような理念と原理を示しました。
【自然農法の理念】 大自然を尊重し、その摂理を規範に順応する
【自然農法の原理】 生きている土の偉大な能力を発揮させる
つまり、生命を生かし、より豊かにしようとする自然の働きを引き出し、永続的な生産を行うことが自然農法の目標です。 その後、化学肥料や農薬全盛の時代にあっても、創始者の理念に共鳴する人々によって自然農法は実践され、 受け継がれてきました。そして今日、食品の安全性を求める声が高まるとともに、農薬と化学肥料が及ぼす環境破壊への危機感が広く社会で認識されるようになり、自然農法の果たす役割が高く評価されています。
自然農法センターでは、今後の農業のあり方として、これまでの自然農法を新しくとらえ直し、次の5つの条件を設定しています。
1.人間の健康を維持増進する食べ物を生産すること。
2.生産者と消費者の双方に経済的・精神的メリットがあること。
3.誰にでも実行でき、かつ永続性があること。
4.自然を尊重し環境保全に責任を持つこと。
5.人口の増加に伴う食糧生産に責任を持つこと。
基礎知識
自然農法の基礎知識
農業試験場・育種圃場
農業試験場・育種圃場
当センターが推進する自然農法は、「より多くの生命が、より豊かに調和する」自然の方向性とそれを支える生物による営みに人間が正しく関わり、その働きを引きだすことで、自然に息づく人間をはじめ多様な生物が、より豊かになることを目的としています。
自然農法栽培とは、こうした考え方に基づき、生態系を乱す化学肥料・農薬(合成・天然を問わず)の使用を控え、「耕地生態系を充実させて物質循環機能を高め、全ての生き物の役割を認め、より自然の機能を発揮させる」事を原則とした、永続的な栽培をいいます。そのための適切な有機物の利用、品種や栽培時期を含めた耕種管理の適性化などを技術の基本としています。
自然農法の生産方針
生物を介した物質循環は、また生命の連鎖でもあります。私たちの生命は他の植物や動物の生命によって支えられているのです。
私たちが健康で豊かな生活を送るためには、私たちの生命の糧となる植物や動物もまた、健康で、生命力に溢れていなくてはなりません。自然農法生産の大きな目標は、この生命力に溢れた、健康な作物を栽培・生産し、消費者に提供することです。
生命の糧ですから、安全であることはもちろん、安定した生産ができなくてはなりません。生産性が高い土壌は、構造が発達して膨軟で適度な透排水性と保水性があり、肥沃で肥持ちがよく、土壌生物が多様で多く存在しています。そういう土は、雑木林や湖沼で見受けることができます。これを手本に、優良な土壌腐植の増加と豊かな土壌生物群を育てる育土(いくど)※が最も重要であると考えています。育土のためにも、地域内にある未利用資源の有効活用や休閑期等を利用した有機物生産は欠かせません。
その上に立って、厳しい環境の中でも自立して子孫を残す事ができる力の強いタネの利用、植物の生理に合うような適期の栽培を心がけるなど、生産資材や石油資材に依存しないような工夫が必要です。
※自然農法では一般で言う「土づくり」を「生きている土を育てる」という意味で「育土」と呼びます。
安定生産に向けた栽培のポイント
安定生産に向けた栽培のポイント
自然農法の生産方針
生物を介した物質循環は、また生命の連鎖でもあります。私たちの生命は他の植物や動物の生命によって支えられているのです。
私たちが健康で豊かな生活を送るためには、私たちの生命の糧となる植物や動物もまた、健康で、生命力に溢れていなくてはなりません。自然農法生産の大きな目標は、この生命力に溢れた、健康な作物を栽培・生産し、消費者に提供することです。
生命の糧ですから、安全であることはもちろん、安定した生産ができなくてはなりません。生産性が高い土壌は、構造が発達して膨軟で適度な透排水性と保水性があり、肥沃で肥持ちがよく、土壌生物が多様で多く存在しています。そういう土は、雑木林や湖沼で見受けることができます。これを手本に、優良な土壌腐植の増加と豊かな土壌生物群を育てる育土(いくど)※が最も重要であると考えています。育土のためにも、地域内にある未利用資源の有効活用や休閑期等を利用した有機物生産は欠かせません。
その上に立って、厳しい環境の中でも自立して子孫を残す事ができる力の強いタネの利用、植物の生理に合うような適期の栽培を心がけるなど、生産資材や石油資材に依存しないような工夫が必要です。
※自然農法では一般で言う「土づくり」を「生きている土を育てる」という意味で「育土」と呼びます。
安定生産に向けた栽培のポイント
安定生産に向けた栽培のポイント













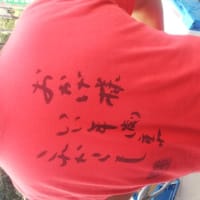







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます