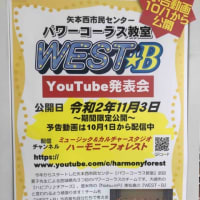今回は時間の関係で最後まで聞く事が出来ませんでしたが、
どの研究内容も興味深く、大変参考になりました。
会場は東京芸術大学。
前日参加されていた耳鼻科医師の方も会場に多数お見かけし、ざっと参加者は100名はいたと思います。
まず学会理事長の米山文明先生と竹田数章先生に熊谷組技術研究所が共同研究者となり
「音カメラを使用して、発声時の体外放出音の伝播方式の映像化に関する研究」
声を映像化するのは初めて見ましたが、日本人・イタリア人・ドイツ人で同じように発声しても全く違うし、
膝と下半身に体重をかけて上半身をしなやかにした際の発声映像も大きく違います。
また、声楽家と狂言師(今回のモデルは野村萬斎さん)でも違うし、
反響板を使う・使わないでも映像が違ってきます。
研究の途中経過での発表ということだったので、
今後どんな形で私たちの仕事に役立てていくのか楽しみです。
そして、飯田忠文先生が「歌声の基本」と題して
呼吸や発声練習前に有効な体操(ヨガや太極拳)を医学的な視点からも研究され、発表。
また、母音、二重母音、スタッカート、トリルなどを鍛える発声法を私たちも実践しながら受講しました。
午後からは東京混声合唱団常任指揮者の松原千振先生の
「言語と声、ハーモニー」と題してよく合唱で取り上げられる言語の特徴を検証。
またハーモニーを使い音程感覚を考え、旋法の特質も取り上げていました。
グレゴリオからルネサンス、モ―ッァルト、バルトーク、北欧東欧、日本の童謡を音源を聞きながら講演。
その中から、数曲の楽譜が配られ、初見で歌ってみようという時間がありましたが、
さすが!パートどおりにまとまって座っていないし、音取りもしていないのに関わらず
音叉の音だけを頼りに、みなさんすぐに歌えていました。
先生は音程感覚やハーモニーを意識して歌わせるためには音叉を使用する事を勧めていました。
また、バッハのコラールを使用する事も個人だけでなく
合唱団全体のレベルアップを図るのに有効だそうです。
早速、自分の持っているコーラスレッスンやゴスペルクワイヤーにも取り入れていきたいと思っています。
どの研究内容も興味深く、大変参考になりました。
会場は東京芸術大学。
前日参加されていた耳鼻科医師の方も会場に多数お見かけし、ざっと参加者は100名はいたと思います。
まず学会理事長の米山文明先生と竹田数章先生に熊谷組技術研究所が共同研究者となり
「音カメラを使用して、発声時の体外放出音の伝播方式の映像化に関する研究」
声を映像化するのは初めて見ましたが、日本人・イタリア人・ドイツ人で同じように発声しても全く違うし、
膝と下半身に体重をかけて上半身をしなやかにした際の発声映像も大きく違います。
また、声楽家と狂言師(今回のモデルは野村萬斎さん)でも違うし、
反響板を使う・使わないでも映像が違ってきます。
研究の途中経過での発表ということだったので、
今後どんな形で私たちの仕事に役立てていくのか楽しみです。
そして、飯田忠文先生が「歌声の基本」と題して
呼吸や発声練習前に有効な体操(ヨガや太極拳)を医学的な視点からも研究され、発表。
また、母音、二重母音、スタッカート、トリルなどを鍛える発声法を私たちも実践しながら受講しました。
午後からは東京混声合唱団常任指揮者の松原千振先生の
「言語と声、ハーモニー」と題してよく合唱で取り上げられる言語の特徴を検証。
またハーモニーを使い音程感覚を考え、旋法の特質も取り上げていました。
グレゴリオからルネサンス、モ―ッァルト、バルトーク、北欧東欧、日本の童謡を音源を聞きながら講演。
その中から、数曲の楽譜が配られ、初見で歌ってみようという時間がありましたが、
さすが!パートどおりにまとまって座っていないし、音取りもしていないのに関わらず
音叉の音だけを頼りに、みなさんすぐに歌えていました。
先生は音程感覚やハーモニーを意識して歌わせるためには音叉を使用する事を勧めていました。
また、バッハのコラールを使用する事も個人だけでなく
合唱団全体のレベルアップを図るのに有効だそうです。
早速、自分の持っているコーラスレッスンやゴスペルクワイヤーにも取り入れていきたいと思っています。