『太陽にほえろ!』(たいようにほえろ)は、東宝テレビ部が制作した刑事ドラマシリーズ。
『太陽にほえろ!』(PART1)は1972年(昭和47年)7月21日から1986年(昭和61年)11月14日まで、全718回。日本テレビ系列で金曜日20時から1時間枠で放送された。
続いて続編にあたる『太陽にほえろ!PART2』が1986年(昭和61年)11月28日から[1]1987年(昭和62年)2月20日まで、全12回放送。この項ではPART2についてもあわせて述べる。
“ボス”こと藤堂係長(石原裕次郎)を中心に、ニックネームで呼び合う警視庁七曲警察署(東京都・新宿区)刑事課捜査第一係(強行犯係)の刑事たちの活躍を描いたテレビドラマ。現在では日本の刑事ドラマの代表格とも称される作品である。
それまでの刑事ドラマは事件と犯人が中心で描かれており、レギュラーの刑事達(主に本庁の捜査一課所属)は狂言回しに過ぎなかった。しかし本作は、所轄署の捜査一係に勤務する刑事の一人一人にフルネームと性格設定を与え、「青春アクションドラマ」と銘打って刑事を主役にした物語を展開した。「走る」刑事ドラマとしても有名で、勝野洋、宮内淳が走った延距離は地球半周分とも言われる[誰によって?]。
サツ、デカ、ホシ、タレコミといった警察用語を世に広めたが、取り調べの際の出前など実際の警察とは異なる描写も多い。
当初の構想では、主人公・マカロニ刑事こと早見淳の成長物語として展開していく予定であった。しかし、早見役の萩原健一が降板を熱望し「劇中で死にたい」という萩原本人の申し出を製作側が受け入れ、早見は通り魔強盗に刺し殺されるという形で姿を消す。だが主役級の降板という事態にもかかわらず番組を終了させることはなく、無名の松田優作を萩原の後任に起用してさらなる成功を収めた。これに端を発し、新人や無名俳優を主演の新米刑事として出演させてその人間的に成長する姿を描き、やがて彼らが「殉職」[2]することで番組を卒業していくというパターンが定着。勝野洋、渡辺徹などといったスターが生み出された。やがて、番組の路線が安定してくると沖雅也、三田村邦彦、世良公則など芸能界で実績のある俳優が起用されるケースも出てきた。また露口茂、竜雷太、小野寺昭、下川辰平らベテランおよび中堅のメンバーにも主演作が用意されるようになり、新米刑事の青春物語から群像劇としての魅力を加えていった。
本作はレギュラー出演者のスケジュール調整には大変注意が払われていた。実際に警察官は「非番」という形で交代制で休みを取る[3]のでこれに準じて、番組1年目は萩原(40話、42話、44話)・小野寺(5話、10話、11話、14話、36話、37話、45話)・下川(10話、18話、31話〜33話、36話、48話、49話)の欠場があった。2年目以降はごく一部の例外(81年の石原裕次郎・沖雅也の病欠)を除き、一係メンバーは毎回必ず顔を揃えていた(岡田晋吉プロデューサーによれば「関根恵子はセミレギュラー扱いだった」)。裕次郎は86年にも再入院し代役として渡哲也が配されたが、最終回で復帰。番組のテーマともいえる「生命の尊さ」を訴え、シリーズ通しての主役として物語をしめくくった。
『太陽にほえろ!』(PART1)は1972年(昭和47年)7月21日から1986年(昭和61年)11月14日まで、全718回。日本テレビ系列で金曜日20時から1時間枠で放送された。
続いて続編にあたる『太陽にほえろ!PART2』が1986年(昭和61年)11月28日から[1]1987年(昭和62年)2月20日まで、全12回放送。この項ではPART2についてもあわせて述べる。
“ボス”こと藤堂係長(石原裕次郎)を中心に、ニックネームで呼び合う警視庁七曲警察署(東京都・新宿区)刑事課捜査第一係(強行犯係)の刑事たちの活躍を描いたテレビドラマ。現在では日本の刑事ドラマの代表格とも称される作品である。
それまでの刑事ドラマは事件と犯人が中心で描かれており、レギュラーの刑事達(主に本庁の捜査一課所属)は狂言回しに過ぎなかった。しかし本作は、所轄署の捜査一係に勤務する刑事の一人一人にフルネームと性格設定を与え、「青春アクションドラマ」と銘打って刑事を主役にした物語を展開した。「走る」刑事ドラマとしても有名で、勝野洋、宮内淳が走った延距離は地球半周分とも言われる[誰によって?]。
サツ、デカ、ホシ、タレコミといった警察用語を世に広めたが、取り調べの際の出前など実際の警察とは異なる描写も多い。
当初の構想では、主人公・マカロニ刑事こと早見淳の成長物語として展開していく予定であった。しかし、早見役の萩原健一が降板を熱望し「劇中で死にたい」という萩原本人の申し出を製作側が受け入れ、早見は通り魔強盗に刺し殺されるという形で姿を消す。だが主役級の降板という事態にもかかわらず番組を終了させることはなく、無名の松田優作を萩原の後任に起用してさらなる成功を収めた。これに端を発し、新人や無名俳優を主演の新米刑事として出演させてその人間的に成長する姿を描き、やがて彼らが「殉職」[2]することで番組を卒業していくというパターンが定着。勝野洋、渡辺徹などといったスターが生み出された。やがて、番組の路線が安定してくると沖雅也、三田村邦彦、世良公則など芸能界で実績のある俳優が起用されるケースも出てきた。また露口茂、竜雷太、小野寺昭、下川辰平らベテランおよび中堅のメンバーにも主演作が用意されるようになり、新米刑事の青春物語から群像劇としての魅力を加えていった。
本作はレギュラー出演者のスケジュール調整には大変注意が払われていた。実際に警察官は「非番」という形で交代制で休みを取る[3]のでこれに準じて、番組1年目は萩原(40話、42話、44話)・小野寺(5話、10話、11話、14話、36話、37話、45話)・下川(10話、18話、31話〜33話、36話、48話、49話)の欠場があった。2年目以降はごく一部の例外(81年の石原裕次郎・沖雅也の病欠)を除き、一係メンバーは毎回必ず顔を揃えていた(岡田晋吉プロデューサーによれば「関根恵子はセミレギュラー扱いだった」)。裕次郎は86年にも再入院し代役として渡哲也が配されたが、最終回で復帰。番組のテーマともいえる「生命の尊さ」を訴え、シリーズ通しての主役として物語をしめくくった。











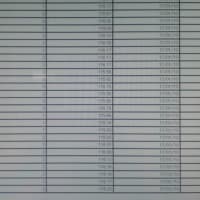


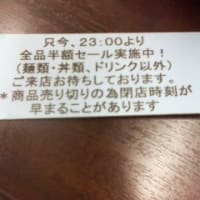
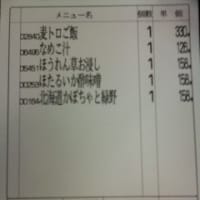





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます