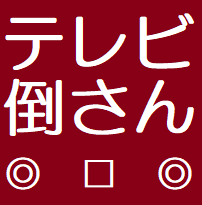神奈川県の65歳以上を対象にした「コロナ患者のワクチン接種状況(令和4年7月1日~12月20日)」で、「感染者数と死亡例の割合(接種回数別)」を見ると、表やグラフでは「全体データ(65歳以上)の死亡情報あり合計は850人」で「80歳以上の死亡情報あり合計は644人」です。
年齢区間 :死亡数(人)
65歳以上 : 850 (全体データ)
80歳以上 : 644
(差: 206)
年齢区間 :死亡数(人)
65歳以上 : 850 (全体データ)
80歳以上 : 644
(差: 206)
このデータから、「65歳~79歳」は206人になるので、
年齢区間 : 死亡数:全国総死亡数
65~79歳: 206: 12752
80歳以上 : 644: 38718
年齢区間倍率:3.13: 3.04
です。
「全国総死亡数」は、2023年1月31日迄のコロナ感染症による全国総死亡数で、「65~79歳」の死亡数は、「70歳代の死亡数」に「60歳代の死亡数の1/2」を加えた数値です。実際には「60~64歳」よりも「65~69歳」の死亡数が多いので、「全国総死亡数の年齢区間倍率」は「神奈川県の年齢区間倍率」に、更に近似すると思われます。
ここで、神奈川県と全国データの「年齢区間倍率」はほゞ同じなので、接種の有無に関するデータも全国の傾向と同じと仮定します。
また、神奈川県のデータでは「感染者数」となっていますが、正しくは「確認陽性者数(以降、陽性者数)」とし、65歳以上(80歳以上も含まれる)を調べると、
:接種0回:接種1回以上:接種比率%
陽性者数:7929:139545: 94.6
死亡数 : 113: 737: 86.7
死亡率%:1.42: 0.53: --
注)「接種0回」は、「接種情報」で「接種0回」と明記された人数で、「陽性者数」は、元の表の、
「全国総死亡数」は、2023年1月31日迄のコロナ感染症による全国総死亡数で、「65~79歳」の死亡数は、「70歳代の死亡数」に「60歳代の死亡数の1/2」を加えた数値です。実際には「60~64歳」よりも「65~69歳」の死亡数が多いので、「全国総死亡数の年齢区間倍率」は「神奈川県の年齢区間倍率」に、更に近似すると思われます。
ここで、神奈川県と全国データの「年齢区間倍率」はほゞ同じなので、接種の有無に関するデータも全国の傾向と同じと仮定します。
また、神奈川県のデータでは「感染者数」となっていますが、正しくは「確認陽性者数(以降、陽性者数)」とし、65歳以上(80歳以上も含まれる)を調べると、
:接種0回:接種1回以上:接種比率%
陽性者数:7929:139545: 94.6
死亡数 : 113: 737: 86.7
死亡率%:1.42: 0.53: --
注)「接種0回」は、「接種情報」で「接種0回」と明記された人数で、「陽性者数」は、元の表の、
[陽性者数]=[死亡情報なし]+[死亡情報あり]
で算出した人数。
また、全国コロナ感染死亡数の90%以上は70歳以上とされているので、ここでは、65歳以上の感染死亡数をもって全数として扱い、「接種関係情報の記載無し」は、0回接種以外で接種回数が分からないと判断し、「接種済み」に加算している。
日本人全体の81%が少なくとも一回接種した事は分っています。神奈川県の年齢層別接種率が分からないのですが、全国の全体の接種率で65歳以上の年齢別接種率を凡そ90~96%とすると、神奈川県の「65歳以上の陽性確認者の接種比率(94.6%)」とほゞ同じになる事から、「ワクチン接種には感染予防効果が無かった」と言えます。
長くなったので、続きは次回へ・・・・