古事記の「ヲロチ退治」に登場する「八俣遠呂智」は、一つの胴体に頭は八個と尻尾が八本に分かれています。「八俣遠呂智」は荒れ狂う河川を暗喩しているとも言われていて、退治の時に使われるお酒は、お神酒を供える事で安寧を願う神事の意味も有ると思います。一方、「ヲロチ退治」の物語は日本平定の手法を示しているとも考えられます。
「八」は多数を意味し、多くの首領(頭)と従属者(尻尾)が連合(胴体)を組む、強大な連合組織が「八俣遠呂智」の正体だと考えます。
地方の豪族が政略結婚等を繰り返し、連合を組み勢力を増強し領地を拡大していく方法は、万国共通の「国づくり」の定石です。ところが、この手法では「船頭多くして船山に上る。」の如く、見方にによれば「船が山に登る」ほどの凄い事が出来るようにも見えますが、本来の目的は達成できません。八人の頭(カシラ)がいれば一人ぐらい優れた人がいても、連合を組んでいる為に有らぬ方向に引き摺られてしまいます。「八俣遠呂智」の一つの頭が「罠だから飲むのを止めろ!」と言ったとしても、他の頭が酒を呑むと体全体にアルコールが廻り、「八俣遠呂智」全体が泥酔してしまいます。
「欧州連合(EU)」は巨大な組織(胴体)で、頭(主導国)も尻尾(従属国)も多く、現在は敵国から貰った酒で悪酔いしています。一国だけまともな頭(カシラ)がいても、「共胴体」で繋がっている為に共倒れになりそうですが、自分の頭に酔いが回る前に「自らの頭」を切り離す事に気が付いた国がイギリスです。権威を持つ国王がいる国はやはり違います。
古事記では、国家統一には力だけではなく「権威」が重要である事を示す為に、「ヲロチ退治」の時に「須佐之男命」は「天照大御神」の弟である事を「知らしめる」事で、出雲を統治する事に成功します。
明治憲法 第一條
大日本帝國ハ萬世一系ノ天皇之ヲ統治ス
大日本帝國ハ萬世一系ノ天皇之ヲ統治ス
「統治」とは「統(しろしめす)」「治(おさめる)」の事で、「しろしめす」は「知る」の意味であり、「権威を以て、天皇は国民をよく知り、国を治める」事が義務付けられています。決して、「天皇主権」や「天皇独裁」を意味するものではありません。
「統合された権威」の無い王国連合、連邦、連合国などは、「須佐之男命」によって解体され、「天照大御神」の権威によって一体化します。これが「古事記のヲロチ退治」の意味するところだと思います。
権威の無い「象徴」は、国民の統合にはならず、解体される恐れがあります。
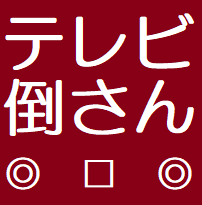










「宋書」にある「倭の五王」は、日本の天皇では無く、朝鮮半島の五王ではないでしょうか?
タタラ製鉄(ヤマタノオロチ)が紀元前の話なら、日本が古くから半島南部を支配していた事を証明できるかも知れません。