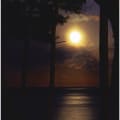『古事記』顯宗天皇 けんぞう天皇 1
伊弉本別王御子、市邊忍齒王御子・袁祁之石巢別命、坐近飛鳥宮治天下、捌歲也。天皇、娶石木王之女・難波王、无子也。此天皇、求其父王市邊王之御骨時、在淡海國賤老媼、參出白「王子御骨所埋者、專吾能知。亦以其御齒可知。」御齒者、如三技押齒坐也。爾起民掘土、求其御骨、卽獲其御骨而、於其蚊屋野之東山、作御陵葬、以韓帒之子等、令守其陵。
然後持上其御骨也。故還上坐而、召其老媼、譽其不失見置・知其地、以賜名號置目老媼、仍召入宮內、敦廣慈賜。故其老媼所住屋者、近作宮邊、毎日必召。故鐸懸大殿戸、欲召其老媼之時、必引鳴其鐸。爾作御歌、其歌曰、
阿佐遲波良 袁陀爾袁須疑弖 毛毛豆多布 奴弖由良久母 淤岐米久良斯母
於是、置目老媼白「僕甚耆老、欲退本國。」故隨白退時、天皇見送、歌曰、
意岐米母夜 阿布美能於岐米 阿須用理波 美夜麻賀久理弖 美延受加母阿良牟
≪英訳≫
Emperor Kenzou, born to Prince Izahowake, the son of Prince Ichinobe-no-Oshiha, ruled the world from Asuka Palace in Kawachi Province for eight years. The Emperor married Princess Naniwa, the daughter of Prince Iwaki, but they had no children. When the Emperor sought the bones of his father, Prince Ichinobe, an old woman from Omi Province claimed, “I know well the place where the prince’s bones are buried. I can also identify it by his teeth, which have three branches.” The prince’s teeth were indeed large with three branches. The people were summoned, and they dug the earth to find his bones. They placed them in a mausoleum on the eastern hill of Kayano, appointing the children of Karafukuro to guard it.
Later, the Emperor dug up the bones. He summoned the old woman and praised her for not forgetting the location, giving her the name “Okime-no-Baba”. He then brought her into the palace, showing great kindness. A house was built near the palace where the old woman lived, and she was summoned there every day. To call her, a bell was hung at the main hall’s door, which would ring when they wished to summon the old woman. The Emperor composed a song:
Through the low fields of pampas grass,
Past the small valley where the sound of the bell rings,
Okime will soon arrive.
Okime then said, “I have grown very old and wish to return to my homeland.” When the time came for her departure, the Emperor saw her off, composing a song:
Okime, O Okime from Omi,
Starting tomorrow, you will hide in the mountains,
And I fear I shall never see you again.
≪この英文の和訳≫
伊弉本別(イザホワケノ)の王の御子で、市邊忍齒(イチノベノオシハ)の王の御子であり、袁祁之石巢別(オケノイワスワケ)の命(みこと)顕宗(けんぞう)天皇として、河内(かわち)の飛鳥宮(あすかのみや)で八年にわたり天下を治められました。この天皇は、石木(イワキ)の王の娘である難波(ナニワ)の王と結婚されましたが、御子はありませんでした。その後、顕宗天皇は父王であるイチノベノノ王の御骨を探されました。この時、近江(おうみ)の国に住む老婆が「王の御骨が埋められた場所は、私がよく知っており、そのお齒でも判別できます」と申しました。王のお齒は三本の枝のある大きな齒でした。そこで人々を召集し、土を掘り、御骨を探し出しました。それを見つけて、カヤ野の東の山に御陵を建て、*カラフクロの子たちにその御陵を守らせました。
後に、顕宗天皇はその御骨を掘り上げられました。そして、老婆を呼び寄せ、場所を忘れずに覚えていたことをお賞めになり、「置目の老媼(おきめのばば)」という名前をお授けになりました。その後、老婆を宮中に招き、敦(あつ)くお気遣いをなさいました。宮の近くに老婆が住む家を建て、毎日お呼び寄せになりました。老婆を呼び寄せるときは、宮殿の戸に鈴を掛け、その鈴を鳴らすようにしました。顕宗天皇のお詠みになった歌
茅の低い原を抜けて、小谷を過ぎると、鈴の音が聞こえてくる。
置目(おきめ)がやってくるのだ
置目は申しました「私は年を取りましたので、故郷に帰りたいと思います」。その帰郷の際、天皇は見送り、歌をお詠みになりました。
置目(おきめ)よ、あの近江の置目よ、
明日からは山に隠れてしまって、
二度と見えなくなるだろうね
令和5年9月20日(水) 2023
*「カラフクロ」とは、古事記に登場する人物で、大長谷王(後の雄略天皇)に猪鹿の狩り場を教えた人です。カラフクロは韓帒(カラフクロ)とも呼ばれ、韓(カラ)から来たという説があります。カラフクロは大長谷王に仕えていましたが、大長谷王が履中天皇の子である忍歯王(おしばのみこ)を殺したとき、その墓を作るよう命じられました。その後、カラフクロの子孫は代々忍歯王の墓守となりました。カラフクロの子孫は沙沙貴神社(ささきじんじゃ)の神職として伝えられています。
(Bing AI)