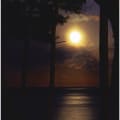『日本書紀』応神天皇 2
元年春正月丁亥朔、皇太子卽位。是年也、太歲庚寅。
二年春三月庚戌朔壬子、立仲姬爲皇后、后生荒田皇女・大鷦鷯天皇・根鳥皇子。先是、天皇以皇后姉高城入姬爲妃、生額田大中彥皇子・大山守皇子・去來眞稚皇子・大原皇女・澇來田皇女。又妃皇后弟々姬、生阿倍皇女・淡路御原皇女・紀之菟野皇女。次妃和珥臣祖日觸使主之女宮主宅媛、生菟道稚郎子皇子・矢田皇女・雌鳥皇女。次妃宅媛之弟小甂小甂、此云烏儺謎媛、生菟道稚郎姬皇女。次妃河派仲彥女弟媛、生稚野毛二派皇子。派、此云摩多。次妃櫻井田部連男鉏之妹糸媛、生隼總別皇子。次妃日向泉長媛、生大葉枝皇子・小葉枝皇子。凡是天皇、男女幷廿王也。根鳥皇子、是大田君之始祖也。大山守皇子、是土形君・榛原君、凡二族之始祖也。去來眞稚皇子、是深河別之始祖也。
≪英訳≫
In the first year of spring, on the first day of the first month, the Crown Prince ascended to the throne. This year was known as Tai-sai Kanoetora.
In the second year, on the third day of the third month of spring, Nakatsuhime was proclaimed the Empress. The Empress gave birth to Oratano Himemiko, Oosazaki no Sumera Mikoto (Emperor Nintoku), and Netorinomiko. Later, the Emperor took Takaki no Irihime, the Empress’s sister, as his consort, who bore him Nukata no Oonakatsuhiko Mikoto, Ooyamamori no Mikoto, Izanomawaka no Mikoto, Oharano Himemiko, and Komutano Himemiko. Another consort, Otohime, the sister of the Empress, gave birth to Abe no Himemiko, Awaji no Miharahime Mikoto, and Kino Unono Himemiko. The next consort, Miyakushiyakahime, a descendant of Wani no Omi and the daughter of Hifure no Omi, bore Uji no Wakairatsuko Mikoto, Yada no Himemiko, and Metori no Himemiko. The next consort, Onabehime, sister of Yakahime, gave birth to Uji no Wakairatsume no Himemiko. Another consort, Otohime, daughter of Kawamatana Nakatsuhiko, bore Wakanoke Futamatano Mikoto. The next consort, Sakurai Tabenomurajimusanai’s sister, Iwohime, gave birth to Hayabusawake no Mikoto. The next consort, Himuka no Izumi no Nagahime, gave birth to Obae no Mikoto and Obae no Mikoto. In total, the Emperor had twenty children, both sons and daughters.
Netorinomiko (Prince Netori) is the ancestor of Ootanokimi (Lord Oota). Ooyamamorinomiko (Prince Ooyamamori) is the ancestor of both the Hijikatanokimi (Lord Hijikata) and the Hariharanokimi (Lord Harihara) clans. Izanomawakanomiko (Prince Izanomawaka) is the ancestor of the Fukakawawake clan.
≪この英文の和訳≫
元年の春、一月一日に、皇太子が皇位につかれました。この年は、太歳庚寅(たいさいかのえとら)と知られています。
二年目の春、三月三日に、仲姫(なかつひめ)が皇后として立てられました。皇后は、荒田皇女(おらたのひめみこ)、大鷦鷯天皇(おおさざきのすめらみこと、仁徳天皇)、根鳥皇子(ねとりのみこ)をお生みになりました。その後、天皇は皇后の姉である高城入姫(たかきのいりひめ)を妃とし、彼女から額田大中彦皇子(ぬかたのおおなかつひこのみこと)、大山守皇子(おおやまもりのみこ)、去来真稚皇子(いざのまわかのみこ)、大原皇女(おおはらのひめみこ)、澇来田皇女(こむたのひめみこ)をお生みになりました。また、別の妃で皇后の妹である弟姫(おとひめ)からは、阿倍皇女(あべのひめみこ)、淡路御原皇女(あわじのみはらひめみこ)、紀之蒐野皇女(きのうののひめみこ)をお生みになりました。次の妃である和珥臣(わにのおみ)の祖先である日触使主(ひふれのおみ)の娘、宮主宅媛(みやぬしやかひめ)からは、蒐道稚郎子皇子(うじのわきいらつこのみこ)、矢田皇女(やだのひめみこ)、雌鳥皇女(めとりのひめみこ)をお生みになりました。さらに、次の妃である宅姫(やかひめ)の妹、小甌媛(おなべひめ)からは、蒐道稚郎姫皇女(うじのわきいらつめのひめみこ)をお生みになりました。また、その次の妃である河派仲彦(かわまたなかつひこ)の娘、弟姫(おとひめ)からは、稚野毛二派皇子(わかのけふたまたのみこ)をお生みになりました。その次の妃である桜井田部連男組(さくらいたべのむらじむさい)の妹、糸媛(いをひめ)からは、隼総別皇子(はやぶさわけのみこ)をお生みになりました。次の妃である日向泉長媛(ひむかいのいずみのながひめ)からは、大葉枝皇子(おおばえのみこ)、小葉枝皇子(おばえのみこ)をお生みになりました。この天皇には、合わせて二十人の子供がありました。
根鳥皇子(ねとりのみこ)は、大田君(おおたのきみ)の先祖です。大山守皇子(おおやまもりのみこ)は、土形君(ひじかたのきみ)と榛原君(はりはらのきみ)の二つの一族の先祖です。去来真稚皇子(いざのまわかのみこ)は、深河別(ふかかわわけ)の先祖です。
令和6年3月30日(土) 2024