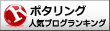2021/3/10(水) 晴
今日の最高気温21°出発は11時、気温16°、目的地を網津川眼鏡橋群としてポタリングに出る。
国道501→平木橋→農免道路へは、いつものルート。国道57へ出て右折し、尾根筋を見て左折した。が、間違って城塚千体仏に着いた。
城塚を後にして、馬門大歳神社に移動する。
国道57から県道58へ左折南進し、「あじさいの湯」を過ぎた辺りから左手方向を眺めながら進むと、ひときわ大きな大歳神社の楠木(写真5参照)が見える。

南方向へ延びた大枝(写真6参照)

北方向へ延びた大枝は瘤になり、主幹の部分が空洞(写真7参照)なっているのか。
楠木は、古代には丸木船の材料に使われた。ここは「大王の石棺」を積みだした所。主幹部分は船材に使われ、そのひこばえが巨樹になったのか?

説明板(写真8参照)には、宇土市指定天然記念物で、宇土市最大の巨樹とある。

大歳神社(写真9参照)は、西向きに建っている。拝殿の拝む方向の向うに楠木があり、御神木が祭神のようにも見える。

鳥居は、馬門石(阿蘇溶結凝灰岩のピンク石)(写真10参照)で造られている。

馬門石石切場跡
2016/11/11(金) 晴
関西まで運ばれた「阿蘇ピンク岩」製の大王の石棺が切り出された宇土市馬門石切場まで行って来た。
馬門地区は、写真中央の高い山と手前の丘陵の谷間にある。

今から11年前の2005年熊本県宇土半島から大阪まで「大王のひつぎ実験航海」が行われた。
1500年前の石棺輸送についての2005年当時の解釈は、「献上品であり古代王権のデモンストレーション」だったというようなことであったと思う。
「献上品」に対して、それは違うだろうと私は思っている。
私が思う仮説は、継体大王が九州連合の国家間を分断し、九州王朝磐井の君の筑紫国包囲網作戦の一環として、火の君との政治取引ではなかったかと考えている。
火の君の本貫地と言われている氷川町の野津古墳群、大野窟古墳は6世紀初期から中頃にかけて築造され、栄えていたと推定する。
被支配、収奪される側であれば地域は衰退すると考える。
馬門石石棺が発見されている古墳は、今城塚古墳以外は大王墓に匹敵する大古墳はないということからも献上品とは言い難い。
馬門石石切場の谷の上流に牧神社(写真2参照)があり、律令国家草創期の707年宇土大宅郷に「牧山」が開かれた(写真3参照)とある。
継体大王の時代はこれより100年ほど前。官営の牧が開かれる以前に馬を飼育する人々がいたと想像する。
継体大王は、河内馬飼首荒籠に決断を促されて王位に就くことを決断したという。
馬飼いつながりで、継体大王は各地の王族に馬門石を推奨し火の君を優遇・懐柔したのではないかと推測する。
また宇土地域には、半島系の須恵器土器が多量に出土するという。
ここにもこの地方と継体大王のつながりが考えられる。
さらに、熊大横瀬久芳氏によれば(http://yrg.sci.kumamoto-u.ac.jp/lecture/presen/s6.pdf)、肥後熊本と福井、新潟の骨格形質は近いとある。熊本県合志郡は、越国と同祖かと考える。
継体大王の母は福井の出身で継体大王も福井で育ったという説もあり、肥後と馴染み深い関係にあったかもしれないと想像する。
継体大王の出身地近江に肥後型の横穴石室古墳があるという。
石棺と一緒に職人集団も移動したことも考えられる。
牧神社を後にして帰途に就く。今日も無事だったことを天に感謝する。
熊本(自宅)34km→馬門石切場27km→熊本(自宅)所要時間5.5時間(実4時間) 総計61km 走行累計18,825km
馬門石石切場跡
2014/8/18(月) 曇/ときどき雨
天候は曇。今日の最高気温は30度、10時と15時に傘マークの予報。
この時季のこの気温は自転車走行日和と、自宅を9時半南方向へ出発。
「小田良古墳」か「馬門(マカド)石切場跡」へ行こうと自宅を出発したが、天はそう甘くない。自宅から高野辺までの間に4回の雨宿り。
緑川の平木橋を渡るころには11時半になっていた。
15時までに帰宅するには、小田良古墳は無理ということで、馬門石石切場跡を目的地とする。
「馬門石石切場跡」を5/2、7/4に探索に失敗していて、言わば三度目の挑戦である。
ある方のブログに「左折し、先を右折し・・・」という記載があり、これを参考に進行すると「馬門石石切場跡」(右写真1参照)にあっけない程簡単に現場到着する。
手前右手丘の上には、赤石神社がある。
観光用の演出なのか、切出し途中で中止したのか、正面にいつで切出せそうな大きな四角い石がある。手前に廃石材が転がっている。

石切り場を後にして100m程奥に道を辿ると、牧神社(写真2参照)がある。

説明板(写真3参照)によると、奈良時代から明治時代初期まで牧場があったという。

「馬門」と言う地名について知りたいと思いインターネットを検索したところ、栃木県佐野市、栃木県茂木町、青森県十和田市、青森県野辺地町等にあり、「一般に湖の出口をマカドという・・・マカド(馬門)はマカ(曲)・ド(処)という・・・」(佐野市HPより)とある。
さらに馬門石の「大王の棺」が なぜ宇土から運ばれたか?の疑 問には、県道58から橋を渡って直ぐの右手にある大歳神社(右写真5参照)がキーワードであると言う「久留米地名研究会 武雄市 古川清久」氏のページにたどり着いた。私の考えた「馬門」など戯言にもならないので割愛する。

近年の天気予報はかなり正確なので、15時からの降雨の前に帰宅すべく「大歳神社」境内で弁当を食して早々に帰途に就く。
15時半自宅着。摂取水分量1l(500ml×2本)到着間際から雨になった。
無事だったことを天に感謝。
熊本(自宅)27km→馬門石石切場跡29km→熊本(自宅)
所要時間6時間(実4.5時間) 総計56km 走行累計7,294km