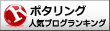2023/5/8(月) 晴
今日は最高気温予報23°比較的涼しい気温で晴天に、目的地を宇城市の鴨籠橋(かもこばし)、松合(眼鏡)橋の石橋探訪として、午前10時からポタリングに出る。
新幹線側道、国道3を南進し、宇土市から田圃の中の北園古墳を右手に見て国道266に出て西進する。
国道266に出る少し手前の塚原の溜池は、昨日までの雨で池の水は濁っている。その中に、奇麗なスイレンの花(写真1参照)が咲いている。

不知火中学校から右折して、宇城市指定文化財の鴨籠橋(写真2参照)を見る。
宇城市ホームページには、「・・・明治期に地元住民が主体となって架橋しましたが、高欄(こうらん)がなく橋幅も狭かったため、昭和26年(1951年)に再度住民が海東村の石工に依頼し拡幅されました。
明治期架橋(下流側)の石材には、宇土市網津町で採掘される阿蘇溶結凝灰岩、通称馬門石(まかどいし)が用いられ、昭和期架橋(上流側)の石材には安山岩が用いられています。・・・平成28年地震によって被災し、令和3年に復旧されました。復旧工事の際の調査により、馬門石の石材は水門等の他用途に使用されていたものを転用したことなどが分かりました。」とある。

下流側の輪石は馬門石(写真3参照)で造られている。

上流側は安山岩(写真4参照)で造られている。

橋詰に、小さく可憐なニワゼキショウの花(写真5参照)が咲いている。

再度国道266に出て、西へ走り松合に着く。みそ醸造所の前の広場に、眼鏡橋(石橋)の説明板(写真6参照)がある。

平石3枚の擬似橋(写真7参照)のことかと思ったが、その向こう側の柵の中の石材のことらしい。熊本地震後に訪れた時にはビニールシートが掛けてあった。それ以前に訪れた時は、不確かな記憶だが輪石のみの橋が復元されていたように思う。

目的の宇城市指定の松合(眼鏡)橋(写真8参照)に移動する。
宇城市ホームページには、「松合橋は不知火町松合に所在しており、文政3年(1820年)に架橋された石橋です。
火事が多かった松合地区においては、家屋同士の間隔を広くし、延焼を防ぐ目的として、江戸時代末期に埋め立てによる土地の拡張が行われました。松合橋は、その埋立地である屋敷新地と川で隔てられた元の松合集落を結ぶ橋で、現在も集落の主要道として利用されています。
この石橋の特徴は、基礎石(凝灰岩)、輪石(馬門石:宇土市網津町で産出されるピンク色の阿蘇溶結凝灰岩)、壁石(安山岩)で石材を使い分けている点で、これほど明白に使い分けられた例は、県下でも数少ないものです。
また、海岸に面した立地から、橋面幅に対して基礎幅を広げる、いわゆる裾広がりの安定形にすることで、潮の干満による水圧の増加に備えるといった工夫が施されています。」とある。

工事中のテントの隙間から覗くと、馬門石の輪石(写真9参照)が見える。全体を見たいところだが、工事中では仕方がない。仕事に邪魔にならないように早急に退散する。

直ぐ近くに「松合目鏡橋架設二〇〇年にちなんで」(写真10参照)という文章が掲示されている。「・・・松合目鏡橋がめでたく二〇〇歳になったので、今までいろいろお世話になったことを思い出して、感謝しながら渡りましょう。日本の石橋を守る会々長・・・」とある。

近くの和田公園に「土蔵・白壁の町松合の街並み案内図」(写真11参照)が掲示してある。ここを折り返し点として帰途に就く。

スマホgoogleマップに宇土市デジタルミュージアムが表示された。帰路の途中なので、その中の浜戸川の「太郎兵衛の渡し跡」に寄ってみる。地図の表示点と自分の位置情報が重なる所(写真12参照)に行ってみる。偶然かどうか分からないが、堤防道路上にマーキングがある。それ以外の案内標識類は何もない。

帰路は、平木橋、八城橋、高橋稲荷大橋を渡るルートを選択する。高橋稲荷大橋上から鯉のぼり(写真13参照)を見る。帰路を急ぐ。

16時半に帰宅する。今日も無事だったことを天に感謝する。
熊本(自宅)32km→宇城市松合36km→熊本(自宅)
総所要時間6.5時間(実5.5時間) 総計68km 走行累計54,147km