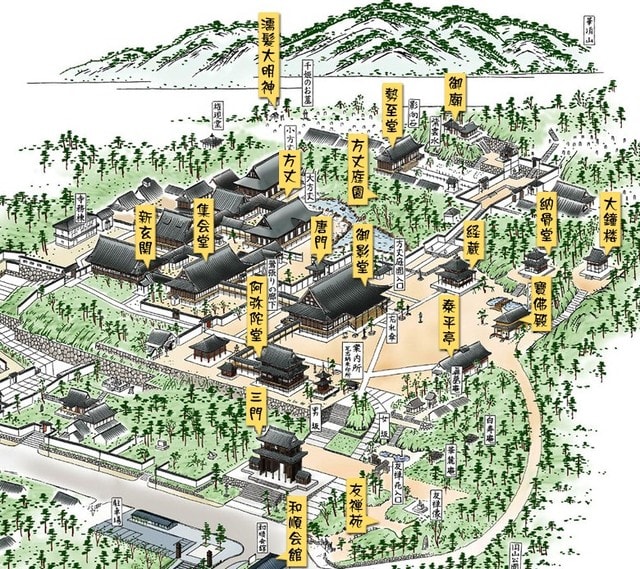今回は京都市の北区、大徳寺の北にある今宮神社のやすらい祭りが行われます。
元々は稲作の豊穣をねがって花鎮めとして始まり、次第に民衆の疫病退散を願うお祭りになったものです。
京都では「春の花が散る頃、散る花のように疫神が病を振りまき人を悩ます」と言われてきました。 そのため鎮花祭(はなしずめのまつり)とも呼ばれ平安時代から続いています。




「やすらい花や ヨーホイ」の掛け声とともに、赤熊(しゃぐま)を振り乱して鬼たちが舞います。
そして、笛、鉦、太鼓にあわせて行装の一団が囃し、花に宿る精霊が悪霊を誘いだし花傘に閉じ込めながら各町内を練り歩きます。
この傘に入ると一年を無病息災に暮らせるそうで、近所のお馴染みさんと手をつないで傘に駆けよる光景が見られます。
古来より水無月の夏越の祓えと大晦日の大祓の年に二回、半年の罪穢れを人形に依せて流す行事が行なわれてきました。
また、当社では毎年四月に厄疫を鎮めるやすらい祭が行なわれ、この時、鎮疫に現れる鬼の装束を模した人形をやすらい人形と言い、社頭にて随時授与しております。

阿呆賢(あほかし)さんという石
阿呆賢(あほかし)さんという石が据えられています。
高札によりますと病弱な人がこの石に病気平癒の願いを込めてなでると良いそうです。
又「重軽石」とも言われ、まず軽く手のひらで3度石を打ち持ち上げます。
願いを掛けて又3度手のひらで撫でてから持ち上げ、軽ければ願いが叶うと言う事です。

納め方
中の空欄にお名前などを記入し本殿へ納め疫厄を祓います。
納められた人形は吉日を選びお祓いの後、お焚き上げ致します。
中央に付いているお札は厄除けのお札として玄関の外側にお貼り下さい。
やすらい人形(ひとがた)



四地区
1)紫竹上野町・光念寺出発-今宮神社(14時半頃)-光念寺
2)紫野雲林院町・玄武神社出発(13時頃)-氏子区域-玄武神社(18時頃)
3)西賀茂・川上大神宮神社出発-氏子区域-今宮神社(15時頃)
4)上賀茂・岡本やすらい堂出発-上賀茂神社-やすらい堂(1ヶ月後に実施)
■期 間:2019年4/14(日)
■場 所: 今宮神社、玄武神社、川上大神宮
■時 間: 11~16時
■アクセス: 今宮神社:市バス206「船岡山」
玄武神社:市バス206「大徳寺前」
川上大神宮社:市バス9「西賀茂車庫前」 ■お問合せ 今宮神社(075-491-0082)
玄武神社(075-451-4680)
川上大神宮(075-493-2750)
詳しくは:http://www.imamiyajinja.org/jpn/imamiya_JPN/yasurai_ji.html

あぶり餅
あぶり餅(あぶりもち)は、竹串にさした親指大のきな粉をまぶしたお餅を炭火であぶり白味噌のたれを塗ったお菓子です。
今宮神社お店は歴史が古く平安時代頃からある日本最古のお菓子とされています。
神社参道で応仁の乱で京都が焼きはらわれてしまい飢餓に苦しむ庶民に振舞ったといういわれがあります。
また、あぶり餅で使われる竹串は今宮神社に奉納された斎串(いぐし)で、食べることで病気・厄除けのご利益があるとされています。

あぶり餅が食べれるお店
「かざり屋」
住所:京都府京都市北区紫野今宮町96
営業時間:10:00~17:30
定休日:水曜休(1日・15日・祝日の場合は翌日休)
電話番号::075-491-9402
料金:一人前15本 500円

「一和」(いちわ)
住所:水曜休(1日・15日・祝日の場合は翌日休)
営業時間:10:00~17:00
定休日:水曜休(1日・15日・祝日の場合は翌日休)
電話番号:075-492-6852
料金:一人前15本 500円

京都の古都なら http://www.e-kyoto.net/