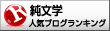<2002年5月に書いた文を一部修正して復刻します。>

1) ドイツの文豪・ゲーテという人をどう理解したらいいのだろうか。 我々人間が感じること、考えること、想像することの全てをこの人は把握しているようだ。 それだけではなく、我々が感じ、考え、想像することの全てを越えるものを、この人は体験しているようだ。 その精神の広さと深さにおいて、この人の右に出る者はいないのではないか。
例えば、最も崇高なものも、最も醜悪なものもこの人は理解でき、そして体得して実行することができるだろう。 つまり、人間が持っているものを全て保有しているということだ。 ナポレオンがゲーテに会った時、「あなたは人間だ」と言ったことは十分に分かるような気がする。
この汲めども尽きない人から、我々は何事でも学び、教えられることができるだろう。そういう意味で、この人は正に“人生の師”と言える。 全ての人がそれぞれの仕方で、ゲーテから学ぶことができるのだ。 例えば私の場合は、ゲーテからはっきりと学んだものは「汎神論」である。
2)「汎神論」のことはさておき、私なりにゲーテについて語っていきたい。 若き日のゲーテは、新しい文学運動であるシュトゥルム・ウント・ドラング(疾風怒濤)の旗手であった。 ご存知のように小説「若きウェルテルの悩み」や、戯曲「ゲッツ・フォン・ベルリヒンゲン」の著者として一世を風靡した。非常に輝かしい青春を駆け抜けたのである。
しかし、ゲーテ自身の告白から知られるのは、その青春は同時に極めて苦悶に満ちたものであったようだ。 肉と霊の葛藤に苦しみ抜いた形跡がある。彼ほど生命力に満ち溢れた人も珍しいから、その葛藤は凄まじいものがあったらしい。「ウェルテル」にもその一端が窺える。
人はその偉大さによって、ゲーテを神聖視するきらいがある。それはよく分かるが、彼の青春時代は正に懊悩苦悩の連続だったようだ。 それは現代風に言えば、リビドー(libido)の横溢による絶え間のない苦悶ということである。 リビドーと言う限り、もちろん性的エネルギーの奔出も含まれる。
年上の娘から料亭の少女、その後 牧師の娘から銀行家の令嬢へと、青春時代の彼の恋愛はとどまる所を知らなかった。その間にも、他の青年の婚約者であるシャルロッテ・ブッフ(「ウェルテル」の中のロッテのモデル)に恋をして果たせず、心に痛手を負うということもあった。 挙げ句の果てには、銀行家の令嬢との婚約を破棄して彼はワイマールへと去って行く。正に恋愛の疾風怒濤という感じがする。
3) そうした中で、ゲーテがどれほど「罪」の意識を感じたかは計り知れない。ある意味で、煩悩の塊だったと言ってよい。 若き日の彼は自分自身にこう言った。「 この哀れな者よ、一体いつまで狂い回らなければならないのか!」 その深い苦悶の合間から、束の間の「生」の喜びが輝かしい青春の詩歌となって、ほとばしり出てきた感じがするのだ。 煩悩の塊であればこそ、真実の喜びを体験できるのかもしれない。
晩年になって、家族との食事の時にゲーテがふと漏らした言葉は、この天才の恐ろしさを如実に物語るものである。 彼は言った。「もし私が、自分の好きなようにしていたら、私の意思一つで自分自身も、周りの人達をも全て破滅させていただろう」
この言葉を待つまでもなく、彼は生死のぎりぎりの所を頻繁にさまよって来たのだ。 これは耐え難い苦痛だったに違いない。地獄の業火に苛まれる罪人を想い起こさせる。それほどまでに、この人は苦悩したのだ。 こうしたことは、余人にはなかなか分からないだろう。彼自身が自分の煩悩を乗り越えるためにどれほど苦労したかは、彼の次の言葉の中にも表れている。「自分の風変わりな、どうしようもない性格を治してくれたのは、スピノザの哲学(汎神論)だった」
ゲーテの心(精神)こそ、ありとあらゆる矛盾、あつれき、衝突を包含していたのだろう。 フランスの作家ロマン・ロランが言った。「彼の心は、あらゆるものの戦場だった。それは耐え難い戦場だった」と。 そして、ゲーテ自身もこう言った。「私の後を決して追うな」
4) 多くの人が知っているように、ゲーテはワイマールに行ってから、ようやく落ち着きを取り戻すことができた。現実生活との調和を得ることができたのだ。 7歳年長のシュタイン夫人とのプラトニックな恋愛が、背景にあったのは言うまでもない。しかし、ゲーテと知り合った最初の頃は、シュタイン夫人も彼の野性を相当警戒していた形跡がある。
その後のゲーテの人生については、余りに多くの伝記に描かれているので省略する。 37歳の時のイタリアへの脱出旅行から晩年に至るまで、彼の創造力(デモーニッシュな創造力)と、自然研究の精神はまったく衰えを見せるどころか、むしろ円熟と深みを加えていった。 驚嘆すべき創造力は劇作、詩、小説等で発揮され、自然科学の研究は植物、動物の形態学、「色彩論」などに結実していった。 ゲーテのことを『ルネサンス最後の巨人』と評した人がいるが、正に“万能の天才”と言うべき存在であった。
これほど輝かしい人も他にいないが、晩年に至るまで彼は“悩める人”であった。そこがまた、我々普通の人間を魅了してやまない所である。 39歳の時、若い造花女工(クリスティアーネ・ヴルピウス)と同棲し男子を儲けるが、彼女と正式に結婚するのは18年も後になってのことである。 その間も、また妻に先立たれた後も、晩年に至るまでゲーテの恋愛遍歴は止まることがなかった。
5) 19世紀ロシアの有名な批評家ヴィッサリオン・ベリンスキーは、「ゲーテはまるで豚(ブタ)みたいな奴だ」と言ったことがある。漁色家ということである。 これは正に当を得たものであろう。彼は74歳になっても、19歳の少女に恋をして結婚を申し込んだほどだから。
しかし、ゲーテの恋がドン・ファンのような単なる漁色家のものと違うのは、それが余りにも美しく昇華されることである。 19歳の少女に失恋した老ゲーテは、悲嘆と苦悶のどん底から魂を揺さぶるような詩をうたう。有名な「マリーエンバートの悲歌」の一節を紹介しよう。
『どうしようもない憧憬に 此方彼方へ私はさまよい 慰さめる手だても知らず ただ果てもなく涙は流れる よし涙よ 湧きやむな 流れ続けよ この心の火を消すことは それでもできまい 生と死が むごたらしくも組み打ちする 私の胸の中は今すでに 狂おしく裂けんばかりだ』(人文書院発行「ゲーテ全集 第一巻 詩集」より。高安国世訳)
哀切の尽きないこの悲歌を読む時、我々はとても74歳の老人が詠んだものとは思えない。 恋に破れた老ゲーテの心情が切々と迫ってくる。 年老いて尚このような情熱を秘めているとは、驚異としか言いようがない。情熱の虜(とりこ)にならなければ、このような悲歌は生まれてこないだろう。
こうした点に、私どもはなんとも言えない魅力をゲーテに感じるのではないか。 絶えず生の拡充を求めて、生と闘った人間。 そして、人生の最後の瞬間まで生を愛した人間。 死の間際に「もっと光を!(mehr Licht!)」の言葉を残した人間・・・ゲーテは『生の詩人』として、人類の中に永遠に生き続けるだろう。 (2002年5月9日)