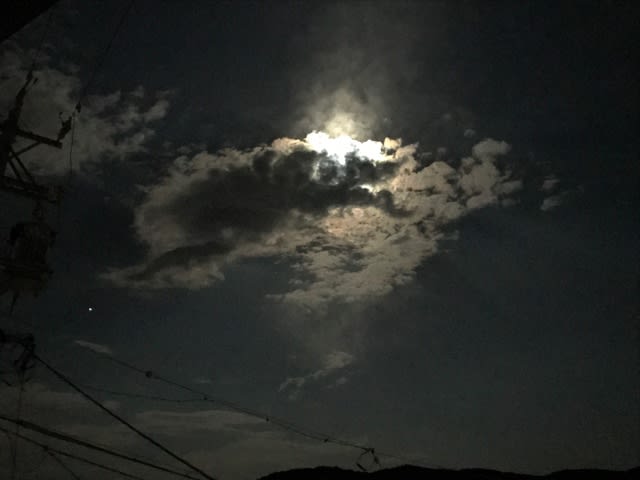最初にお詫びします。PGC3589は写ってません。m(_ _)m



1)中西昭雄著「メシエ天体&NGC天体ビジュアルガイド」誠文堂新光社
2)浅田英夫著「エリア別ガイド 星雲星団ウォッチング」地人社館
3)早水 勉著「The Book of The Starry Sky 星空の教科書」技術評論社
4)渡邉耕平著「電視観望 実践ガイドブック Ver 1.1」株式会社サイトロンジャパン
5)JUNZO著「アンドロメダ銀河かんたん映像化マニュアル」日本実業出版社
銀河星雲マニア~JUNZO氏が立ち上げた著書と連動したWebsite
6)渡邉耕平著 根本泰人監修「月・惑星撮影 実践ハンドブックVer1」サイトロンジャパン
7)【新時代のスマート望遠鏡】Seestar S50レビュー | 天リフOriginal
11)シンメトリーへの憧憬 – 不規則銀河 NGC 55~たのしい天体写真
電視観望の記録等関連Blog
01)電視観望の機材07(機材一覧表)
02)電視観望の機材009(スマート天体望遠鏡 ZWO Seestar S50)
03)星見娘で電視観望17(ちょうこくしつ座銀河 C65/NGC253)
04)星見娘で電視観望24(ちょうこくしつ座 C70/NGC300)
撮影情報