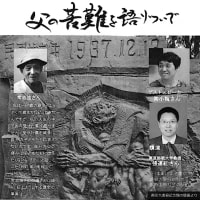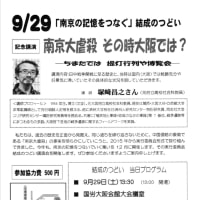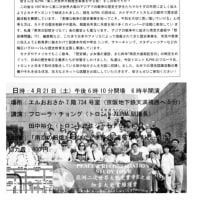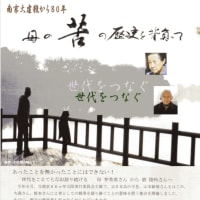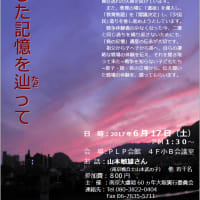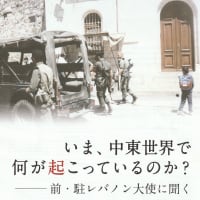さらにそれを詳しく述べているのがラーベの日記だ。
1938(昭和13)年1月14日前後の日記を見てみよう。
1938(昭和13)年1月14日の日記
「私は安全区を設置するために当地で発足した国際委員会の代表を引き受けました。現在ここは二十万人もの中国人非戦闘員の最後の避難場所になっています。これを組織するのは必ずしも容易な仕事ではありませんでした。しかも日本から全面的には承認を得られず、中国軍上層部が、ぎりぎりまで、つまり南京から逃げ出すまで部下と共にここに駐留していたために、いっそう困難になりました。
今まで、給食所や食糧の配給所などを設置して、安全区にひしめいている二十万人の市民をどうにか養ってこられました。ところが今度、「難民の保護は新しく設立された自治委員会が引き継ぐ。よって米販売所を閉鎖すべし」との命令が日本軍から出されたのです。市内に秩序が回復し、南京を出る許可が下りましたらそちらに参ります。今までのところ、申請はすべて却下されています。
安全区委員会の解散まで私が当地にとどまることをお許し下さいますよう、遅ればせながらお願い申し上げます。というのも、わずかとはいえ、我々外国人の存在が大ぜいの人々の禍福を左右するからです。十二月十二日以来、私の家と庭だけでも六百人以上の極貧の難民たちがおります。たいていは庭の藁小屋に住んでおり、毎日支給される米を食べて生きています。 ナチ式敬礼をもって ジョン・ラーベ」(注2)
ここには、「私は安全区を設置するために当地で発足した国際委員会の代表を引き受けました。現在ここは二十万人もの中国人非戦闘員の最後の避難場所になっています。」、「今まで、給食所や食糧の配給所などを設置して、安全区にひしめいている二十万人の市民をどうにか養ってこられました。」とあり、安全区にいる市民・非戦闘員、つまり難民が20万人いることが述べられている。
1937(昭和13)年1月15日の日記
「南京の状況 一九三八年一月十三日
当地南京では、電話、電報、郵便、バス、タクシー、力車、すべて機能が停止している。水道は止まっており、電気は大使館のなかだけ。しかも一階しか使えない。イギリス大使館にはまだ電気が通じていない。
なぜ交通が麻痺しているかといえば、城壁の外側は中国人に、市内はその大部分が日本軍によって、焼き払われてしまったからだ。そこはいまだれも住んでいない。およそ二十万人の難民はかつての住宅地である安全区に収容されている。家や庭の藁小屋に寄り集まって、人々はかつがつその日をおくっている。多い所には六百人もの難民が収容されており、かれらはここから出ていくことができない。
なぜ交通が麻痺しているかといえば、城壁の外側は中国人に、市内はその大部分が日本軍によって、焼き払われてしまったからだ。そこはいまだれも住んでいない。およそ二十万人の難民はかつての住宅地である安全区に収容されている。家や庭の藁小屋に寄り集まって、人々はかつがつその日をおくっている。多い所には六百人もの難民が収容されており、かれらはここから出ていくことができない。
安全区の外の道路には人気がなく、廃墟となった家々が荒涼とした姿をさらしている。
食料品の不足は限界にきている。安全区の人たちは、すでに馬肉や犬の肉に手をだしている。ヒュルターがきのう、やっとのことでもう一度市内を出て棲霞山までいき、セメント工場のギュンターさんから、豚を一頭に鶏を何羽か買いこんできてくれた(砲艦に乗せてもらったお礼に、いくらかイギリス大使館に寄付した)。そうでもしないことには手に入らない。
ラーベ氏の率いる委員会はアメリカ人と力を合わせてめざましい成果を上げた。一万人の命を救ったといっても、過言ではない。
水の問題も深刻だ。断水しており、洗濯もできない。沼という沼には死体が投げこまれており、汚染されている(写真21)。(中略)
南京に進駐したときの日本軍のしわざについては黙ってるのが一番だ。チンギス=ハーンを思い出してしまう。要するに「根絶やしにしろ!」ということだ。ある参謀部の中佐から聞いたのだが、上海から南京へむかった補給部隊は本隊に追いつかなかったそうだ。それで、日本兵はベルゼルカー(北欧神話に出てくる熊の皮をまとった大力で狂暴な戦士)のように手当たり次第に襲ったのか。「戦い抜けば、南京で美しい娘が手に入る」とでもいわれたにちがいない。
だから女性たちが、いま目もあてられないほどひどい目にあっているのだ。それを目のあたりにした人たちとその件について話すのは難しい。話そうとすると、くりかえしそのときの嫌悪感がよみがえるからだ。
部隊が統制を失ったからだ、ということはやさしい。だが私はそうは思わない。アジアの人間の戦争のやり方は、我々西洋人と根本的に違っているからだ。もし、日本と中国の立場が逆だったとしても、おそらく大した違いはなかっただろう。とくに扇動する人間がいる場合には。占領された地域では市内でも田舎でも、作物が畑で腐っている。市内の畑に近よることは禁じられており、田舎では住民が逃げたか、殺されたかしたからだ。野菜、じゃがいも、かぶ。そのほかどれもこれもみなだめになって、飢えが蔓延している。」(注3)
これは、ドイツ大使館南京分室事務長シャルフェンベルクの記録であるが、ここにも「およそ二十万人の難民はかつての住宅地である安全区に収容されている。」とあり、20万人が難民の数であることが分かる。
1937(昭和13)年1月17日の日記
「昨日の午後、ローゼンといっしょにかなり長い間市内をまわった。すっかり気が滅入ってしまった。日本軍はなんというひどい破壊のしかたをしたのだろう。あまりのことに言葉もない。近いうちにこの街が息を吹き返す見込みはあるまい。かつての目抜き通り、イルミネーションなら上海の南京路にひけをとらないと、南京っ子の自慢の種だった太平路は、あとかたもなく壊され、焼き払われてしまった(写真14)。無傷の家など一軒もない。行けども行けども廃墟が広がるだけ。大きな市が立ち、茶店が建ち並んでいた繁華街夫子廟もめちゃめちゃで見るかげもない。瓦礫、また瓦礫だ!いったいだれが元通りにするというんだ!帰り道、国立劇場と市場の焼け跡によってみた。ここもなにもかもすっかり焼け落ちていた。南京の三分の一が焼き払われたと書いたが、あれはひどい思い違いだったのではないだろうか。まだ十分調べていない東部も同じような状態だとすると、三分の一どころか半分が廃墟と化したと言ってよいだろう。
日本軍は安全区から出てくるようにとくりかえしいっているが、私は逆にどんどん人が増えているような気がする。上海路の混雑ときたら、まさに殺人的だ。いまは道の両側にそこそこしっかりした作りの屋台ができているのでなおさらだ。そこではありとあらゆる食料品や衣料品が並べられ、なかには盗まれた故宮宝物もまじっている。難民の数は今や約二十五万人と見積もられている。増えた五万人は廃墟になったところに住んでいた人たちだ。かれらは、どこに行ったらいいのかわからないのだ。」(注4)
ここには、「日本軍は安全区から出てくるようにとくりかえしいっているが、私は逆にどんどん人が増えているような気がする。」、「難民の数は今や約二十五万人と見積もられている。増えた五万人は廃墟になったところに住んでいた人たちだ。かれらは、どこに行ったらいいのかわからないのだ。」とあり、安全区へ難民が避難している光景が述べられている。
これまで安全区には20万人の市民・非戦闘員・難民がいたが、日本軍の南京入城以降難民が更に増え、その難民が安全区へ押し寄せているのである。
つまり、人口が20万人から25万人に増えたのは安全区の人口であって、南京市全体で表現すれば、南京市内で人口の移動があったというべきであろう。
(注2)ジョン・ラーベ『南京の真実』(講談社 1997年10月9日)183-184頁
(注3)ジョン・ラーベ前掲 185-187頁
(注4)ジョン・ラーベ前掲 190-191頁
(注3)ジョン・ラーベ前掲 185-187頁
(注4)ジョン・ラーベ前掲 190-191頁