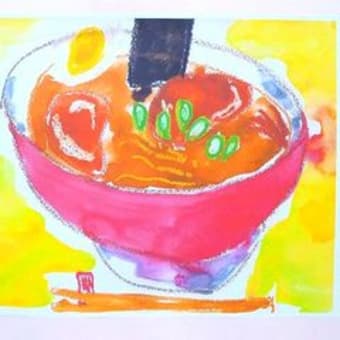70.生活にリズムを作る(15) ゆっくりお風呂その2
「知的障害児者、発達障害児者 個性と可能性を伸ばす!」
造形リトミック教育研究所
*楽しいからのパートナー
*新しく知るからのパートナー
*ちょっと簡単からのパートナー
 おはようございます。
おはようございます。入浴に関しての相談。
・衣服の着脱は自分でできるのに、やってもらいたがる。
・自分が入り終えると、お湯を抜いてしまう。
・何でも「やだやだ」と言って、お風呂にも入りたがらない。
自分が入り終えると、お湯を抜いてしまう:
家族がお風呂に入ろうとすると、お湯がない!これでは、びっくりですね。でも、お子さんの行動としては、「自分勝手」でも、「自分のことしか考えていない」のでもなく、「お湯を抜く=後始末をきちんとする」、という律儀な行動だと言えます。
では、どうしたらよいでしょうか?
「最後にお風呂に入った人がお湯を抜く」、というルールをわかるように示して、教えてあげることです。それをどうやって伝えるか?
表にしたらどうでしょうか?お風呂に入る人の名前を左欄に順番に書き込み「お湯を抜かない」「お湯を抜く」をその右欄に書き込む。「抜く・抜かない」を○×で表してもいいでしょう。
お風呂に入る順番が日によって異なるようでしたら、毎日表を変えてもいいのですが、ホワイトボードの利用が有効です。また表の枠は、ビニールテープを貼って作っておくと便利です。ホワイトボードも、A4サイズぐらいの大きさのものが、100円ほどで買えます。
漠然としたことやことばだけで説明したのでは理解しにくいことは、表にする。つまり視覚的に確認できる形にするのです。理解できないことをやらされたり、また逆に禁止されたり、律儀に行っているのに叱られたのでは、ストレスがたまるばかりです。
ひとつの困った行動を修正するのも、一工夫するとお互いに楽しくなります。納得して行動できるようにすることは、他の行動へも良い影響をもたらします。クリエイティブ!それは、ストレスの反対側にあり、良い循環を生みます。(つづく)
造形リトミック教育研究所
>>ホームページ http://www.zoukei-rythmique.jp/
>>お問い合せメール info@zoukei-rythmique.jp