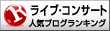白百合の花は、聖母マリアさまの象徴とされて、花言葉で言うと「純潔」「無垢」です。
私の母校は、函館白百合学園高等学校です。高校3年生の時、学園祭で一人芝居をしました。私は校長先生に、校長室へくるように言われました。一体なにごとかと内心冷や冷やしましたが、ごくほそい鎖のネックレスを頂戴したのです。小さな百合の花のペンダントヘッド、その裏にマリアさまが刻まれていました。「身隠しのマリアさまですよ。」と校長先生は仰られたとおもいます。先生はマ・スール(シスターの意味)です。その時、窓から入った光がたくさん部屋に溢れていました。両手でありがたく頂戴した白百合の花は、東京にひとり旅立つ私にとって、大切な御守りとなりました。
<白百合の花と文学>
人に伺うと、白百合は、一本だけの場合は「死者へ捧げる花」という意味になるのだそうです。一瞬、どきっとしますね。でも文学の世界に重ねると、怖いとか忌み嫌われるイメージではなく、こんな場面となります。
夏目漱石の「夢十夜」第一夜では、床についたある美しい女が
「百年、私の墓の傍に坐って待っていて下さい。きっと逢いに来ますから」
と言い残しこの世を去ります。男はその後、長い長い年月を経て女を待ちつづけます。そしてある夜。女との再会を諦めかけたその時に、男の目の前に一輪の白い百合の花が現れます。
「自分はこう云う風に一つ二つと勘定して行くうちに、赤い日をいくつ見たか分らない。勘定しても、勘定しても、しつくせないほど赤い日が頭の上を通り越して行った。それでも百年がまだ来ない。しまいには、苔の生えた丸い石を眺めて、自分は女に欺されたのではなかろうかと思い出した。
すると石の下から斜に自分の方へ向いて青い茎が伸びて来た。見る間に長くなってちょうど自分の胸のあたりまで来て留まった。と思うと、すらりと揺ぐ茎の頂に、心持首を傾けていた細長い一輪の蕾が、ふっくらと花弁を開いた。真白な百合が鼻の先で骨に徹えるほど匂った。そこへ遥の上から、ぽたりと露が落ちたので、花は自分の重みでふらふらと動いた。自分は首を前へ出して冷たい露の滴る、白い花弁に接吻した。自分が百合から顔を離す拍子に思わず、遠い空を見たら、暁の星がたった一つ瞬いていた。
「百年はもう来ていたんだな」とこの時始めて気がついた。」
私はあの美しくて哀しい…そして不思議に溢れた場面が大好きです。
自分が朗読することも、誰かの朗読を聴くことも好きです。
漱石がその意味合いを意識したのかどうかはわかりません。ほんとうのことはどうであれ、様々に感じる部分を深めてゆくと… 私にはまるで美しい幻燈をみるかのようにある姿が心に映ってきます。
「白百合」は理想の女性、という意味もあるようですね。
さまざまに思いを巡らせて、机の上の白い百合を眺めていました。
…うちのお花は、なんだか元気いっぱいですね(笑)