
確実に実家にこれと同じ本があるはず。paperbackの悪いところは、どうしても用紙が黄ばんでしまうことで、この黄ばんだ本にはあまり触れたくないんだよな。
だったら捨てようよと思うんだけど、例によって本を捨てることはなかなかできません!そして部屋が益々狭くなっているんですが…。
有名な話だけど、これが本屋で売られているかというとそうでもなく、これの本当の邦題
「アンドロイドは電気羊の夢を見るか」
をとりあえず脳内翻訳して、
"Do androids dream of electric sheep?"
を探してもらうべく、いつもの本屋のいつものお姉さんに、探していただいたところ、これが…。
なんか違う!
何度も言うが、ハードカバー3000円超の本は不要だ!
「"Blade Runner"でいいですか?」
と言われてハッとしたが、まあ、そういう名前もある。
この本が出版されたのが1968年だというんだから、もう40年以上前に書かれた「近未来」SF小説だったんだな、当時は。
その14年後にハリソン・フォード主演でRidley Scottがこれを映画にして、いまだにMy Favourite filmの1つです。Vangelisの音楽も大好きで、あっというまに虜になって、日本語訳の小説⇒原本を購入したわけです。
ハヤカワの表紙は、文字通り「羊」。実家で見かけたから今度日本語訳も読んでみよう。
そして、paperbackの表紙から笑える。
ネオンが
「料理」
「子持ちの烏口」
「光※★」(読めん)
「壺」
「人造ヱ(←この字は違う…)星に」
って意味分からん。そういやあ、映画でハリソン・フォードのリック・デッカードが、屋台でうどんを食べるシーン、うどん屋のオッサンが日本人。何年か前にその役者さんは亡くなったらしいけれど、
「1個で十分ですよ!」
とうどんの玉の数をリックと争っていたな、日本語で。
生身の動物を飼うこと(買うこと)がステータスであり、作り物のに羊は愛を注げても、作り物のアンドロイドを殺傷することは問題ない。
感情あるものを抹殺し、感情のないもの(或いは分かりかねるもの)は、庇護する。なんだろうか、この矛盾は。
某グリーンピースがクジラを護れとかで、捕鯨船を襲っているようなもの?ちょっと違うな。
最近の子供が、カブトムシが死んじゃった時に、
「"電池が切れた"から入れ替えて」
と親に頼むのは、あながちこの話と大差がある訳ではないんじゃないかと…。
映画とは全く違うけれど、この本は自分が何かを考えているふりをしたい時…とか、心をイガイガさせたい時に読むと、なんかホントに哀しくなってぐったりするんだよな。(ひとりSM?)
「40年前」における近未来の生活を描写しているわけですが、ドアをノックするアクションとか、電話は"dialed number"であるところが、いい意味で心に沁みました。
(って感想それだけ?!)










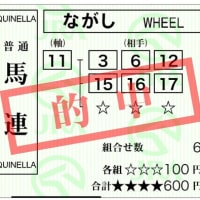
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます