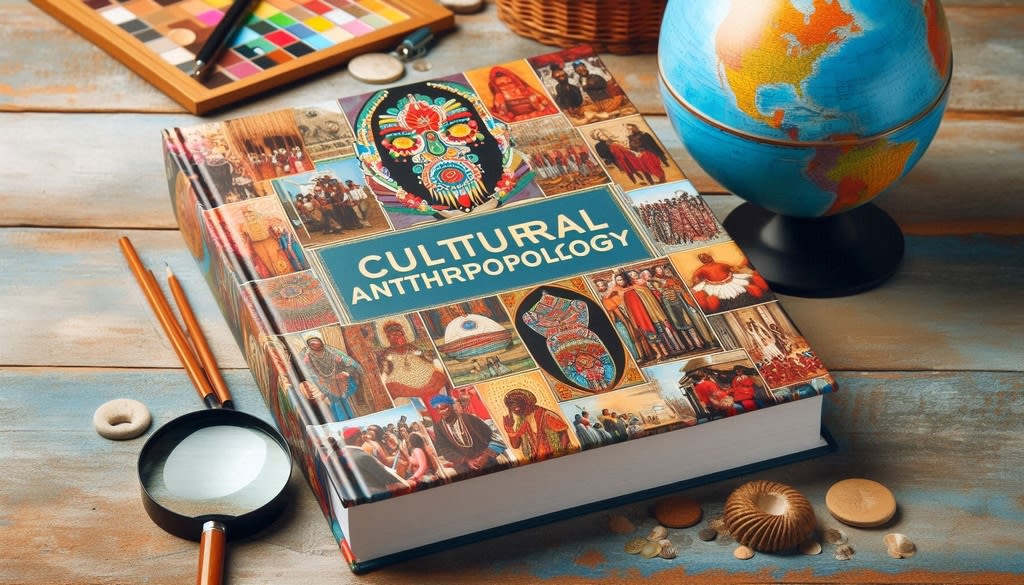
文化人類学の起源は、18世紀から19世紀にかけてのヨーロッパにおける啓蒙思想の影響と、植民地拡大がもたらした異文化との接触に深く関連しています。西洋では、啓蒙時代に人間社会や文化に対する体系的な理解が求められ、科学的手法を通じて異文化を探求する姿勢が広まりました。
初期の文化人類学
文化人類学の前身には、ヨーロッパの探検家や宣教師たちによる異文化の観察や記述がありました。彼らはアフリカ、アジア、南米などの非ヨーロッパ諸国を訪れ、そこでの文化や慣習をヨーロッパの視点で記録しました。19世紀後半になると、これらの記述が体系化され、進化論の影響を受けた「社会進化論」が誕生します。エドワード・タイラーやルイス・ヘンリー・モーガンなどが、文化や社会は進化するものであり、「野蛮」から「文明」へと進む段階的な過程で捉えました。
構造主義と機能主義の台頭
20世紀に入ると、社会進化論の限界が認識され、より具体的な文化の構造や機能に着目する理論が発展します。フランツ・ボアズ(Franz Boas)は、文化相対主義の概念を提唱し、すべての文化はその独自の文脈で理解されるべきだと主張しました。これにより、文化人類学は人類共通の普遍的進化を探るよりも、各文化の独自性を重視する方向に進みました。
東洋の視点
一方で、東洋やその他の地域でも文化人類学に類する思想が存在していました。たとえば、中国の古代思想家たちは、異民族の文化や習慣を記録し、国家の安定や外交政策に役立てようとしました。孔子の弟子たちは、異なる部族の風俗や道徳を観察し、それを「教化」の対象として捉えていました。インドでも、仏教徒やヒンドゥー教徒が異文化に関心を持ち、交流を通じて知識を広めました。
このように、文化人類学は西洋の植民地主義や科学的探究心によって発展しましたが、他の地域にも異文化への理解を深める思想的な土壌が存在していました。文化相対主義や現地でのフィールドワークを通じた学問的探究が進むことで、文化人類学は今日、異なる文化を尊重し、共感を持って理解する学問として確立されました。





















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます