私は小児科医ですが、思春期女子の生理痛・月経痛・月経困難症の患者さんも通院しています。
「生理痛がひどくてつらい」と相談に来る方はいないのですが、
ニキビの相談に来て、「実は生理痛もつらいんです」とか、
体調不良(起立性調節障害)で受診し、「実は・・・(以下同文)」とか、
小さい頃から通院してきた患者さんが「生理が始まってしばらくしてから痛みがつらい」とか、
間接的に相談を受けて、治療に至るパターン。
なかには、「整理の前になるとイライラして、家族も自分自身も大変です」
というPMSに悩む中学生女子もいました(この方は漢方が著効)。
生理痛は市販の鎮痛剤でしのいでいることが多いようですが、
漢方薬が有用です。
私の治療方針は「鎮痛剤+漢方薬」です。
患者さんの体質・体調により漢方薬を何種類か使い分けています。
数種類試しても手応えがない場合や、
痛みがひどくて学校を休むなど生活に支障が出るレベルでは、
単なる生理痛ではなく、治療が必要な病気が隠れている可能性を考慮し、
婦人科へ誘導しています。
婦人科では、スクリーニング検査で器質的疾患がなければ、
ホルモン剤を勧められるようです。
婦人科医が思春期の月経困難症について説明している記事が目に留まりましたので紹介します。
<ポイント>
・小児でも鎮痛剤で効果が不十分な場合、ホルモン製剤などによる介入で月経のつらさは大きく軽減できる。
・ホルモン製剤(※)は種類が多く、薬剤によっては不正出血などの副作用も生じ得る。効果や副作用に個人差もある。
※ 低用量エストロゲン・プロゲスチン配合薬(LEP、保険適用の低用量ピル)、プロゲスチン製剤など。
・小学生が、器質的異常のない機能性の月経困難症を生じることも珍しくなく、月経前症候群(PMS)を訴えることもある。
・小児の月経痛の場合、月経血流出路の狭窄を来す先天性の子宮奇形が原因となっていることもあり、まれな疾患ではありますが、見逃さないよう注意する。
ホルモン製剤の使い分けや副作用対策も書かれています。
気になる文章もありました;
「以前、小学生の患者さんが当院を受診された時に「家の近くの病院に何件か問い合わせたけれど小学生は診ていないと言われた」という話を聞き、驚きました」
・・・そうなんです、当院の近隣の婦人科開業医も小学生・中学生は門前払いなのです。
これは精神科にも言えることで、
「中学生までは薬が使えないので受診しても意味がない」と断られることが多いのです。
では、小中学生の婦人科疾患・精神科疾患は誰が診療するのでしょう?
診てくれる医師を探して患者さんが彷徨っているのが現状です。
この問題は個人開業医のレベルではなく、学会レベルで検討して欲しいですね。
▢ 思春期の月経困難症、様子見せず積極的な介入を
稲葉可奈子氏(Inaba Clinic院長)に聞く
初経は、多くの場合10歳から14歳ごろに認められ、小学校6年生の女子では半数以上が月経に対応しながら生活を送っているという報告もある。小児科でも月経困難症への対応を求められる機会は少なくないようだ。日経メディカル Onlineが2024年9月に医師会員を対象に行った調査では、小児科医から「患者から月経痛の相談を受けるが対応に難渋している」といった声が多く挙がった(関連記事:月経困難症、非専門医の多くはNSAIDsや漢方薬で対応)。
「小児でも、ホルモン製剤などによる介入で月経のつらさは大きく軽減できる」と語る産婦人科医の稲葉可奈子氏(Inaba Clinic[東京都渋谷区]院長)に、思春期の月経困難症診療のポイントについて聞いた。
──小学生や中学生でも、受診するほどの月経痛で困っている患者さんが多くいらっしゃるようですね。
稲葉 その通りです。月経痛は「子どものうちは伴わず、成長するにつれて生じるもの」とは限りません。初経を迎えていれば、小児でも成人と同じように、軽い子もいれば、重い子もいるものです。小児の月経痛の場合、月経血流出路の狭窄を来す先天性の子宮奇形が原因となっていることもあり、まれな疾患ではありますが、見逃さないよう注意する必要があります。小学生が、器質的異常のない機能性の月経困難症を生じることも珍しくなく、月経前症候群(PMS)を訴えることもあります。最近では、月経痛を治療したり月経の日を調整したりできることの認知度が上がっており、中学受験の前に受診する患者さんもいます。
──お子さんやその保護者から、受診時に月経困難症の相談を受けて、対応に悩まれている小児科の先生もいらっしゃいます。
稲葉 月経困難症は「月経に伴う下腹部痛や腰痛、頭痛などの病的症状」を指しますが、明確な治療開始基準はありません。臨床的には本人の「つらい」という自覚症状が最も重要なので、患者さん本人が月経痛で困っているなら婦人科に紹介してもらえればと思います。受診時に相談がある時点で、きっと患者さんは困っていますよね。多くの思春期の患者さんにとって、婦人科受診のハードルは高いかと思いますので、受診した場合には内診はほとんど行わないことや、治療について説明を聞いた上でいったん治療しない選択肢があることも伝えていただきたいです。
治療法に関しては、鎮痛薬や低用量エストロゲン・プロゲスチン配合薬(LEP、保険適用の低用量ピル)、プロゲスチン製剤、漢方薬などがあります。多くの医師が使い慣れている鎮痛薬と異なり、ホルモン製剤は種類が多く、薬剤によっては不正出血などの副作用も生じ得ます。効果や副作用に個人差もあります。例えば、小児科で鎮痛薬を処方してみてもまだ痛くてつらい、など、症状が改善しない場合には婦人科医に紹介するという形もあると思います。
──稲葉先生は、月経痛を訴える思春期の患者さんにはどのような治療を選択されているのか、教えてください。
稲葉 まだ鎮痛薬を使用したことがない患者さんなら、年齢によりアセトアミノフェンやNSAIDsなどの鎮痛薬を勧め、鎮痛薬を使用しても痛みが軽減しない場合はホルモン製剤を提案しています。LEPは、片頭痛がある場合は脳梗塞のリスクを増加させることが知られているため、添付文書上、前兆のある片頭痛では禁忌、前兆のない片頭痛では注意が必要とされています。幸い今は、プロゲスチン製剤のジエノゲスト(商品名ディナゲスト他)がありますので、片頭痛がある場合はジエノゲストをお勧めしています。片頭痛がない場合はLEP(特にヤーズフレックス[一般名ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス])とプロゲスチン製剤それぞれの説明をして、相談して方針を決めています。
LEPの中には、4週間に1回の休薬期間を設け、消退出血を起こさせる薬剤も多いですが、そもそも毎月消退出血を生じさせないといけないわけではありません。むしろ消退出血が起こるときに腹痛や頭痛を伴う場合もあります。ヤーズフレックスは、消退出血の回数を4週間ごとよりも減らすことができます。最大120日間連続で服用できるので、うまくいけば年に3回程度に減らすことができるだけでなく、学校行事などに合わせて消退出血のタイミングを自分でコントロールできることが大きなメリットです。こうした理由から、LEPの場合はヤーズフレックスをまずお勧めしています。もちろん合う人合わない人がいますので、何か気になる症状があれば薬を変更します。
一方ジエノゲストは、1日1回の服用でよいLEPと異なり、1日2回服用する必要がありますが、月経痛は軽減しますし、骨代謝への影響がLEPよりも少ないとされています。LEPは、添付文書上は、骨端の早期閉鎖を来す恐れがあるため、骨成長が終了していない可能性がある患者は禁忌とされていますが、初経後の低用量エストロゲン・プロゲスチン配合薬の投与が将来的な身長に影響するとの報告はありません。ただし、獲得骨量が低下する可能性があるという報告は存在し、「OC・LEPガイドライン2020年度版」(日本産科婦人科学会、日本女性医学学会)では「初経発来後から使用できるが、骨成長、骨密度への影響を考慮する必要がある(推奨レベルB)」とされています。
データ上、身長には影響しないとされていても、もし将来、患者さん自身の希望よりも身長が伸びなかった場合に「LEPの影響ではないか」と思ってしまう可能性はあります。そのため、身長の伸びが気になる患者さんには、将来気にしなくてすむようにジエノゲストにしておく方が良いかもしれないですね、という説明をしています。
──先生はクリニックのウェブサイトに「小学生・中学生・高校生でも治療できます」と明記されていますが、「近隣に思春期の女子を診察してくれる専門医の心当たりが少ない」「近隣に紹介できる婦人科がない」といった声もあるようです。
稲葉 以前、小学生の患者さんが当院を受診された時に「家の近くの病院に何件か問い合わせたけれど小学生は診ていないと言われた」という話を聞き、驚きました。他には、小中学生の診療を行っていても「まだ若いからひとまず様子を見よう」といった対応がなされることもあるようです。成長に伴って月経痛が軽くなる保証はなく、若いから治療できない、子どもだから我慢するしかないというわけではありません。学校生活に影響が出ることもありますし、年齢にかかわらず適切な治療を行うべきだと考えています。小児を積極的に診療している婦人科医の数はまだ十分とは言えないのかもしれませんが、小児科の先生には、日ごろから相談でき、安心して紹介できる婦人科医を見つけていただければと思います。
月経痛の緩和には、ストレスの低減や腹部を冷やさないといった生活の改善が有効という話も見かけますが、ストレスを減らすのは大人でも大変ですし、生活習慣の改善による効果には限界があります。せっかく痛みを軽減する有効な治療方法があるわけですから、思春期の患者さんでも選択肢として示していければと考えています。
<参考>
・思春期の月経困難症(日本産婦人科学会)











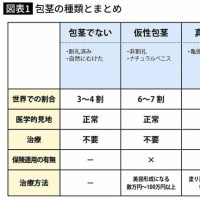
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます