生理痛を鎮痛薬で凌いでいる助祭はたくさんいると思います。
生活に支障が出る(学校や仕事を休む)レベルでは医療の介入が必要ですし、
治療効果に手応えがない場合はベースに病気(器質性月経困難症)が隠れていないかどうかの検討が必要です。
先日視聴した産婦人科医によるWEBセミナーでも「とにかく月経痛が強くてつらい場合は、ホルモン剤(低用量ピル)が有効なので推奨します」とコメントしていました。
当院は小児科なので、他の症状で受診されたときについでに相談を受けることがあります。
軽症であれば鎮痛剤頓服、それでもつらければ漢方薬の定期内服を手案しています。
漢方薬には“婦人科三大処方”というくすりがあり、その人の体力・体質に応じて当帰芍薬散(23)、加味逍遥散(24)、桂枝茯苓丸(25)の三つを使い分けます。患者さんの7割に手応えがあり、月経痛が軽減します。
また、加味逍遥散(24)は月経前症候群(PMS)にもよく効きます。
三剤とも、錠剤が用意されていますので、「漢方は苦くて飲めない」女性にも使用可能です。
さて、月経の鎮痛に関する記事が目に留まりましたので、紹介します。
▢ リポート◎月経のつらさは医師の介入で軽減できる〜「鎮痛薬ありき」から一歩先へ、月経困難症の多様な治療選択肢
近年、月経困難症に対する治療選択肢は多様になった。その一方で、月経のつらさを抱える女性が皆適切な治療を受けられているとは言い難い状況だ。診療の課題や治療選択肢、非専門医ができる介入について紹介する。
月経期間中に、月経に随伴して下腹部痛や腰痛、頭痛などの病的症状が起こる月経困難症。厚生労働省が2022年に発表した調査結果によると、月経痛がある18~49歳の女性1724人のうち75.4%が「医療機関(婦人科等)を全く受診していない」と回答した(厚生労働省)。その理由として、「医療機関に行くほどのことではないと思うから」が43.1%で最多。「仕事を休みづらいから」「医療機関に行くことが恥ずかしいから」と回答した人がいずれも約10%だった(複数回答)。
東京大学医学部附属病院女性診療科・産科准教授の平池修氏は、「月経痛や月経前症候群(PMS)、更年期障害といった『女性特有の健康課題』は、社会的な認知度こそ上がってきたが、適切な受診につながっていないケースは多い。『たかが月経痛』ではなく、安心して受診して治療を受けられる疾患だという認識がまだ不十分だ」と指摘する。
▶ NSAIDsの効果は本当に十分?
いまだ、「仕方がないもの」と考えられがちな月経困難症だが、最近、治療の選択肢は広がっている。淀川キリスト教病院(大阪市東淀川区)産婦人科医長の柴田綾子氏は、「月経困難症には明確な診断基準はなく、患者が痛みで困っていたら、治療対象になる。学校や仕事、家事など、日常生活に支障が出ているような状態なら治療した方がよい」と話す。
月経困難症には、子宮腺筋症や子宮内膜症、子宮筋腫などの原因疾患を伴う器質性月経困難症と、子宮や卵巣に明らかな異常が認められない機能性月経困難症がある。前者は、まず原因疾患の治療を行うことが原則だが、後者では、治療によって苦痛なく過ごせるようにすることが重要だ。
「産婦人科診療ガイドライン─婦人科外来編2023」(日本産科婦人科学会、日本産婦人科医会[以下、ガイドライン])では、クリニカルクエスチョン「機能性月経困難症の治療は?」に対して、
「鎮痛薬(NSAIDsなど)による対症療法を行う(推奨レベルB)」
「鎮痛薬(NSAIDsなど)の効果が不十分な場合は、低用量エストロゲン・プロゲスチン配合薬(LEP)※、プロゲスチン製剤、またはレボノルゲストレル放出子宮内システムを使用する(B)」
「漢方薬あるいは鎮痙薬を投与する(C)」と示されている。
※ LEPは月経困難症や子宮内膜症に伴う疼痛など疾患の治療を目的として保険診療で用いる。経口避妊薬(OC)もエストロゲンとプロゲスチンの合剤だが、避妊を目的に自費で使用する。
実際には、月経痛に対して、OTC医薬品の鎮痛薬を服用したり、かかりつけの医療機関でNSAIDsなどの鎮痛薬を処方されたりしているケースは少なくない。ただ、「医師が『効いているだろう』と思っていても、実際には効果が不十分な場合もある」と平池氏。ガイドラインでも「(NSAIDsの)効果は64~100%との報告もあるが、15%以下において効果が認められなかったとの報告もある」と記されている。平池氏は「鎮痛薬の処方後は、痛みや生活への影響が本当に軽減されているかを患者に確認することが欠かせない」と話す。
その上で、「鎮痛薬を使用しても生活に支障が出ている場合、LEPやプロゲスチン製剤によって劇的に楽になることも多いので、婦人科医への紹介を検討してほしい」と柴田氏。「器質性疾患の有無を診断するためにも、月経困難症診療に携わっている婦人科医の受診が望ましいだろう」(平池氏)。
▶ 月経困難症の治療選択肢の特徴は?
月経困難症に対して、ガイドラインで示されている主な治療の選択肢は表1の通りだ。

表1 月経困難症に対する主な治療選択肢
(添付文書や柴田氏への取材を基に編集部作成、2025年1月31日時点)
まず、LEPはエストロゲンとプロゲスチンの合剤であり、薬剤によってプロゲスチンの種類が異なるなど、複数の選択肢がある(2025年1月時点で、ヤーズ[一般名ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス]、ルナベル[ノルエチステロン・エチニルエストラジオール]は後発品が存在)。エストロゲンを含有しているため、血栓症リスクの高い患者には適しておらず、添付文書では、「前兆を伴う片頭痛の患者」や「35歳以上で1日15本以上の喫煙者」「血栓性静脈炎、冠動脈疾患などや、その既往歴がある患者」などには禁忌だ。「血栓症や副作用のため使用できない患者もいるが、LEPは月経痛や出血量を減らす効果が高いと実感している」と柴田氏。複数ある選択肢の中から、薬価やPMSへの効果の有無など※を考慮して、患者と相談しながら選択しているという。
※ PMSはLEPの適応症ではないが、ガイドラインではPMSに対して「ドロスピレノン・エチニルエストラジオール錠を処方する(推奨レベルB)」と記載されている。
一方、プロゲスチン製剤のジエノゲスト(商品名ディナゲスト他)は、エストロゲンを含まないため、血栓症リスクの高い患者にも使用でき、後発品もあることが大きなメリットだ。ただし、「個人差はあるが、月経が完全に止まり快適に過ごす方もいる一方で、特に服用を開始した時期は不正出血が生じやすく、服用をやめてしまう患者も見受けられる」(柴田氏)という。同じくプロゲスチンを含有するレボノルゲストレル放出子宮内システムは、子宮腔内に装着すれば最長5年間効果が持続する。挿入時に痛みを伴うため、未経産婦や器質性疾患がある場合は特に、事前に患者と相談が必要だ。
漢方薬も幅広い患者に使用できる選択肢だ。柴田氏は、効果発現が緩やかな当帰芍薬散や加味逍遙散、桂枝茯苓丸は1日2~3回の内服を継続とし、即効性のある芍薬甘草湯は症状の強いケースに対して、頓用で処方しているという。
ブチルスコポラミン(ブスコパン他)などの鎮痙薬は、ガイドラインに「思春期の月経困難症の中には(中略)有効であるケースもみられる」との記載があり、柴田氏も「思春期や若年の患者で痛みが強いときに頓用で使うことがある」と話す。
このように月経困難症の治療選択肢は多岐にわたるが、国内ではホルモン製剤は婦人科医によって処方されているケースが多く、非専門医は鎮痛薬や漢方薬での対応にとどまっているのが実情だ(関連記事:月経困難症、非専門医の多くはNSAIDsや漢方薬で対応)。一方で、患者が薬局で自らLEPを購入できる国もある。
婦人科以外の医師がホルモン製剤を処方することに対する考えは専門医の中でも様々だが、柴田氏は「ホルモン製剤を使用するハードルを下げることは、痛みで悩んでいる患者のためになる。定期的な器質性疾患の検査は専門医療機関で行うなど、婦人科医と連携した上で、プライマリ・ケア医が処方してもよいのではないか」と述べる。
月経痛は数十年にわたり患者のQOLを大きく低下させる。「患者が痛みを訴えたときは、『痛み止めありき』ではない治療につなげるべきだ」と平池氏は話している。











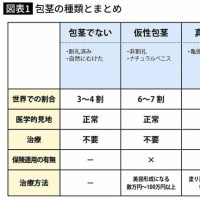
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます