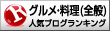こんにちは 横森です
今回は再来週、大浜だいしんアリーナで開催予定の全日本シニア柔道体重別選手権について書きます。

今大会の歴史は非常に浅く、今年で第3回です。柔道の競技力向上を目的としたオープン開催の全国大会ですが、警官が出場している点で全日本実業団柔道選手権と一線を画します。また、国内有数のビッグトーナメントでありながら、講道館杯出場枠が決勝に進出した2名にしか与えられないという点も特徴的であります。警官が出場すると試合の様相もだいぶ変わってきます。今年は特に、学生時代に全国区で活躍していた選手の多くが地方都道府県警察に所属しており、実業団個人戦とは全く異なる結果が予想されます。

近年では警視庁、神奈川県警、大阪府警、兵庫県警、福岡県警などが強豪選手を多く揃えている一方で、強豪企業に所属する非強化選手の早期敗退が目立ちます。また、講道館杯で来年度の同大会出場権を得られなかった選手も、この大会に出場するケースが大半です。こうした点では全日本シニアは講道館杯以上のレベルの大会と言えるかもしれません。

過去の今大会の結果を見ると、決勝進出者は以前何かしらのカテゴリーで全国大会入賞経験のある実業団選手や講道館杯出場者が多いようです。昨年は穴井隆将天理大学監督が出場し、初戦で習志野高出身の瀧川選手(明心館)に一本勝ちを収めたことが話題になりました。また、高藤選手(パーク24)が66kg級デビュー戦に選んだ試合でもありましたが、結局は欠場でした。

また、近頃は各地で全日本柔道選手権の県予選が行われています。入賞者一覧を見ていると、実業団が強い県、警察が強い県、学生や高校生が強い県など特色があることがわかります。

京葉ガスやSBCの本拠地である千葉県は毎年のように入賞者が実業団選手です。千葉県出身で日本一になる選手はほぼ全員が県外に出てしまい、就職に際して帰葉するケースも多いため、こうした結果になるのかもしれません。

一方、名門・筑波大学を擁する茨城県は国スポ代表選手を見ても明らかなように、筑波大学の学生や、県内企業に勤務する筑波大学卒業生が上位を独占しています。今年の茨城県選手権は全日本強化B指定の田中龍雅選手が、決勝で筑波大学主将にして昨年度の全日本学生柔道体重別選手権100kg級準優勝の田中航太選手を下して優勝しました。

栃木県選手権と埼玉県選手権は、いずれも県内出身の地方県警が入賞者の大半を占めましたが、両県とも高校生が決勝進出を決めたことがニュースとなりました。栃木県選手権では超巨漢の黒田選手(白鴎大足利)、埼玉県選手権では平野選手(埼玉栄)が高校生ながらに関東選手権へと駒を進めました。

わたしのはなし
中学生の頃、埼玉栄中学と対戦しました。当然5−0で負けましたが、私がその際に対戦した西山選手は今年度の実業団個人戦で計量オーバーして失格でした。強すぎて組手はあっさり持たせてもらえた上、なすすべなく投げられたことをよく覚えています。

自分の柔道人生で、我ながら金星を上げたことが一度だけあります。同じく中学時代、マルちゃん杯関東大会で東海大相模中学校と対戦しました。その代の相模中は後に講道館杯を制し、日の丸を背負う天野選手を先鋒に配した布陣でした。私は中堅でした。2−0で回ってきました。どうせ負けるだろうと思い、何となく試合上に立ちました。

終わってみれば私の体落の技ありによる優勢勝ちでした。その相模の選手がその後、活躍したかはわかりません。無名選手だったのかもしれません。しかし、いち田舎の中学生にとって東海大相模の選手に勝つことが出来たことは自信になり、満を持して挑んだ2週間後の中学最後の県大会は東海大浦安の2年生に負けました。結局、日本柔道は東海大が牛耳っているのかもしれません(?)。

ちなみに私に勝った浦安の選手は現在東海大柔道部に所属しています。中学時代は私に勝った後、後に全日本学生体重別で3位に入賞することになる黒川選手(現明治大学)に敗れました。