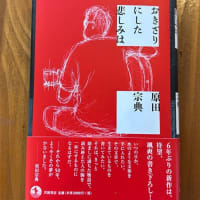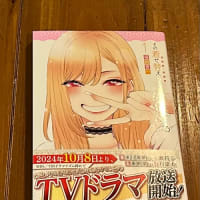今日、久しぶりに本屋さんに行ったら、『蒼穹の昴』浅田次郎著が文庫で平積みになっていました。お正月にNHKのドラマになるためらしいですが、もし読んでいない方がいたら、お薦めの本です

何年か前にこの本の紹介記事を県立大学のフリーペーパーに書いたので、以下に紹介しますね。学生さん向けに季節の一冊として書いたものです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
 蒼穹の昴(そうきゅうのすばる) 浅田次郎
蒼穹の昴(そうきゅうのすばる) 浅田次郎 
これは、中国の清朝末期の動乱期の歴史的事実とフィクションを織り交ぜて語られる壮大な物語です。主役の春児(ちゅんる)は中国の田舎の貧しい子どもで、牛馬の糞を拾って細々と生きていました。そして、その父や兄と同じように飢えと寒さでいつ死んでもおかしくない、将来に希望のない日々を送っていました。しかしある日、村の老いた占い師に「おまえは、たぐい稀な星まわりに生まれついている。その守護星は昴(すばる)であり、末には紫禁城の奥に仕え、中華の財宝をその手に入れるだろう。」と告げられるのです。
地主の次男の梁文秀(りょう ぶんしゅう)も、この占い師に「将来は科挙の最終試験に通り、都で天子さまに仕え、政を行なうだろう。しかし、困難な一生となる。心して仕え、ほこり高く生きよ。」と告げられていました。文秀は型破りな性格で、貧し春児を弟分として面倒をみていました。そして、お告げどおりに、科挙の試験に次々と合格し、ついに最終試験「順天会試」に臨むべく北京に行くのです。その時に春児も話し相手として連れていきます。
ここから、二人の運命が大きく展開していきます。まず、中国の熾烈な科挙の試験の様子がリアルに再現されていて、びっくりさせてくれます。その後、この二人を中心に物語が進んでいくのですが、清朝末期の宮廷と政治をその手に握っていた西太后、その祖先の物語、文秀と共に試験を受けた若き秀才たち、清朝末期に名を残した人々、名も無き人々の物語が縦横無尽に語られます。
著者の浅田次郎は巧みなストーリーテラーですが、他の作品では技巧的すぎて好きになれないものもあります。しかし、この本はその技巧を感じさせない面白さと奥深さがあります。登場人物が多いにもかかわらず、それぞれの個性が際立っており、清朝末期の混乱と、それに翻弄される人々の波乱万丈な人生から目が離せなくなり、最後まで一気に読み進んでしまうことと思います。最近何かと注目されている中国の、長い長い歴史の一端をかいま見て、この後の中国や日本の歴史を思い返してみるのも良いかもしれません。
最近、講談社文庫に収録されました。秋から冬にかけての夜長に読む本としておすすめの一冊です。でも、面白すぎて寝不足にならないように注意してくださいね。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・
あまり小説を読まない夫が、面白いと言って、続編とも言える『中原の虹』まで読んでいましたから、相当面白いということで、お薦めの一冊(といっても長いので、文庫は何冊かにわかれていると思いますが)です
 そして、恥ずかしながら泣けました
そして、恥ずかしながら泣けました
私的には、ドラマを見る前に読んだ方が楽しめるのではと思います。



 すごくおもしろかったです。長い物語でしたが、まさに寝る間を惜しんで読みふけったな~読んだあと、北京に旅行しました。行く前に、もう一度読みました。紫禁城を歩くとき、浅田次郎の文章が思い出され、2倍楽しめました
すごくおもしろかったです。長い物語でしたが、まさに寝る間を惜しんで読みふけったな~読んだあと、北京に旅行しました。行く前に、もう一度読みました。紫禁城を歩くとき、浅田次郎の文章が思い出され、2倍楽しめました