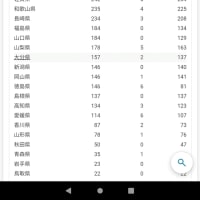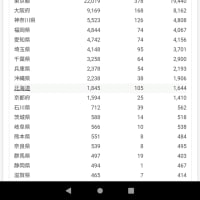とてもいい記事なので、拡散します。
(元記事 https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/58831)
(元記事 https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/58831)
-----------------------------------------------------------------------
パンツの中まで調べられたゴーン氏が選んだ治外法権
国際社会が「脱日本」を正義と見做す可能性
2020.1.7(火)
伊東 乾
2020.1.7(火)
伊東 乾
カルロス・ゴーン氏の所在が2019年12月30日、レバノンのベイルートで確認された、という報道で、日本国内はゴーン一色のお正月を迎えているようです。
実際、本稿の校正時点でも「ゴーン容疑者の不法な脱出」「トルコの航空会社が刑事告訴」といった日本語の記事ばかりが目立ちます。
「ゴーンは悪い。悪い奴が法を破って悪いことをした」というPRが大半と見えます。しかし国際的にみれば「よくて5分」議論は2分、というのが過不足ないところと思います。
実際、本稿の校正時点でも「ゴーン容疑者の不法な脱出」「トルコの航空会社が刑事告訴」といった日本語の記事ばかりが目立ちます。
「ゴーンは悪い。悪い奴が法を破って悪いことをした」というPRが大半と見えます。しかし国際的にみれば「よくて5分」議論は2分、というのが過不足ないところと思います。
トルコの航空会社が不法利用を提訴(https://www.reuters.com/article/us-nissan-ghosn/security-camera-shows-ghosn-leaving-tokyo-home-alone-before-his-escape-nhk-idUSKBN1Z208D)もロイター電ですが、テレグラフ紙(https://www.telegraph.co.uk/business/2019/12/31/japans-tough-justice-means-carlos-ghosn-right-flee/)には映画「大脱走」などで知られるアンチヒーロー、スティーヴ・マクィーンの名を挙げつつ、ゴーンは「正義」から逃亡したのではなく、日本の不正な司法から脱出したと擁護、日本語でも、数は少ないながらオリンパス長年の粉飾決済を告発して解任されたマイケル・ウッドフォード元社長による痛烈な司法批判(https://www.jiji.com/jc/article?k=2020010200374&g=int)など、大本営発表式の一律報道と正反対の主張が確認できると思います。
楽器の箱に隠れて「パーティ会場を抜け出した」あるいは「そのまま出国」など、いまだ情報が錯綜している報道を元旦のベルリンで耳にしながら、筆者は率直に「やはり・・・」という思いとともに、国際世論が「どちら」に味方するか、が気になっています。
例えば私たちは「北朝鮮」から脱出してきた人たちを、命がけで不当な権力に背を向けた英雄のように捉えることがあります。
ベルリンでは、冷戦時代に「ベルリンの壁」を突破して自由な西側世界に脱出してきた人たちは、事実「英雄」でもありました。
これと同じように、今回のカルロス・ゴーン氏「日本脱出」・・・「脱北」同様に短縮するなら「脱日」とでも呼ぶべきでしょうか・・・を、国際世論が「正義の行動」と捉えれば、日本国にとっては大変なダメージになるでしょう。
日本という国は、まともな法治が成立せず、官憲の横暴がまかり通るとんでもない「ならずもの国家である」というのが、とりわけコンプライアンス関係者を中心に、ゴーン氏のメインメッセージとして国際社会に受け入れられ始めていますし、日本国内でも郷原信郎弁護士(https://news.yahoo.co.jp/byline/goharanobuo/20200101-00157363/)を筆頭に、明確な根拠に基づいた批判がなされています。。
あえて言えば、カルロス・ゴーン氏は日本の司法制度を見限った。
こんな未開で野蛮なところに置かれていたら、どんな目に逢うか知れたものではない。現地民の掟などにはとても従っていられない、という「治外法権」を自ら宣言して、彼は父祖の地、レバノンに降り立って世界に向かって正面から情報を発信している。
日本国内で「ソンタク」の何のと、微温な表現に世論が慣れているような場合では、すでにないところまで、事態は発展しています。
日本は直接のやり取りができないレバノンに、ICPO(国際刑事警察機構)はゴーン氏の身柄引き渡しを求めましたが、1月2日、アルベール・セルハン・レバノン暫定法相はこれを否定。
日本での裁判は実質的に開廷が至難となっています。そもそもそのような司法案件として、きちんと物事は成立していたのか??
基本的人権のない国
実際、レバノンに到着したゴーン氏は「私は有罪が前提とされ、差別が蔓延し、基本的な人権が無視されている不正な日本の司法制度の人質ではなくなります」と、日本の司法制度を全面的に「不正」と断じ、公式な情報発信をスタートさせています。
「私は正義から逃げたわけではありません。不公正と政治的迫害から逃れたのです」という発言は、日本から脱出したカルロス・ゴーン氏のものか、北朝鮮から脱出した脱北者のステートメントか、文言だけでは判断がつかないでしょう。
(もちろん、ゴーン氏の発言にほかなりません)
「私は正義から逃げたわけではありません。不公正と政治的迫害から逃れたのです」という発言は、日本から脱出したカルロス・ゴーン氏のものか、北朝鮮から脱出した脱北者のステートメントか、文言だけでは判断がつかないでしょう。
(もちろん、ゴーン氏の発言にほかなりません)
さらに、「私は不公正と政治的迫害から逃れました。ようやくメディアと自由にコミュニケーションができるようになりました。来週から始めるのを楽しみにしています」と言います。
日本はいったん刑事事件の容疑者、あるいは被告人となると、あらかじめ有罪が前提とされ、無実を主張しようとしても自由な社会発信「すら」できないという事実を表明、国際社会には「ゴーン氏の主張こそ妥当」と見る向きも決して少なくないことが予想されます。
「人質司法」と日本の「罪人観」
一連の「ゴーン事件」は2018年11月19日、東京地検特捜部によって日産のカルロス・ゴーン元会長が逮捕されたことでスタートしました。
日本と欧州を往復する私の耳に強く聞こえてきたのは、先進国としては常軌を逸した司法手続きの「不当さ」への疑問が大半でした。
事実、各国から矢の批判が相次ぎ2019年2月には衆院予算委員会で法務大臣が、例によっての「問題ない」式の答弁もしており、私に身近な欧州の関係者からはただただ呆れられていました。
4回に及ぶ無理筋の「再逮捕」と、108日にも及ぶ「拘留」は、それだけ取り上げても極めて「異例」ないし「異常」な「人質司法」の実態が、広く国際社会に知られることとなりました。
やっとその状態が解消した直後の2019年4月4日、さらに極めつけの「再逮捕」となった経緯は、国際的に「日本の検察は正気か?大丈夫か?」という、通常とやや異なる心配もって受け止められるところまで進んでしまった感がありました。
ちなみにウエブで「人質司法」の英語を調べると、「Hitojiti Shiho」 という「英単語」が見つかるでしょう。
「人質」と「司法」をバラバラに英訳して「hostage justice」として検索すると、トップにBBCのゴーン事件報道(https://www.bbc.com/news/world-asia-47113189)、続いて上記昨年4月の「ゴーン再逮捕」時の報道(https://www.japantimes.co.jp/news/2019/04/17/national/crime-legal/examining-carlos-ghosn-japans-system-hostage-justice/#.Xg86qW5uJjo)が出てきます。
「人質」と「司法」をバラバラに英訳して「hostage justice」として検索すると、トップにBBCのゴーン事件報道(https://www.bbc.com/news/world-asia-47113189)、続いて上記昨年4月の「ゴーン再逮捕」時の報道(https://www.japantimes.co.jp/news/2019/04/17/national/crime-legal/examining-carlos-ghosn-japans-system-hostage-justice/#.Xg86qW5uJjo)が出てきます。
これは、おかみが「お縄」にした「とがにん」は、拷問でも何でも方法を選ばず「自白」させ、自白したものは有罪だ、ということで、目をつけた容疑者は必ず「有罪ありき」で犯罪人と確定する、21世紀の国際社会では極めてユニークな日本独自のシステムであることを意味します。
要するに「人質司法」という現象は、世界に類例の少ない、極めて「日本的」な“伝統”ないし土俗の風習であることが、客観的に理解できるかと思います。
この折は、郷原信郎弁護士もリアルタイムで指摘している通り(https://mainichi.jp/articles/20190405/mog/00m/040/012000c)、何とか「自白」を引き出して、ゴーン氏を「落そう」とした検察側の、最後の「暴発」でありました。
事実、東京地裁は4月25日に保釈を決定しますが、なりふり構わぬ日本検察の「手法」は、国際社会に明確に印象づけられることとなりました。
ここに至るゴーン事件の詳細については、すでに多くの報道もなされており、改めてここで繰り返すことは避け、より本質的と思う点を掘り下げてみたいと思います。
それは日本列島に特有の「罪人」に対する感覚にほかなりません。
日本社会には「推定無罪」という発想が、ホンネの部分に存在していません。誤認逮捕であろうと、冤罪事件であろうと、「いちど捕まったものは犯人、罪人」という見方が本質的に定着しています。
国際社会を見渡せば、容疑者段階では実名を報道しないケースも少なくありません。
しかし、日本では一度「逮捕」されると、仮に誤認逮捕で、無罪が確定して「前科」なしでも「前歴」がつきます。それが露わになると、就職その他に著しい困難があるのが日本社会の現実です。
翻ってフランスでは、大統領を務めた二コラ・サルコジは故カダフィ大佐からのリビア・ゲート献金問題で2度も身柄を拘束されていますが、昨年10月は「即位正殿の儀」にフランスを代表して参列しています。
外事の局面における日本社会のへっぴり腰には定評があるゆえんです。
ところが、ゴーン事件に関しては最初から検察発表がそのまま喧伝され、ゴーン氏側が無罪の情報発信を試みると「再逮捕」といったプロセスを、国際社会、特にフランスは今回の経緯ではっきり認識するところとなってしまいました。
こうした日本の「罪人観」は、ゴーン氏のレバノン会見でも明確に指摘されている通り、日本社会の「差別」と極めて深く結びつく、根の深いものにほかなりません。
江戸時代以前「士農工商」の常民の<埒外>に置かれた人々が様々に差別を受けたことは21世紀の日本社会でもそれなりに知られています。
しかし、主要な「被差別」の対象が「犯罪者」と、その犯罪者を取り締まったり、処罰を執行する「刑吏」に大別されることなどに始まる、具体的な差別の詳細はほとんど理解されていないのが実情の一つ。
また、刑事司法の対象となった者が、刑期などを終えて以降も、就職など通常の社会復帰が困難であること。
平たく言えば、前科のある人間を雇う会社は2020年の日本でも極めて例外的で、その背景には、犯罪の「嫌疑」がかかっただけでも常民の埒外に置くという、昨日今日の話ではない「日本特有のメンタリティ」が、濃厚に影響している可能性が考えられます。
さらに、こうした伏流水のような差別意識は、いまだ容疑段階にある収監者に対するありとあらゆる処遇に通底していることを、2018~19年にかけて、ゴーン氏自身が骨身に沁みて痛感したであろうことが、全く想像に難くありません。
パンツの中まで改められる?
あえて他の記事が触れないような点から検討するなら、ゴーン氏は「パンツの中まで改められた」可能性があると私は考えます。
仮にゴーン氏が、西欧先進国の司法制度を前提とする常識を持っていた場合、日本の拘置所や留置場、刑務所などでの「容疑者」に対する取り扱いは、人間としての最低限の品位を認めない、いわば常民の埒外である「罪人」への差別に満ちたものと映ったこと、これは間違いないと思います。
具体的には施設によって詳細は異なると思いますが、東京地検特捜部によって逮捕され、小菅の東京拘置所に収監されたゴーン氏は、まず写真撮影と指紋採取など、拒否することができない手続きを踏まされたことでしょう。
次いで、入所に当たっては身体検査を受けたはずで、ここでは「自殺の予防と収監者の安全確保のため」などとして、衣服はすべて改められ、ほぼ半裸の状況で「口の中」も改められる。
さらにはパンツの中までチェックされるといった境遇にゴーン氏が直面した可能性があると。これは彼が収監されたと聞いた直後、反射的に感じました。
私には「オウム真理教事件」に関連して、1999年から2018年までまる19年間、東京拘置所に定期的に通い続けた長い年月があります。
その内聞の、正確なところは分かりませんが、入所者がどのようなプロセスを経るか、については二人称から直接、様々な消息を聞いてきました。
またオウム裁判進捗の過程で、刑法の團藤重光先生とご一緒するようになり、2005年以降は秘書役のような形でお手伝いもさせていただき、日本の「矯正施設」のもつ様々な問題を基礎的なレベルから認識するようになりました。
共著「反骨のコツ」を上梓させていただく頃には、大まかにこの種の問題が発生したとき、團藤先生ならどのようにおっしゃるか、見当はつくようになっていました。
そこで、語り下ろしを校正してメディアに発表する原稿のドラフトなども書かせていただくようになった。
そうした観点から見て、あくまで私の文責で記しますが、ゴーン事件での日本司法、とりわけ日本検察の失態は「人間の主体性を軽んじ、文化としての法治をないがしろにする、とんでもないこと」と、團藤先生なら、まず間違いなくおっしゃったように思います。
実際、留置場や拘置所では「容疑者」に「観念」させるべく、自尊心を踏みにじるような行為を意図的に行わせるケースが少なくない。というか非常に多いといった詳細は、佐藤優さんを筆頭に、実際に「矯正施設」の現実を知る方々が、あちこちに記していると思います。
日本では、明治41(1908)年に「世界で初めて」作られたとうい「監獄法」が2006年まで残存していました。
これが「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」(https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=417AC0000000050)に改められた時期、私は團藤先生のお手伝いをしていましたので、改正されたといっても精神風土を含め、明治41年以来の慣習を引きずっている日本の現実、例えば「代用監獄」の問題(https://www.nichibenren.or.jp/activity/criminal/detention/haishi.html)などを知るようになりました。
ゴーン氏が容疑者として、あるいは被告人としてどのような局面に遭遇したか、その詳細はいまだ細かく報じられていませんが、一切読むことのできない日本語の書類/調書に署名を求められて拒否、といった経緯を漏れ聞くにつけ、国際社会では全く通用しない代物であったことは、察するに難くありません。
フランスでは保険加入などでも身体検査は素っ裸で徹底している、といった話も耳にしましたし、ゴーン氏の軍歴などを確認していませんが、素っ裸で検査を受けることそのものへのナイーブなアレルギーは少なかったかもしれません。
しかし「完全武装解除」を意味する素っ裸の状態のまま、口の中を改めるに始まって、佐藤優さんが体験されたような「人間としてのプライドをへし折る」ような真似をさせられていたとしたら、「・・・こんなとんでもない野蛮な国のルールに付き合っていたら、とんでもないことにさせられてしまう・・・」と心を決して、全く不思議ではない。
事実そのような意味内容をベイルートからの第一声からゴーン氏は発し続けています。
国内では「保釈の取り消し」「15億円没収」その他、様々な報道がなされているのに加え「この問題は大したことではない」式の識者のコメントも目にしましたが、ポジショントークというべきでしょう。
日本の刑法もまた。幾多の改正を経たとはいえ、大枠は明治40年、1907年に定められた「法律第45号」が、113年を経ていまだに現行法として有効です。
1945年以降の欧州の観点からは、あり得ない非人間的な内容が、いまだ多々残されているのも、團藤先生、また欧州出身のカトリック神父で法律学者であったホセ・ヨンパルト先生から伺ってきました。
「ゴーン出国問題」はおよそ軽く考えてよい問題ではなく、取り扱いを誤ると、国際社会から日本の法治の信用を完全に失いかねない極めて危険な、デリケートな問題であるのは間違いありません。
「ゴーン出国問題」はおよそ軽く考えてよい問題ではなく、取り扱いを誤ると、国際社会から日本の法治の信用を完全に失いかねない極めて危険な、デリケートな問題であるのは間違いありません。
事態の進展を見つつ、多くの報道と異なる角度から、引き続き検討したいと思います。
(つづく)
(つづく)