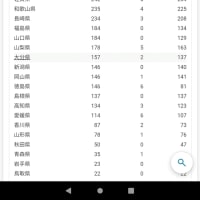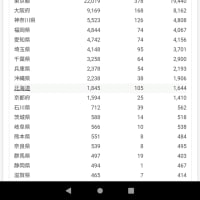音楽家の善意を悪用、一線を越えた偽ベートーベン
あまりに気の毒な当代一流の音楽家・新垣隆氏(2)
2014.02.12(水) 伊東 乾 (作曲家=指揮者 ベルリン・ラオムムジーク・コレギウム芸術監督)
私が「偽ベートーベン」の顔写真を初めて目にしたのは楽器店のCD売り場だったように記憶しています(私は通常ベートーヴェンと表記しますが、偽者にはベートーベンと表記することにしています。前回の記事はこちら)。
CD売り場に置かれた宣材には、よく知られたベートーヴェンの髪形と表情に似せたこの人物が顔にドーランを塗り、青白い撮影用の照明(「月光」でもイメージしたのでしょうか?)を当てられて写っていました。
服装はヘビーメタルのロックシンガーが着るような王子様風?の衣装と見えましたが、今考えると18世紀末のベートーヴェンの時代を「イメージ」したのかもしれません。
何であれ、一目見て「芸能系の売り出し」が明らかで、まともな作曲家がすることではありません。率直に、亡くなった武満徹さんなどは、相当に自己演出のある方だったと思いますが、さすがにメークして宣材写真を撮らせたりはしなかった。
三善晃でも林光でも松村禎三でも誰でも、普通の作曲家は普通の服装で普通に写った写真しか出しません。だって顔で音楽するわけではないのだから、当然です。
同時に記されていたプロフィールは、まともな音楽家が見れば直ちにウソと分かる自己演出過剰な作文でした。
これは芸能プロダクションが入った売り出し商品で、オーケストレーションなどスタッフライターが入っているに違いない、と3秒後に判断しましたので、それきりです。まともな音楽家で、この人を相手にする人がいるとは、正直思われません。
が、実際には、彼を持ち上げる人が業界にもチョコチョコいるらしい。そういう方に、何も「筆を折れ」などと乱暴なことは申しません。ただ、どうか一度ペンを走らせる手を休め、胸に手を当てるなどして、しばらく考えてみるクールダウンの時間を持たれてもよろしいのではないでしょうか?
私にはこの世界の兄貴分に当たる指揮者の大野和士さんも同様の指摘をしておられ、心強い限りと思います。持ち込みでセールスがあっても、きちんと真贋を見分けたうえで、推すものをしっかり推して頂きたいと思います。
“本人自演の再現ドラマ”
「惚れた目で見りゃ あばたもえくぼ」などと言いますが、何をどう勘違いされたのか、いま見ると、「偽ベートーベン」のテレビ番組は、バラエティなどでよく使われる「再現ドラマ」のような演技を本人が随所でしているのが分かります。
この際、私は番組制作にも関わってきたので意地悪く見つけてしまうのですが「カメラワークのある画像」が目立ちます。どういうことかと言うと、リハーサルをしているということです。
ニュースや、正常なNHKスペシャルなどで「作曲家の自宅探訪」となると、ドキュメンタリー・ノンフィクションの絵づらになりますが“本人自演の再現ドラマ”では、苦しんでいるような場面が綺麗な画角で撮られている。
分かる人は100%分かる、相当気持ちの悪い画像ですが、どうしてプロがチェックするはずの放送局でこういうものが通用したのか、率直に不思議に思います。被曝2世、障害といった言葉が、多くの人を遠慮させでもしたのでしょうか?
番組制作のプロセスを知らない多くの視聴者が騙されるのは、仕方がないことかもしれません。
1つの可能性として、先ほども触れた「あばたもえくぼ」の錯覚があったのかもしれません。また、相当多くの触れ込みつき情報ではありました。心理学には「教唆の効果」という言葉もあります。
豊田亨死刑囚について書いた『さよなら、サイレント・ネイビー』をはじめ、今までいろいろなところで指摘してきたことですが、自分が「好き」と思ったものに対しては、多くの人が感情的にほかの目で見ることができなくなり、極端な反応を示しやすい。
少なくとも音楽のプロは一番こういうことに気をつけねばならないポイントです。どんなに入神の演奏中でも、頭上3メートルには全体を冷静に見つめているもう1人の自分が必要不可欠、というのは私たちクラシックの音楽家がトレーニングで身につける大切な能力の1つです。
「ファンになったら何でも好き、何をやっても素晴らしい」みたいな裸の王様状態が、今回の騒ぎの背景に存在しています。
もう1つ、前回、急いで入稿した中で「あまちゃん」に言及しておきました。最近テレビから発信して国民的な広がりを見せた劇伴(ドラマの伴奏音楽)の例として、ある意味安心して挙げられるものとして選びました。
「あまちゃん」の音楽は大友良英さんというミュージシャンが担当しています。この大友さんが、新垣隆君と並んで作品を委嘱される、アヴァンギャルドの即興演奏家であるのを、テレビを視聴されるどれくらいの方がご存じでしょうか?
ここに、作曲家の高橋悠治さんたちが演奏する「糸」というグループのCDのリンクを張っておきましょう。この中に、作品を委嘱された作曲家として大友さんのお名前も新垣君の名も並んでいるのが分かると思います。
新垣君は「あまちゃん」の作曲家と並んで、新作を委嘱される、第一線のアーチストであることを、念頭に置いてください。彼は本来、おかしなアマチュアのゴーストライターなどさせられるような音楽家ではありません。
同時に、大友良英さんが、新垣君が自分の名で発表する「本流」の作品と並んで新作を委嘱される、前衛のフィールドで長年評価の高いミュージシャンであることも、お分かりいただけると思います。
私はこういう30年来の大友さんの活動の方が好きだし、そちらでは多くの刺激を受けてきました。たぶん大友さんは即興演奏やノイズミュージックの作品と「あまちゃん」の音楽を区別するような話し方はしないと思います。ジャンルの持つ柔軟性があるでしょう。
私もまた、テレビや商用の音楽だからといって、値引きをするようなことは一切しません。仕事は注文をいただいてするものですが、あらゆる可能性を念頭に私の方からも施主さんにボールを投げ返し、納得のいくものを作ります。
前衛のミュージシャンでもある大友良英さんは、多くの方がテレビで親しんだ範囲をはるかに超えて、多くの可能性を持った素晴らしいアーチストです。
いまから27年前、私は武満徹監修の季刊誌「ミュージック・トゥデイ・クオータリー」の創刊に参加して、当時はまだ20代だった大友さんを、巻上公一さんやジョン・ゾーンなどと共にフォーカスして取り上げたことがあります。
当時の大友さんはかなり先鋭的な意識を持った即興演奏のギタリストで、端的に言えば、作曲家・新垣隆君が自分の名前で展開する作品群にも通じる、鋭い切れ味を持つ前衛でした。
一昨年の大河ドラマが(やはり同門の先輩である)独自の活動で知られる作曲家・吉松隆さんの起用で、「NHKのドラマも最近なかなか頑張ってるな」と思っていたところ、朝の連ドラで大友良英とあり、期待しました。
実際のオンエアは、私たちのようにこの仕事をする人間としては安心して見ていられる作りでもっと冒険してくれてもよいのに、と思ったのは正直なところです。私は、敬意や愛情を感じない音楽には基本、言及しません。
例えば「偽ベートーべン」は名を記す気にもなりませんし、率直に記しますが日本のクラシック周りには代作の商慣習があり、ずっとそれを繰り返す人々の名もここに記したくありません。
大友さんには次に手がける劇伴、もっと刺激的な仕事をしてほしいなと思います。また、当然ながら、新垣君にも、こんなことでめげないで彼本来の音楽で大いに頑張ってほしいし、私自身も彼が落ち着いたら小さなものからと思いますが仕事を頼むつもりです。
当然ながら彼自身が自分の名で展開する音楽を依頼します。そういうエールの気持ちを含め、同じCDにカップリングされている大友さんと新垣君の例を挙げさせてもらいました。
新垣君が巻き込まれていく経緯
あれは確か1990年頃だったと思います。現在私の研究室がある東京都文京区内のキャンパスの目の前にあるキリスト教会で「冬の劇場」と銘打つ、若い作曲家グループの同人演奏会シリーズが開かれました。
ゲストをフィーチャーしており、作曲家・ピアニストの高橋悠治さんも参加しておられたこの「冬の劇場」の中心メンバーとして、当時は20歳前後だったと思いますが、新垣隆君を知り、音楽家・作曲家としての能力と資質も合わせて認識しました。
新垣君の「本流」の仕事は、米国のアーチストであるジョン・ケージやアルゼンチンの作曲家マウリシオ・カーゲルなどに影響を受けたと思える、偶然性やシアトリカルな要素にも開かれたアナーキーなユーモアを伴う独特のものです。
即興演奏やノイズミュージシャンとしての大友良英さんとの近親性は、同じCDにカップリングの例で先ほどお話ししました。新垣君の師匠・中川俊郎さんなど先輩作曲家の影響も大きいでしょう。
さて週刊文春2月13日号の記事では「不協和音」「現代音楽」などと、何となく皆がイメージしやすそうなストーリーが書かれていましたが、新垣君本来の仕事のいくつかは、すでに音楽とは理解されず、不条理演劇のように見る人があるかもしれない。そこで観客席から少なからず笑いが出ることもあったりします。
ほとんど「非音楽的」「反音楽的」と言うべき音楽のアナーキスト、新垣隆君は、古典的な音楽の書法、ピアノの演奏、ソルフェージュなど音楽全体の基礎に、彼が勤務する桐朋学園大学の全歴史の中でもたぶん数番目に入る、超優秀な能力を持っています。
そして、それらをほとんど一切使わない、極北のような独自の分野で、たわむことのない挑戦を続けてきた本物の芸術家です。
そんな彼が、ほかにも多数受けてきたであろう依頼仕事の1つとして「偽ベートーベン」から最初の依頼を受けたのは前回も書いた通り1996年だったと文春記事は伝えます。
新垣君自身、「九六年に私が最初に作った映画『秋桜』のテーマ曲は(偽ベートーベン)が制作予算を無視して約二百万円もの自腹を切り、私が大学で集めた学生オーケストラに演奏させて録音しました」(週刊文春)と述べています。
さてこの文春の記事では場所が飛んでいて、統一した印象を持ちにくいですが、新垣君がテープに録音された断片素材を提示されて「オーケストラ用の楽曲」として仕上げてほしいと依頼され、その結果生まれたのが『秋桜』という映画の音楽だということになります。
最初に新垣君が受けたのは「断片から楽曲を合成してほしい」という依頼で、決して「ゴーストライター」ではないことを、改めて確認しておきましょう。
この依頼に答え、受験その他で問われる基礎的な能力の応用だけで、新垣君によれば「息抜き」程度に趣味よくまとめた気軽な調性音楽の譜面ができたとき、
「この作品はぼくの名前で発表したい。君の名前は演奏家としてクレジットする・・・」
と、後出しじゃんけんで偽ベートーベンが言ったとき、同時に彼は約200万円「もの」自腹を切り(「もの」は新垣君の表現)、新垣君に集めてもらったオーケストラメンバーでの演奏、録音をした。
この熱意や、大枚のお金を負担しているという事実に、気の優しい新垣君が押されて、これをのんでしまったのが、最初の間違いだったと思います。
多くの人はこの記事を読んで気にもとめないと思いますが、オーケストラ曲は作曲家が総譜を書くだけでは演奏などできません。実際にはヴァイオリンならヴァイオリン、フルートならフルートの奏者がそれを読んで演奏する「パート譜」を作らなければなりません。
こうした写譜の作業も、まず間違いなく新垣君が仲間に頼んで手伝ってもらったと思われます。なぜなら偽ベートーベンは写譜ができないし、プロの写譜屋さんに発注すると、あっというまに数十万円の経費がかかってしまうので・・・。
元の楽曲合成・オーケストレーションの依頼は数万円とのことでしたが、新垣君としては、もう1つ、予算200万円強のこの演奏依頼は、彼を通して仲間や後輩たちに仕事を発生させるものにもなっている、こういう細かな現実に目をとめていただきたいのです。もしかすると写譜でも(安価と思いますが)謝礼が発生したかもしれません。
本当に善意の音楽家である新垣君としては、「自分にとってはどうという作業でもない、この気軽な調性音楽のスコア書きで、200万円ものお金を使って、しかも友達に演奏の仕事も作り出してくれているのだから、この譜面に自分の名前なんか出さなくてもいいや、アシスタントで縁の下の力持ちに徹してあげてもぜんぜんかまわない・・・」といった感想を持った可能性が高いと思います。
どうせ映画がヒットするとは思っていなかった新垣君は、ナイーブに「チーム仕事の中で黒子に徹してあげても惜しくない」と思ったと察しがつきます。
====ところがここから先、偽ベートーベンは、こうした新垣君ののんびりと牧歌的な想像を絶した行動を取り始めます。これを自作と称して「別の映画会社、ゲーム会社、テレビ局等」(文春ママ)あちこちに売り込み、偽って仕事を拡大させていきます。
==この「偽計業務」は、明らかに新垣君の事前の想像を絶するものでした。==3年後の1999年にはゲーム「鬼武者」のテーマ曲として、尺八その他の邦楽器を含む203人編成のオーケストラを編成、演奏、録音、記者発表などを行っています。
この音楽をちらと聴きましたが、私たち仕事でやっている者には、観光絵葉書に出てくる“典型的日本趣味”を増幅したような代物で、新垣君としても、やや露悪趣味的に楽しみながら、この譜面を作ったのではないか、などとも想像します。
あまりにも典型的な「ザ・日本」、自分の名を冠して「作品」などとは、私ならとても言う気にはなりません。
このときも、203人から成るオーケストラを編成、パート譜を作り、練習場の手配など何から何まで、音楽制作は新垣君がもっぱら担当していたことに注意していただきたいのです。新垣君は簡単に、
「(偽ベートーベン)は楽譜が読めないので、指揮をしたのは私ともう一人の副指揮者です」
とだけ、言葉少なに語っていますが、あらゆる音楽雑務はもっぱら真面目で能力の高い新垣君が担当しているわけです。==
「偽ベートーベン」は派手なPRで予算をぶん取ってくるなど音楽以外のことしかしていません。すべての、きちんとした音楽作りは新垣君をプロデューサーとして進められました。そして、その成果だけを「偽ベートーベン」が、すべて自分の仕事であると称してぶん取っていることが分かります。
つまり、原譜の作成にとどまらず、新垣君が善意で尽力した音楽家としての仕事を、二重三重に「偽ベートーベン」は詐取しているわけです。そして、それをどう使うか、「偽ベートーベン」は一切、新垣君に相談などしていない。
善意の新垣君は、純然と匿名のスタッフ、アシスタントとして頑張ろうと思った。この時点ではゴーストライターとも思っていなかったし、単にスタッフの1人として音楽のほぼすべてにフェアプレーで尽くした。一切の共謀性などはありません。
今回の件で「偽ベートーベンがプロデューサー」などと書いてあるものを見ますが、仕事の実情とかけ離れた表現と言わねばなりません。
ここまで、初期の音楽プロデュースをしているのはすべて新垣君であって、偽ベートーベンはブローカー以下の働きしかしていません。自作と詐称してお金を持ってくる口利き営業より音楽寄りのすべてのプロダクションは、新垣君が担当しています。
かつ、これはしょせん(という表現を嫌う人がいるのは分かりますが、私たち職業人の正直な感想としてはしょせん)ゲームの音楽で、それをまとめた「交響組曲」に、自分の名前をクレジットしようなんて、職業古典音楽側の人間はほとんど考えません。
まして新垣君は(一種、往年のデヴィッド・チュードアを髣髴させるような)極北の音楽アナーキストとでも言うような前衛に位置するアーチストで、この譜面賃仕事、また皆に演奏の仕事もできたプロジェクトで、自分の著作権など主張しようとは全く考えていなかった。
私たちの世界で言う、いわゆる「買い取り」仕事として、納品しておしまい(この場合は譜面の納付と、演奏の完了)と自覚して、淡々と誠実に仕事した。そこまでのことに過ぎません。
で、いったい誰がその後を、想像するでしょう?
この、ヒットしたゲーム音楽「鬼武者」の作曲者が「聴力を失った孤高の天才作曲家」である、と自称して、あろうことか海外にまで売り込み、米国「TIME」紙(2001年9月15日号)に「現代のベートーベン」などとして紹介されることになる、などと。
こうした偽計業務、つまり「詐欺」の本体は、もっぱら偽ベートーベン側が考え、実施したもので、善意で裏方に徹することにした新垣君は、その都度「買い取り」譜面を提供した後、図に乗り調子に乗った「偽ベートーベン」の三百代言を、せいぜいが「すごいことをするなぁ、と私は驚くばかり」、その実大半は知らずに過ごしていたのにほかなりません。
海外でのウソ、フェイクがまかり通ってしまうと偽ベートーベンは「将来はハリウッド映画の音楽を作る」「アカデミー賞を取る」などと、調子のつき方が加速していきます。
これを、完全な音楽テクニックとアナーキーな前衛の意識と2つながらに持つ新垣君は、どのように見つめていたのでしょうか?
ともあれ、ここまでは「グループワークに善意の買い取り納品」で応じていた新垣君だったと思われます。
ところが、2001年になって、これまでとやや意味合いが異なる次の相談が持ちかけられたと文春記事は記します。
「現代典礼」と名づけられた「交響曲」を代作してほしいという依頼で、このあたりから新垣君の「ゴーストライター」としての役割は変質し始めたように思われます。
(つづく)
元記事
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/39908