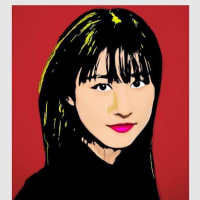「しばらくは派手なアーティスト活動を止めて“人間活動”に専念したい」と宣言してから早6年。フランス語で“幻”や“気配”を意味する言葉を冠した自身6枚目は、2008年の『HEART STATION』以来約8年ぶりに放たれるフル・アルバム。待ち侘びたファンも多く、国内のチャートはもちろん、全米iTunesチャートでも3位を記録するなど、彼女のカムバック作は高く評価されているようだ。
ただ、誤解を恐れずに言えば、個人的には非常に落胆してしまったというのが本音。これまでのアルバムのなかでは(Utada名義の『エキソドス』『ディス・イズ・ザ・ワン』を除いて)最もインパクトの薄い印象となってしまった。
まず、アルバムに先行してNHK連続テレビ小説『とと姉ちゃん』主題歌に起用されていた「花束を君に」が耳に入ってきた時に、あまりにも淀みのない純朴過ぎる作風に正直不安が過ぎった。「この曲はタイアップありきだろうから」と問い質す自分もいた。咄嗟に前作『HEART STATION』に(ボーナストラック扱いではなく)童謡風の「ぼくはくま」が収録されていたことに違和感を抱えていた時を思い出していた。
次に、すでに映画『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』テーマ・ソングとして2012年12月にリリースされた「桜流し」が収録されることも分かったが、この手のメランコリックなバラードにはどうも食指が動かない性分もあって、当初過ぎった不安を払拭するどころか増殖させてしまうことにもなった。
そして、ついに対面した復帰作。冒頭の「道」はリード曲で自身出演のCMソングにも起用されていたが、“消えない星が私の胸に輝き出す”などのフレーズから察するに、おそらく母・藤圭子を意識して作ったと思われる楽曲。宇多田ヒカルも妻、母となり、自身の母である藤圭子をいつも以上に感じたのだろう。心の内に浮かんでは消える葛藤や自問自答を、シリアスなテンションではなくあくまでもポップ・ソングとして描いたのが素晴らしい。
そう思えたのも束の間、次の「俺の彼女」で一気にトーンダウン。男と女のそれぞれの目線から本当に触れ合うべきものについて語った歌だが、石原裕次郎の「嵐を呼ぶ男」風のやさぐれ具合での歌唱とメロディは古臭いヤンキー歌謡にも思えるほど。
「花束を君に」に続く椎名林檎を迎えての「二時間だけのバカンス」は、スタンダード・ジャズ・ヴォーカル曲にポップなメロディを上乗せしたような宇多田らしい楽曲なのだが、どうも椎名林檎との相性が良くない。宇多田自身が詞曲を手掛けているが、椎名の個性も強すぎて、宇多田のパートと椎名のパートが綱を弾き合っているような“ブレ”を感じて仕方ないのだ。これは椎名が悪いということではなく、それぞれがユニークなオリジナリティを持つ歌い手であることは重々承知だが、如何せんそれぞれの個性が強く、それが仇になったよう。それぞれ単体で食すと大変高級で美味なのに、中和点を考えずにミックスしたら、味の濃さがぶつかり合い美味が相殺されてしまったような……とでもいったらいいだろうか。
瑞々しい弦が背後で鳴る「人魚」は特にアクがあるわけでもなく、「花束を君に」と同時期に配信リリースされた「真夏の通り雨」はテンポは違えど「誰かの願いが叶うころ」や「Letters」路線の曲風ということで安定感こそあるが、目新しさはなし。また、ストレートでシンプルな表現で注目されるラッパーのKOHHをフィーチャーした「忘却」だが、これはやや食べ飽きた感もある鬱蒼としたムードもそうだが、なよなよと引きずるように綴るKOHHのフロウと神々しさも窺わせる宇多田のファルセットの組み合わせがどうにも受け入れられない。
といったように、ことごとく自分の期待を削いでしまう要素ばかりが目についてしまい、素朴ながらも小躍りするグルーヴを持つ「ともだち」くらいしか一聴して耳につくものがなかった。
しかしながら、これだけ言っておきながらも誤解して欲しくないのは、このアルバムが駄作であるかといったら、それは断じて違うということだ。元来備えていた表現の才能が人間活動に専念する期間を経たことでいっそう成熟度を高めていて、内面からほとばしる人間の欲求や虚栄心、つまるところ愛への渇望を激しい抑揚を用いずとも描き上げる手腕は見事というしかないし、普通ならダサく聴こえてしまって音に寄せて言葉を選びがちな日常で使う何気ない言葉も、彼女が持つ独特の譜割り感覚でサラッと乗り切ってしまう術がさらなる向上を果たしている。心身共に芳しく熟して、表現方法にさらなる潤いをもたらしたようでもある。“幻影”といった意味に近しいタイトルながら、しっかりと日常やヒューマニズムを捉えているところも彼女らしい。そして、奇を衒うのではなく、しっかりとポップスとしての瑞々しさを満たすような作りに徹しているところは、甘美な果汁が凝縮された豊かな果実といっていい。

では、なぜこのアルバムに落胆したのか。それはおそらく、自分が彼女にR&Bなどの黒い要素を包含し継承してくれる数少ないシンガーとして見ていたからかもしれない。趣向としてオーセンティックなバラードなどにそれほど心打たれないというのも一つある。といっても、「Movin' on without you」や「traveling」といったタイプのアッパー曲がなければダメなんてこともないが、これまでの宇多田の楽曲のなかで好きな曲を見ていくと、ジャム&ルイス・プロデュースの「Addicted To You」「Wait&See ~リスク~」や“ダークチャイルド”ことロドニー・ジャーキンス・アレンジの「タイム・リミット」あたりを頂点としたグルーヴ溢れる楽曲を好んでいることも大きい。
さらには、無意識のうちに宇多田ヒカルに求めていた要素が、今作においては思う以上に少なかったことか。シンガーにはそれぞれ特色とそれぞれに求めるもの(求めてしまっているといった方が正しいか)があると思うが、たとえば、ジャパニーズR&Bディーヴァ・ブームにあったほぼ同時期にデビューしたMISIAは、その圧倒的な声量と声圧による歌唱力が随一だし、途中からR&Bやクラブ路線へ推移した安室奈美恵は、ピッチや声量といったものには群を抜くものはないが、自身の歌声を前面に強調するのではなくビートやトラックと一体化しながらどんなテイストの楽曲でも安室色に染め上げてしまうところに最大の魅力がある。
では、宇多田は何か。ライヴで圧倒させるほどの声圧やヴォーカルパワーはないが、さまざまな音楽的要素や文学的要素を独自の視点で選択するセンス、さらに元の素材が想像出来ないような彩り豊かな装飾で宇多田カラーに染め上げてしまうバランス感覚は見事というほかになく、他の追随を許さないと言っていい。
その染め上げられたカラーに、これまで有していた“黒い”要素やグルーヴが徐々に希薄になってきていて、今作『Fantome』でもそれを実感してしまったからなのだと思う。
当初、R&Bを標榜していた女性シンガーは数多くいるが、殆どがことごとく漆黒度を薄めていってしまうなかで、宇多田にはその歯止めを期待していたのかもしれない。前述のMISIAも現在はオーセンティックなポップ・シンガーとなっているし、安室は時流を捉えてダンス/クラブ色へと移行している。もはやジャンル云々ではなく、“宇多田ヒカル”の作品として捉えるべきなのだろう。これまでそういう見方をしてこなかったことこそが“落胆”を生んでしまったのだと。
彼女の成熟の度合いが高まるにつれて、作品も即効性よりも定着性の強度が上がっている“スルメ”的なアルバムとなっているかもしれない。まだ、自分としては“一聴”したあたりを越えるほど聴いていないこともあり、いましばらく彼女の楽曲に触れていきたいと思う。

◇◇◇
宇多田ヒカル『Fantôme』(2016/9/28)
01 道
02 俺の彼女
03 花束を君に
04 二時間だけのバカンス featuring 椎名林檎
05 人魚
06 ともだち with 小袋成彬
07 真夏の通り雨
08 荒野の狼
09 忘却 featuring KOHH
10 人生最高の日
11 桜流し
◇◇◇