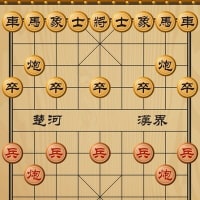シャンチー(中国象棋)基本図書紹介(4)
今回は残局に関する書籍の紹介です。今回もネット書店『書虫』の目録から入手可能なものを紹介します。
注文は『書虫』または内山書店(tel03-3294-0671)
【殺法】
日本シャンチー協会編『殺法入門』などの入門書で基本的な殺法を学んだ人が、次の段階で取り組む本を紹介します。
◆象棋基本殺法 趙慶閣・楊典 成都時代 2013.3
30種の殺法ごとに計300例の局例(182の例題と118の練習問題)に加えて、いくつかの殺法を組み合わせた15局の実戦例を収める。例題の中にも比較的新しい実戦例を取り入れており、現時点で初級者用にどの一冊と問われたらまずこの本を薦めたい。

象棋基本殺法
◆象棋殺法習題集(上)・(下) 汪霞萍等 江蘇科学技術 2010.7-8
上巻には1歩殺から3歩殺まで、下巻には4歩殺から6歩殺まで、それぞれ400題ずつ計800題が殺法の種類ごとに収録されている。著者は徐天紅氏の夫人で1988年中国全国女子選手権準優勝者。
◆象棋基本殺法宝典 趙力・趙紅 山西科学技術 2012.9
50種の殺法ごとに計550題を収める。新書版サイズでコンパクトだが、やや字が小さい。通勤・通学時に使うとよい。
◆象棋絶殺実戦精選 傅宝勝・朱兆毅 安徽科学技術 2008.1
実戦から採った実例330を33の殺法ごとに分類して収める。巻末に古譜残局120例を付す。
◆適情雅趣象棋譜 河南科学技術 2009.11
明代の古譜『適情雅趣』(1570年)を整理したもの。残局550例を収める。過去にいくつかの出版社から出ているが、現在目録で検索できるのは河南科技版のみ。『橘中秘』、『梅花譜』とともにシャンチーを志す人なら学んでおきたい古譜。『適情雅趣』は、中国のデータベースサイト『東萍象棋网』にも収録されている。
◆中国象棋棄子攻殺法 鄭徳豊 人民体育 1966.3
現在は入手困難だが、これも『東萍象棋网』に収録されている。「棄子」(コマを捨てる)による殺の例80局を収める。初版以来856,000冊が印刷され、75ページの薄い本だが初級者にはお薦め。
【実用残局】
実用残局は、一方に1~3枚の攻めゴマが残り、もう一方の子力がそれより劣る場合に、勝ちになるか和になるか(そしてどのようにして勝つか、和にするか)が定式化されたものです。
実用残局は数学における公式、物理における定理ともいうべきもので、シャンチーの要素の中でも最も科学的な部分といわれています。派手な殺法に比べて地味なので(フィギュアスケートで1990年まで行われていたコンパルソリーにも似ています)、日本人できちんと勉強している人は少ないのですが、中国の小学生向けの教材を見ると、全120課のうち41課を実用残局に割いています。中国では小学生の段階でこうした基礎・基本を徹底的にたたきこんでいるのです。
「シャンチー基本図書紹介(1)」で紹介した入門書のうち、『怎様下象棋』(汪霞萍等 江蘇科学技術)、『教孩子学象棋(初級班)』(同編写組 北京体育大学)には、基本的な実用残局がいずれも約100例、また『象棋詞典』(屠景明等 上海文化 2009.4)には約200例が収められています。これらの数は初級レベルで学ぶべき実用残局の量的な水準を示すものです。その上のレベルでは、大著『象棋残局例典』(屠景明 上海文芸 1990.6)が、1018例の実用残局を収めますが、現在では入手困難です。現在入手可能なものでは次のものがあります。
◆梁大師講残局(上・下) 梁文斌 経済管理 2013.4
上下巻合わせて実用残局550例を収める。多くを実戦から採っている。著者の梁文斌は多くの名選手を育て「金牌教練」の名で知られる。

梁大師講残局
◆象棋実用残局宝典 趙力・趙紅 山西科学技術 2012.9
実用残局約400例を収める。上で挙げた『象棋基本殺法宝典』の姉妹編。
◆新中国60年象棋残局精選 石毅主編 人民体育 2012.7
実戦の残局から318例を収める。もともと実用残局は膨大な実戦例から帰納され定式化されたものだが、それがまた実戦に演繹された実例集というべきもの。
◆象棋実用残局第一集、第二集
書籍ではないがこれも『東萍象棋网』に収められている。実用残局を計600例収録。1958・61年に出版された屠景明の同名書をデータベース化したものと思われる。
今回は残局に関する書籍の紹介です。今回もネット書店『書虫』の目録から入手可能なものを紹介します。
注文は『書虫』または内山書店(tel03-3294-0671)
【殺法】
日本シャンチー協会編『殺法入門』などの入門書で基本的な殺法を学んだ人が、次の段階で取り組む本を紹介します。
◆象棋基本殺法 趙慶閣・楊典 成都時代 2013.3
30種の殺法ごとに計300例の局例(182の例題と118の練習問題)に加えて、いくつかの殺法を組み合わせた15局の実戦例を収める。例題の中にも比較的新しい実戦例を取り入れており、現時点で初級者用にどの一冊と問われたらまずこの本を薦めたい。

象棋基本殺法
◆象棋殺法習題集(上)・(下) 汪霞萍等 江蘇科学技術 2010.7-8
上巻には1歩殺から3歩殺まで、下巻には4歩殺から6歩殺まで、それぞれ400題ずつ計800題が殺法の種類ごとに収録されている。著者は徐天紅氏の夫人で1988年中国全国女子選手権準優勝者。
◆象棋基本殺法宝典 趙力・趙紅 山西科学技術 2012.9
50種の殺法ごとに計550題を収める。新書版サイズでコンパクトだが、やや字が小さい。通勤・通学時に使うとよい。
◆象棋絶殺実戦精選 傅宝勝・朱兆毅 安徽科学技術 2008.1
実戦から採った実例330を33の殺法ごとに分類して収める。巻末に古譜残局120例を付す。
◆適情雅趣象棋譜 河南科学技術 2009.11
明代の古譜『適情雅趣』(1570年)を整理したもの。残局550例を収める。過去にいくつかの出版社から出ているが、現在目録で検索できるのは河南科技版のみ。『橘中秘』、『梅花譜』とともにシャンチーを志す人なら学んでおきたい古譜。『適情雅趣』は、中国のデータベースサイト『東萍象棋网』にも収録されている。
◆中国象棋棄子攻殺法 鄭徳豊 人民体育 1966.3
現在は入手困難だが、これも『東萍象棋网』に収録されている。「棄子」(コマを捨てる)による殺の例80局を収める。初版以来856,000冊が印刷され、75ページの薄い本だが初級者にはお薦め。
【実用残局】
実用残局は、一方に1~3枚の攻めゴマが残り、もう一方の子力がそれより劣る場合に、勝ちになるか和になるか(そしてどのようにして勝つか、和にするか)が定式化されたものです。
実用残局は数学における公式、物理における定理ともいうべきもので、シャンチーの要素の中でも最も科学的な部分といわれています。派手な殺法に比べて地味なので(フィギュアスケートで1990年まで行われていたコンパルソリーにも似ています)、日本人できちんと勉強している人は少ないのですが、中国の小学生向けの教材を見ると、全120課のうち41課を実用残局に割いています。中国では小学生の段階でこうした基礎・基本を徹底的にたたきこんでいるのです。
「シャンチー基本図書紹介(1)」で紹介した入門書のうち、『怎様下象棋』(汪霞萍等 江蘇科学技術)、『教孩子学象棋(初級班)』(同編写組 北京体育大学)には、基本的な実用残局がいずれも約100例、また『象棋詞典』(屠景明等 上海文化 2009.4)には約200例が収められています。これらの数は初級レベルで学ぶべき実用残局の量的な水準を示すものです。その上のレベルでは、大著『象棋残局例典』(屠景明 上海文芸 1990.6)が、1018例の実用残局を収めますが、現在では入手困難です。現在入手可能なものでは次のものがあります。
◆梁大師講残局(上・下) 梁文斌 経済管理 2013.4
上下巻合わせて実用残局550例を収める。多くを実戦から採っている。著者の梁文斌は多くの名選手を育て「金牌教練」の名で知られる。

梁大師講残局
◆象棋実用残局宝典 趙力・趙紅 山西科学技術 2012.9
実用残局約400例を収める。上で挙げた『象棋基本殺法宝典』の姉妹編。
◆新中国60年象棋残局精選 石毅主編 人民体育 2012.7
実戦の残局から318例を収める。もともと実用残局は膨大な実戦例から帰納され定式化されたものだが、それがまた実戦に演繹された実例集というべきもの。
◆象棋実用残局第一集、第二集
書籍ではないがこれも『東萍象棋网』に収められている。実用残局を計600例収録。1958・61年に出版された屠景明の同名書をデータベース化したものと思われる。