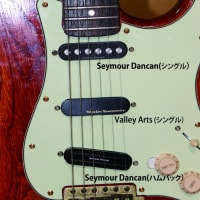2SK1530パワーアンプとの組み合わせということでは、もう一つの組み合わせが残っていた。
いただき物の バイポーラTRを終段に使った 安井式LIKEなアンプだ。局部帰還のNFだけしか
掛かっていないタイプだ。単体で鳴らすと、スッキリした歪の少ない音がする。低域はさすがに
TAD1601をドライブするには力不足な感じがしていたアンプだ。
金田式No.167風と 窪田式の2SK1530を使ったパワーアンプをそれぞれ BTL接続で低域に使う。
そして中高域を安井式LIKEなアンプを使ってみた。
果たして、出てきた音は、確かに歪感の少ない 素直な音だった。
これが、昨夜のことで、今日は、午後から来客があり、主にClassicを聴くとのこと。
なので、この構成で聴いてもらった。持参されたCDは、「Rosset Meyer Geiger Trio/What Happend」と
いうタイトルだった。ピアノTrioなので、私が普段聞いている New york Trioの構成に似ている。
録音も良くて、システムの弱点もさらけ出してくれる。
そう、聴き易いのだが、スピード感と力強さがない、と言ったところか。
山本 剛の MistyをLPでかけたら、全然 その雰囲気が出なかった。あのピアノの高域の カツーンという
刺激的な音が全く出ない。375+077の音がしない。 さすがにガッカリしたので、アンプを クリスキットに替えた。
アンプのゲインが違うので、バランスが崩れてしまったが、刺激的な中高音は 戻ってきた。
ただ、この組み合わせだと、2SK1530の立ち上がりの鈍さが出てきてしまう。
ということで、益々 2sk2554で作りなおす必要性を痛感した。
で、ちょっと試しに再度、中高域のアンプをEL-12ppに替えてみた。 なんだか、こちらの方が、JAZZに
限っては、雰囲気を持った音がする。なので、明日は昼間に オーケストラものを聴いてみることにしよう。