『夕食は、また適当に取りなさい』
ダイニングテーブルの上にあった母親の置き手紙に、今日もため息が出る。いつもこれだ。
冷蔵庫の中をあさり出すこの光景も、日常の出来事へとなっていった。昔はパンと残り物で凌いでいたが、ここ最近は作ることを覚えた。といっても大したものは作れない。自分の飢えさえ満たせばよいのだから。
父親は仕事が忙しく、「疲れた」といって休みの日でも相手にしてくれない。
両親が共働きで、兄弟がいない私はこの家で孤独を感じていた。
小さい時に私が寂しくならないようにと、くまのヌイグルミを買ってもらったことがあるが、話しかけてもなにも答えてくれない。腹話術でなにか言わせたらそれこそ寂しい。
それが十二才までの話だった。
十三才の夏。日曜日の昼間だというのに相変わらず家には誰もいなく、窓を開けて外ののどかな山間の風景を眺めていた。
私があまりにもぼーっとしていたので、訪問者に気づかなかった。その訪問者は開けっ放しの玄関から堂々と入り、私が食べ残したミートボールに狙いをつけていた。ダイニングテーブルへよじ登ろうとする物音でやっと気づいた。
「何しているのよ」
見つかって逃げるのかと思ったが、その茶色の猫は私の方を見て甘ったれた声を出してきた。
「分かったよ。あげる」
小さくカットして、与えてあげた。よほど空腹だったのか、体育会系を連想させるほど、あっという間にガッツリと食べてしまった。満足して出て行くことなく、私のそばに寄り添うように離れようとしなかった。
「もしかして、ひとりなの?」
勝手な想像に過ぎなかった。しかし、今この瞬間私と一緒にいてくれる存在。
「ねぇ、この猫。飼ってもいい?」
どう考えても迷い猫を飼って良いと言うと思えず、ダメもとで母親に頼み込んだ。
「好きにすれば?」
意外にもすんなり通って、その時は嬉しかった。
「それよりあなた。お隣の奥さんがね……」
よくわかった。私に興味がないって。
「ミミだけだよ。この家で私といてくれるのは」
ミミはありきたりな猫の鳴き声で返事をする。
それからずっと、ミミのことを弟のようにかわいがった。
寝るときはいつも一緒で、甘えるように向こうから私の布団に入ってきた。いつもミミの温もりを心地よく感じていた。
食事も私が作ってあげたものを、食べさせてあげていた。おいしそうに食べてくれて、作るのが楽しかった。
三年の月日が流れたある日。
「ミミー! ご飯だよ」
家じゅう叫んでみたが、反応がない。いつもだったら、臭いを嗅ぎつけてすぐ来るのに。ベッドの下や、山積みに置いておいた洗濯物の中。思い当たる所は探し回った。
家の周りもひととおり見てみたがいなかった。
「おなかがすいたら、帰ってくるでしょ」
その時は深刻に考えていなかった。だが、いくら待っても帰ってくることはなく、心配になってきた。
ミミが帰ってきたのは、この三日後。あまりにも変わり果てた姿に絶句した。見つけた人によれば、車か何かにひかれたんじゃないか、と言うが信じたくなかった。これがミミだってことも。
「また一人になる……」
これが嫌だったにも関わらず、部屋にこもるようになった。
ミミをひいた人が誰だったとしても、恨む気はなかった。それより、いなくなったことがショックだった。
両親が家からいなくなると、部屋から出て食べ物をあさる。外に出なくなったことを除けば、ミミが来る前と全く同じ生活になった。結局外に出ても同じことだし。
キッチンで昼食を物色していると、一匹の猫が入り込んできた。その猫があまりにもミミに毛並みやらが似ていた。
「ミミなの?!」
私の声に驚いて、テーブルのものを取り損ね、慌てて出て行ってしまった。すぐさま追いかけていった。
近くの雑木林に逃げていくところまでは、追うことができたが見失ってしまった。必死に捜索をしたが、日が暮れる一方だった。
「やっぱり、思い違いだったのかな……」
あきらめて帰ろうとあたりを見渡してみたら、全く見覚えのない場所に立っていた。
そこで助けてくれた彼女と、いい友達になれると思っていた。気持ちをわかってあげたかった。だから、この話をした。しかし、ガトーは納得する様子はなかった。
「そうだよね……違いすぎるよね。拾った猫と、実の弟じゃあ……」
≪ 第6話-[目次]-第8話 ≫
------------------------------
↓今後の展開に期待を込めて!

にほんブログ村
ダイニングテーブルの上にあった母親の置き手紙に、今日もため息が出る。いつもこれだ。
冷蔵庫の中をあさり出すこの光景も、日常の出来事へとなっていった。昔はパンと残り物で凌いでいたが、ここ最近は作ることを覚えた。といっても大したものは作れない。自分の飢えさえ満たせばよいのだから。
父親は仕事が忙しく、「疲れた」といって休みの日でも相手にしてくれない。
両親が共働きで、兄弟がいない私はこの家で孤独を感じていた。
小さい時に私が寂しくならないようにと、くまのヌイグルミを買ってもらったことがあるが、話しかけてもなにも答えてくれない。腹話術でなにか言わせたらそれこそ寂しい。
それが十二才までの話だった。
十三才の夏。日曜日の昼間だというのに相変わらず家には誰もいなく、窓を開けて外ののどかな山間の風景を眺めていた。
私があまりにもぼーっとしていたので、訪問者に気づかなかった。その訪問者は開けっ放しの玄関から堂々と入り、私が食べ残したミートボールに狙いをつけていた。ダイニングテーブルへよじ登ろうとする物音でやっと気づいた。
「何しているのよ」
見つかって逃げるのかと思ったが、その茶色の猫は私の方を見て甘ったれた声を出してきた。
「分かったよ。あげる」
小さくカットして、与えてあげた。よほど空腹だったのか、体育会系を連想させるほど、あっという間にガッツリと食べてしまった。満足して出て行くことなく、私のそばに寄り添うように離れようとしなかった。
「もしかして、ひとりなの?」
勝手な想像に過ぎなかった。しかし、今この瞬間私と一緒にいてくれる存在。
「ねぇ、この猫。飼ってもいい?」
どう考えても迷い猫を飼って良いと言うと思えず、ダメもとで母親に頼み込んだ。
「好きにすれば?」
意外にもすんなり通って、その時は嬉しかった。
「それよりあなた。お隣の奥さんがね……」
よくわかった。私に興味がないって。
「ミミだけだよ。この家で私といてくれるのは」
ミミはありきたりな猫の鳴き声で返事をする。
それからずっと、ミミのことを弟のようにかわいがった。
寝るときはいつも一緒で、甘えるように向こうから私の布団に入ってきた。いつもミミの温もりを心地よく感じていた。
食事も私が作ってあげたものを、食べさせてあげていた。おいしそうに食べてくれて、作るのが楽しかった。
三年の月日が流れたある日。
「ミミー! ご飯だよ」
家じゅう叫んでみたが、反応がない。いつもだったら、臭いを嗅ぎつけてすぐ来るのに。ベッドの下や、山積みに置いておいた洗濯物の中。思い当たる所は探し回った。
家の周りもひととおり見てみたがいなかった。
「おなかがすいたら、帰ってくるでしょ」
その時は深刻に考えていなかった。だが、いくら待っても帰ってくることはなく、心配になってきた。
ミミが帰ってきたのは、この三日後。あまりにも変わり果てた姿に絶句した。見つけた人によれば、車か何かにひかれたんじゃないか、と言うが信じたくなかった。これがミミだってことも。
「また一人になる……」
これが嫌だったにも関わらず、部屋にこもるようになった。
ミミをひいた人が誰だったとしても、恨む気はなかった。それより、いなくなったことがショックだった。
両親が家からいなくなると、部屋から出て食べ物をあさる。外に出なくなったことを除けば、ミミが来る前と全く同じ生活になった。結局外に出ても同じことだし。
キッチンで昼食を物色していると、一匹の猫が入り込んできた。その猫があまりにもミミに毛並みやらが似ていた。
「ミミなの?!」
私の声に驚いて、テーブルのものを取り損ね、慌てて出て行ってしまった。すぐさま追いかけていった。
近くの雑木林に逃げていくところまでは、追うことができたが見失ってしまった。必死に捜索をしたが、日が暮れる一方だった。
「やっぱり、思い違いだったのかな……」
あきらめて帰ろうとあたりを見渡してみたら、全く見覚えのない場所に立っていた。
そこで助けてくれた彼女と、いい友達になれると思っていた。気持ちをわかってあげたかった。だから、この話をした。しかし、ガトーは納得する様子はなかった。
「そうだよね……違いすぎるよね。拾った猫と、実の弟じゃあ……」
≪ 第6話-[目次]-第8話 ≫
------------------------------
↓今後の展開に期待を込めて!
にほんブログ村












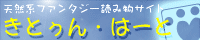
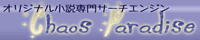






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます