先週、平成24年度台2回福島県ふるさと子ども夢学校推進協議会、子ども農村漁村交流プロジェクト勉強会に
参加させて頂きました。会場は郡山にあるビックパレットふくしま。
震災当時は2000人以上の避難者の方であふれていたこちらの会場を、震災以降初めて訪れました。
震災前に何度も訪れている会場にも関わらず、その施設に入った瞬間から、今までとは違う目線、違う視線で体
感している事に気づきました。駐車場から施設に歩くだけでも数分かかるような広大な敷地。そして入口から繋
がる広いロビー。広大な2階のエントラス。そして通路までゆとりある空間が広がっています。
あの時、避難場所となったこの施設に、着のみ着のままで避難された大勢の被災者がひしめき合うように寄り添
っていらしたあの姿が昨日の事のようにはっきりとした映像となってフラッシュバックしてくるのです。
避難されていた方の殆どが肩を落とし疲れはてたようにどっかりと地べたに座っていたあの光景が…。
その当時も震災直後もここを訪れた事など一度もないのに鮮明に覚えている事の不思議な感覚。
この記憶の映像がいつまで続くのかわかりませんが、頭の中でゆっくりと古い映写機のように回っているうちに
この記憶をきちんと記録としなければという想いをフロアに移る自分の影を見ながらぼんやりと考えました。
この日は大雪。浜通りも今年は珍しく雪が積もり「今年は寒いねぇ。」と、行きかう人びとの挨拶がわりとなっ
ていましたが、いやぁこの日の郡山は肌を突き刺すような冷たさ。吹き荒れる北風にも悲鳴をあげそうな雪模様。
浜通りとは大違いです。そんな事を感じるのは浜通りに生きる我らばかりなり?
 今回の勉強会では、平成16年10月に発生した
今回の勉強会では、平成16年10月に発生した
新潟県中越地震からの復興を体験
された子ども農村漁村交流プロジ
ェクト研究会法務安全対策部門会
議委員の佐藤春夫さん。
同教育部門会議委員の小椋唯一
さん。
新潟県小千谷市若栃の「わかとち未来会議」代表の細金剛さんから震災後の取組の講演がされました。
震災時多くの南相馬市民がお世話になった新潟県。その講演の中でも当時避難された南相馬市民の皆様の
様子が開間見え、震災から交流を続けている方からお聞きしていたお話しを思い出し、とても感慨深いも
のがありました。特に南相馬市下渋佐の皆さんが多く受入して頂いた若栃の「わかとち未来会議」の細金
さんのお話しにでてきた「南相馬食堂」のお話しはその方から以前聞いたことがあり、その「南相馬食堂」
を復活させようと細金さん達が奮闘したが残念ながら実現できなかったというお話しもそのままでした。
しかし、そこには食を通した交流も生まれていた事も確か。この震災が地域にもたらしたものは災害だけ
ではなく、震災で失ったものは大きかったけれどそこで誕生し育むものも与えてくれたのも事実。
「こんな大震災で繋がった仲間は生涯を通して付き合える大切な仲間だ」誰かが言ったそんな言葉が思い
だされます。いつか「南相馬食堂」再開させたいですよね。
ところで、震災前に行っていた子ども達の体験学習の推進、長期滞在体験プログラムの確保、受入体制を
整備し、未来を担う子どもたちの成長を手助けしながら豊かで夢のある未来へ誘う活動。
そこにたどり着くまでは決して簡単にはあきらめず福島独自のメッセージを発信し続ける必要がありそう
です。南相馬市では震災前に14軒の農家民宿が営業をしていました。震災直後は4軒に減少。現在は12
軒(小高区2件、鹿島区1軒は休業中。震災後に開業が3件)現在9軒が営業中。
2月には鹿島区の1軒。農家民宿「塔前の家」さんが再開します。

その農家民宿「塔目の家」の佐藤さんを含む10軒の農家民宿さん達は、センターの企画部会の中で「農家民宿
の集い」を開催し、不定期に各農家民宿を訪問し、お客様へおだしするお食事に関する細かな事から地域の情報
の事などジャンルを問わずおしゃべりしながらおもてなしの情報交換や確認を行っています。


この日は震災後開業された鹿島区北屋形の農家民宿「森林」さんのお宅に集合。賑やかにお話ししていま
した。最近、ご宿泊頂くボランティアさんの中には、親子でいらっしゃる方や相双地域で行われるイベン
トへ参加する為保護者や、引率の大人の方と参加する子ども達も結構増えてきています。
この地を訪れ震災の影響や原発事故の問題を親子で、時には先生と生徒で、大人と子供で直視し、農家民
宿に宿泊する事で夕飯時には当時の話や、復興へ向う現在の状況などの話しを聞く。
放射能は大丈夫か?との問題を考慮してもなお、この震災を学習として捉えようとする動きが増えてきて
いるのかもしれません。
翌日、勉強会に参加された皆様が南相馬市を視察に訪れました。前日の雪が残る南相馬市。郡山から普段
なら2時間ちょいの道を3時間以上かけてのご到着。待っていたのは、浜通りでは珍しい雪げしき。
語り部さんから震災のお話しを聞きながらの道中、放射線測定器を渡された参加者の中には、初めて手に
する方も多かったそうです。徐々に復旧が進んでいる小高区ですが、津波の後を隠すようにきれいな雪景
色が広がる中「さびついた車の残骸がねぇ…」と言葉を捜される参加者の方もいらっしゃいました。
南相馬市博物館では今日から「ふるさと小高」と題した特別展が、3月20日まで開かれます。館内の一
部には小高の古い町並みや住民の方の写真も展示されています。また、シアターでは震災前に完成した南
相馬市の地域紹介が上映され、震災前の小高区の様子も紹介されています。


>>南相馬市ふるさと回帰支/援センターHPへ
参加させて頂きました。会場は郡山にあるビックパレットふくしま。
震災当時は2000人以上の避難者の方であふれていたこちらの会場を、震災以降初めて訪れました。
震災前に何度も訪れている会場にも関わらず、その施設に入った瞬間から、今までとは違う目線、違う視線で体
感している事に気づきました。駐車場から施設に歩くだけでも数分かかるような広大な敷地。そして入口から繋
がる広いロビー。広大な2階のエントラス。そして通路までゆとりある空間が広がっています。
あの時、避難場所となったこの施設に、着のみ着のままで避難された大勢の被災者がひしめき合うように寄り添
っていらしたあの姿が昨日の事のようにはっきりとした映像となってフラッシュバックしてくるのです。
避難されていた方の殆どが肩を落とし疲れはてたようにどっかりと地べたに座っていたあの光景が…。
その当時も震災直後もここを訪れた事など一度もないのに鮮明に覚えている事の不思議な感覚。
この記憶の映像がいつまで続くのかわかりませんが、頭の中でゆっくりと古い映写機のように回っているうちに
この記憶をきちんと記録としなければという想いをフロアに移る自分の影を見ながらぼんやりと考えました。
この日は大雪。浜通りも今年は珍しく雪が積もり「今年は寒いねぇ。」と、行きかう人びとの挨拶がわりとなっ
ていましたが、いやぁこの日の郡山は肌を突き刺すような冷たさ。吹き荒れる北風にも悲鳴をあげそうな雪模様。
浜通りとは大違いです。そんな事を感じるのは浜通りに生きる我らばかりなり?
 今回の勉強会では、平成16年10月に発生した
今回の勉強会では、平成16年10月に発生した新潟県中越地震からの復興を体験
された子ども農村漁村交流プロジ
ェクト研究会法務安全対策部門会
議委員の佐藤春夫さん。
同教育部門会議委員の小椋唯一
さん。
新潟県小千谷市若栃の「わかとち未来会議」代表の細金剛さんから震災後の取組の講演がされました。
震災時多くの南相馬市民がお世話になった新潟県。その講演の中でも当時避難された南相馬市民の皆様の
様子が開間見え、震災から交流を続けている方からお聞きしていたお話しを思い出し、とても感慨深いも
のがありました。特に南相馬市下渋佐の皆さんが多く受入して頂いた若栃の「わかとち未来会議」の細金
さんのお話しにでてきた「南相馬食堂」のお話しはその方から以前聞いたことがあり、その「南相馬食堂」
を復活させようと細金さん達が奮闘したが残念ながら実現できなかったというお話しもそのままでした。
しかし、そこには食を通した交流も生まれていた事も確か。この震災が地域にもたらしたものは災害だけ
ではなく、震災で失ったものは大きかったけれどそこで誕生し育むものも与えてくれたのも事実。
「こんな大震災で繋がった仲間は生涯を通して付き合える大切な仲間だ」誰かが言ったそんな言葉が思い
だされます。いつか「南相馬食堂」再開させたいですよね。
ところで、震災前に行っていた子ども達の体験学習の推進、長期滞在体験プログラムの確保、受入体制を
整備し、未来を担う子どもたちの成長を手助けしながら豊かで夢のある未来へ誘う活動。
そこにたどり着くまでは決して簡単にはあきらめず福島独自のメッセージを発信し続ける必要がありそう
です。南相馬市では震災前に14軒の農家民宿が営業をしていました。震災直後は4軒に減少。現在は12
軒(小高区2件、鹿島区1軒は休業中。震災後に開業が3件)現在9軒が営業中。
2月には鹿島区の1軒。農家民宿「塔前の家」さんが再開します。

その農家民宿「塔目の家」の佐藤さんを含む10軒の農家民宿さん達は、センターの企画部会の中で「農家民宿
の集い」を開催し、不定期に各農家民宿を訪問し、お客様へおだしするお食事に関する細かな事から地域の情報
の事などジャンルを問わずおしゃべりしながらおもてなしの情報交換や確認を行っています。


この日は震災後開業された鹿島区北屋形の農家民宿「森林」さんのお宅に集合。賑やかにお話ししていま
した。最近、ご宿泊頂くボランティアさんの中には、親子でいらっしゃる方や相双地域で行われるイベン
トへ参加する為保護者や、引率の大人の方と参加する子ども達も結構増えてきています。
この地を訪れ震災の影響や原発事故の問題を親子で、時には先生と生徒で、大人と子供で直視し、農家民
宿に宿泊する事で夕飯時には当時の話や、復興へ向う現在の状況などの話しを聞く。
放射能は大丈夫か?との問題を考慮してもなお、この震災を学習として捉えようとする動きが増えてきて
いるのかもしれません。
翌日、勉強会に参加された皆様が南相馬市を視察に訪れました。前日の雪が残る南相馬市。郡山から普段
なら2時間ちょいの道を3時間以上かけてのご到着。待っていたのは、浜通りでは珍しい雪げしき。
語り部さんから震災のお話しを聞きながらの道中、放射線測定器を渡された参加者の中には、初めて手に
する方も多かったそうです。徐々に復旧が進んでいる小高区ですが、津波の後を隠すようにきれいな雪景
色が広がる中「さびついた車の残骸がねぇ…」と言葉を捜される参加者の方もいらっしゃいました。
南相馬市博物館では今日から「ふるさと小高」と題した特別展が、3月20日まで開かれます。館内の一
部には小高の古い町並みや住民の方の写真も展示されています。また、シアターでは震災前に完成した南
相馬市の地域紹介が上映され、震災前の小高区の様子も紹介されています。


>>南相馬市ふるさと回帰支/援センターHPへ
















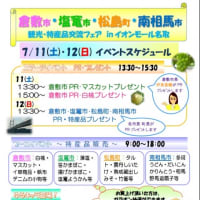



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます