
先日の大鍋越えを越えられず途中須原へ降ったが、残りの点と点を結ぶため反対側からの登頂に挑みました。狩足入口左側にある尾根筋から出発
すぐに山神様の祠が倒れていたので修復し手を合わせ黙々と上を目指します。430m付近は周囲が開け下田方面を見入れば下田富士の頂がちょこっと顔を出しています。
東側には落葉樹林の稜線が見渡せ電波塔がある谷津山が見渡せます。見晴らしの良いこの場所に大岩があり、この東側上に山神様の祠が鎮座してますが風でしょうか、祠が散乱していましたが、拾い上げ修復するも屋根が見つかりませんでした。
見晴らしの良い尾根をどんどん登ります。尾根筋には大岩が点在してますが難なく三角点563.3m地点から延びる尾根の621m地点に突き当たりました。せっかくですので563.3mの三角点まで行くことにします。途中の広い尾根筋には幻の池が少しではありますが水を蓄えていました。
落葉樹歩きはサクサクと落ち葉を踏む音が心地よいです。サクサク…サクサク…いい感じです。
三角点タッチし再び621m地点を辿り下田で一番高いと言う681m地点へ
この場所は山の頂という感じではありません。下田側から見ても稜線上の一部でしかありませんが河津側から見るといい感じの山です。歩いていると山のテッペンに来た感じはありませんネ。(だらだらした平らな頂上)
北西には彼の山十郎左衛門や猿山が見えています。
尚も歩くと大鍋越え林道に突き当たり、少し池代側に歩き市町界線の婆沙羅方面へ15m程急登します。
ここから程なく進み市町界線杭の頂で大発見です。先ほどの681m地点が東側に見えていますがこちらの方が若干高く見えます。地形図をよく見ると690mあるではありませんか。高度計の数字は694mを示しています。う~んっと唸りこの須郷を流れる川は須郷川というそうです。ならばこの山を『須郷山』と命名します。しましたです。
その後615m地点から東南に下りる尾根筋510m通過し348m地点をパスし大登林道へ下山したのでした。このどん詰りの沢筋には山もみじが多く見られ遅い紅葉を楽しみながら出発点へ帰還しました。
すぐに山神様の祠が倒れていたので修復し手を合わせ黙々と上を目指します。430m付近は周囲が開け下田方面を見入れば下田富士の頂がちょこっと顔を出しています。
東側には落葉樹林の稜線が見渡せ電波塔がある谷津山が見渡せます。見晴らしの良いこの場所に大岩があり、この東側上に山神様の祠が鎮座してますが風でしょうか、祠が散乱していましたが、拾い上げ修復するも屋根が見つかりませんでした。
見晴らしの良い尾根をどんどん登ります。尾根筋には大岩が点在してますが難なく三角点563.3m地点から延びる尾根の621m地点に突き当たりました。せっかくですので563.3mの三角点まで行くことにします。途中の広い尾根筋には幻の池が少しではありますが水を蓄えていました。
落葉樹歩きはサクサクと落ち葉を踏む音が心地よいです。サクサク…サクサク…いい感じです。
三角点タッチし再び621m地点を辿り下田で一番高いと言う681m地点へ
この場所は山の頂という感じではありません。下田側から見ても稜線上の一部でしかありませんが河津側から見るといい感じの山です。歩いていると山のテッペンに来た感じはありませんネ。(だらだらした平らな頂上)
北西には彼の山十郎左衛門や猿山が見えています。
尚も歩くと大鍋越え林道に突き当たり、少し池代側に歩き市町界線の婆沙羅方面へ15m程急登します。
ここから程なく進み市町界線杭の頂で大発見です。先ほどの681m地点が東側に見えていますがこちらの方が若干高く見えます。地形図をよく見ると690mあるではありませんか。高度計の数字は694mを示しています。う~んっと唸りこの須郷を流れる川は須郷川というそうです。ならばこの山を『須郷山』と命名します。しましたです。
その後615m地点から東南に下りる尾根筋510m通過し348m地点をパスし大登林道へ下山したのでした。このどん詰りの沢筋には山もみじが多く見られ遅い紅葉を楽しみながら出発点へ帰還しました。


















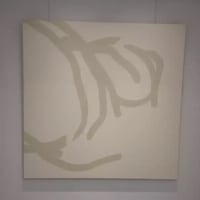
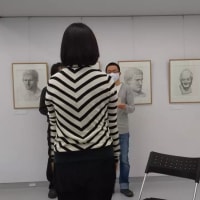








失敗の連続が地図読みの妙薬ですねkawaさん
近時下ビバーク訓練を計画実行します。
私、先日は三方平から東北東の尾根へ下る所までは
地図とにらめっこしていたのですが、その先はぜんぜん。
なので754m地点手前でも、地図をよく見ていれば
どこに下るか分かったのに、それをしないで失敗でした。
まだまだ未熟者、来年はもっと修行します。