はじめに
国や地方公共団体に寄せられる公害苦情の中でもっとも多いのは騒音苦情です。騒音の原因は、工場、建設作業、自動車、航空機、鉄道、一般営業から家庭生活騒音まで多岐にわたりますが、そのほとんどは低周波音を伴っており、正確には[騒音+低周波音]の被害というべきです。その中には、騒音よりも低周波音の方が被害の主体をなすものや、ほぼ純粋に低周波公害とみられるものまで含まれていますが、すべて騒音公害の中に一括して対処されているのが我が国のほとんどの地域での現状です。
騒音はだれにもわかりやすいのに、低周波音は一般にわかりにくいために、[騒音+低周波音]の被害を単に騒音公害と思い込んでいる人は被害者の中にも多くみられ、このことが問題の正しい解決を困難にしています。
騒音苦情に対処してくれる市町村は普通は騒音計しか持っていませんから、こうした苦情の訴えに対し騒音だけを測定し、それを騒音基準に当てはめて判断しようとします。これでは低周波公害は切り捨てられることになります。これだけ苦しいのに、騒音基準をクリアしているから、法的にどうすることもできませんとお役所から申し渡されては、低周波音の被害者は途方にくれるばかりです。
これだけ科学が進歩し測定機器が普及しているというのに、この非科学的なやり方がいまだに無反省に国中で行われており、全国各地で低周波音被害者は切り捨てられています。その見捨てられた被害者のために少しでもお役に立ちたいというのが本書の願いです。 (1994年5月)
目 次
| (1) 低周波音とは | (23)住民不在の行政(続) | |
| (2) 音の強さ | (24)難行する測定 | |
| (3) 騒音計での測定 | (25)秘密測定を | |
| (4) 公害としての扱い | (26)秘密測定を(続) | |
| (5) 騒音と振動と | (27)公害は犯罪である | |
| (6) 基準とは | (28)科学無視の測定 | |
| (7) 基準がないこと | (29)状況無視の測定 | |
| (8) 被害症状 | (30)測定の三原則 | |
| (9) 建物・建具の被害 | (31)原因療法 | |
| (10)個人差 | (32)隣の被害の謎 | |
| (11)鋭敏化 | (33)被害を受けたら | |
| (12)感覚異常者 | (34)必ず記録を | |
| (13)聞こえない騒音か | (35)周囲を固めよ | |
| (14)発生源 | (36)測定は行政に | |
| (15)遠くまで伝わる | (37)協力者を求める | |
| (16)困難な対策 | (38)裁判に訴える | |
| (17)訴えの特徴 | (39)逃げ出すこと | |
| (18)ひどい過小評価 | (40)低周波人間 | |
| (19)環境庁の実態調査 | (41)騒音地獄 | |
| (20)健常な人 | (42)便利中毒文明 | |
| (21)環境中の実態 | (43)やさしさ欠乏症候群 | |
| (22)住民不在の行政 | (付) 騒音公害との鑑別表 | |
(1) 低周波音とは
低周波音とはなんですか?
普通の音とどう違うのですか?
低周波音も普通の音も、いずれも空気中を伝わる振動の波、つまり空気振動です。ではどこが違うのかといいますと、その空気振動の振動数が違うのです。
振動数の単位をヘルツ(Hz)といいます。1秒間の振動数のことです。100ヘルツの音とは、1秒間に100振動の音です。 一般に人の耳は、20ヘルツから20000ヘルツの間の音を聞き取ることができるとされます。20ヘルツ以下の低すぎて聞こえない音を超低周波音、20000ヘルツ以上の高すぎて聞こえない音を超音波といいます。
では、20ヘルツから20000ヘルツの間なら同じように聞こえるかといえば、そうではありません。人の耳の感度(聴力)は、2000ヘルツから4000ヘルツあたりがもっとも良好で、それより高くなっても低くなっても聞き取りか悪くなります。
人間の会話は、500ヘルツから2000ヘルツ前後で行われ、100ヘルツ以下は言葉に入らないとされていますので、日常生活にあまり必要ではありません。そのため、100ヘルツ以下になりますと、耳の感度が急激に低下します。そこで100ヘルツ以下の音を、一般には超低周波音を合めて、低周波音あるいは低周波空気振動と呼びます。つまり音の周波数が低すぎて、聞こえない、あるいは聞き取りにくい音を、低周波音と呼ぶわけです。
(2) 音の強さ
低周波音の強さ(強弱あるいは大小)を表すのにデシベルが使われますが、これはどんな単位ですか?
騒音の時のデシベルあるいはホンとどう違いますか?
音の強さとは物理的な音のエネルギーです。ところが一般に音のエネルギーを直接測ることができませんので、通常は音の圧力(音圧)を測定しています。普通の状態では、音の強さ(エネルギー)は音圧の2乗に比例します。
人間に聞こえる最小の音圧を基準にして、これと任意の音圧との比を対数表示した数値が音圧レベルです。その数値の単位がデシベル(dB)です。
対数表示ですから、普通の計算と違いまして、50デシベルの音が2ヵ所からくれば、その足し算は約53デシベルです。また50デシベルの10倍の音は60デシベルという計算になります。
対策の結果、音を半分に下げましたといわれた時、60デシベルが30デシベルに下がったのならよいのですが、57デシベルに下がっただけでも半分になったといえるわけです。これなら感覚的にはほとんど変わりませんから、だまされないことです。
人の耳の聴覚は、周波数で大きく変動します。そこで耳の性能に合わせて、特に低い周波数を弱く評価するように設計されたのが、公害用の普通騒音計です。これによる測定数値がデシベル(A)で、これまで騒音公害の基準に使われてきたホンと同じです。つまり、人の耳の性能に合わせて補正した数値です。
(3) 騒音計での測定
騒音計で低周波音を測定できますか?
公害用の普通の騒音計で低周波音を測定することはできません。その際測定されるデシベル(A)はA特性ともいい、低い周波数を実際より非常に小さく評価しています。
単一の音(純音)について比較してみますと、
1000ヘルツ 50デシベル=50デシベル(A)
100ヘルツ 50デシベル≒30デシベル(A)
50ヘルツ 50デシベル≒20デシベル(A)
これではとても低周波音を正直に表示してくれません。
また、普通の騒音計では、C特性も測定できるようになっております。これはA特性ほど極端な補正になってはおりませんが、やはり十分平坦(フラット)ではありません。それでも、A特性とC特性と両方を測定すれば、その差が大きいばど、低周波成分が多く含まれていると推定することができますが、参考程度です。
普通の騒音計は、31.5ヘルツ~8000ヘルツの問を測定できるように設計されており、それ以下も以上も切り捨てです。ところが低周波音の被害は、16ヘルツ前後に多くみられますので、これでは本当のところで役に立たないわけです。
騒音苦情は市町村が対応することになっていますが、市町村は騒音計しか特っていないのが通例です。その騒音計で騒音だけでなく低周波音の被害まで対処しようとしがちですので、低周波音被害者は行政から切り捨てられることになります。
(4) 公害としての扱い
公害対策基本法に載っている「典型7公害」の中に、低周波公害がはいっていませんが、公害ではないのですか?
公害対策基本法・第2条
この法律において「公害」とは、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
ここに記載されている7つの項目を典型7公害と呼び、低周波公害は入っていません。また、被害が小範囲、しばしば一人だけの被害の訴えということも多いのですが、1974年当時の和歌山市でのメリヤス工場周辺での約50人の被害の訴え、1977年当時の西名阪自動車道での約100人の被害の訴えなど、相当範囲にわたらないからと否定するわけにもいきません。
1977年、低周波公害を第8番目の公害に指定する目的で、環境庁の大気保全局の下に「低周波空気振動調査委員会」が作られ、基準をきめようとしました。公害を取り締まりの対象にするためには、厳密な基準が必要だという考えでした。
しかし、そういう杓子定規な考え方は低周波公害にふさわしい考え方ではありません。結局基準を設けることはできませんでした。
委員会に出席して基準設定に反対意見を陳述した私に対し当時の橋本道夫大気保全局長は「基準はできなかった。しかし、被害があれば対応する」と述べました。
(5) 騒音と振動と
騒音と振動と低周波音との関係はどうなっていますか?
騒音と振動とは典型7公害として認められ、低周波音は認められておりませんが、実はこの三者は大変近い関係にあります。
騒音 = 空気振動 + 高い周波数
振動 = 地盤振動 + 低い周波数
低周波音 = 空気振動 + 低い周波数
こうした密接な関係から、騒音と振動と同時にある時には、必ず低周波音もあり、この三者が長期間ある時、一番被害者を苦しめるのは、実は低周波音なのです。騒音+低周波音でもまず同じです。
騒音も振動も非常にわかりやすい。しかし低周波音は非常にわかりにくい。ですから、被害者は騒音と振動の被害だけ、あるいは騒音の被害だけと思い込んでいることが多いのですが、低周波音はボクシングのボディブローのように、後から効いてきます。
低周波音は、公害用振動計に、振動をとらえるピックアップの代わりに、低周波音用のマイクをつなげば測定できます。ですから、騒音を測定するほど簡単にはなっていませんが、振動を測定するのと大差ありませんし、測定機械も、個人が購入するのは大変にしても、行政にとっては安い機械です。行政が低周波音だけを差別扱いして測定しないのは、被害実態を無視した不当な行為です。
ましてや、「低周波音被害は公害ではない」とか、「基準がないから測定しても意味がない」とかの暴言が行政から出てくるのは、許せないことです。
(6) 基準とは
公害から住民を守るには、基準が必要だと思いますが?
公害対策基本法が作られた1967年当時、たとえば四日市市とか大阪市西淀川区などの大気汚染はひどいものでした。それに対して、基準値を設けて「これ以下にしなさい」と国が言ってくれるのは、住民にとって確かに有り難いことでした。
しかし、当時のようなあんなひどい公害状況がおおむね存在しなくなった今日では、基準の持つ意味が逆転しています。ここまでなら基準以下だから出してもよろしいとか、出ていても基準以下だから文句をいうことはできないとか、住民の味方であったはずの基準が、いつの間にか企業や行政の味方になっています。
住民が騒音被害を訴えますと、行政は騒音計で騒音を測定してくれます。測定の結果、基準を越えておれば相手に対策を指示してくれますが、基準以下だとなにもしてくれません。その時基準は行司の軍配の役割を果たしています。
騒音で両者が対立している時、軍配が加害者に上がると、被害者の負け。被害者は騒音被害の上に、辛抱が足りない、わがままだ、神経質だ、いやがらせではないか、カネが目当てに違いない、と、二重の被害を受けます。幸い軍配が被害者に上がっても、対策は基準以下にすればよいだけで、騒音被害状況は無視。それ以上はいえませんと突き放されます。基準は行政・企業の免罪符です。
我が国の幹線道路の中で騒音基準をクリアーしているのは、1割強に過ぎませんが放置です。基準は行政の目安だそうです。
(7) 基準がないこと
基準がなければ、どうしようもないのですか?
騒音も振動もひどいある被害者宅のケースです。そこが住居地域でなくて準工業地域であったため、ゆるい基準が適用されましたので、騒音もわずかに基準以下、振動もわずかに基準以下。対策は相手企業にお願いするしかないと困っていました。
測定してみますと、当然ながら相当きつい低周波音が出ておりました。これで、胸を張って相手と交渉できるわけです。もし、変に低周波音の基準なるものがあって、これまた基準ぎりぎりセーフだったりしたら、泣くに泣けないことになります。
本当は、基準などない方がよいのです。あくまで、被害があるということが基本です。「近隣騒音」について、林道義東京女子大教授は、「基準は被害者にあり」と述べておられます。
その基本は日本国憲法にあると考えます。
13条(個人の尊重と公共の福祉)
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第25条(生存権、国の社会的使命)
① すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
(8) 被害症状
低周波公害では、どんな被害症状が出るのですか?
被害症状の主体は、一言でいえば不定愁訴といわれるものです。
頭痛、頭重、イライラ、不眠、肩その他のこり、胸の圧迫感、どうき(ドキドキ)、息切れ、めまい、吐き気、食欲不振、胃やおなかの痛み、耳鳴り、耳の圧迫感、目や耳の痛み、腰痛、手足の痛み・しびれ・だるさ、疲労感、微熱、かぜを引いたような感じ、などなど。これを低周波音症候群と言います。
以上いろいろある中で、夜も低周波音が出ておればの話ですが、頭痛、イライラ、不眠がもっともポピュラーな症状で、三主徴といいます。この三つがあれば低周波公害を疑えという意味で、特に集団的な被害の場合に参考になると思います。
こんな不定な症状ですから、医療機関を訪れても、患者さんが騒音環境のことを教えてくれなければ、医者には診断困難です。自律神経失調症(中年女性なら更年期障害、老人なら動脈硬化症)と命名されて、頭痛には頭痛薬、イライラには精神安定剤、不眠には睡眠薬と対症療法に終始しがちですが、これらは本質的に無効です。原因療法、つまり低周波音発生源を断つしか対策はありません。
もっと明確な身体症状はないかとなりますと、鼻血は確かに多くみられます。その他、回転性のきついめまい発作としてメニエル症候群、急に脈拍(心拍)が早鐘のように打ち出して、また急にパツと正常に戻る発作性頻拍、ひどい体重減少などが被害者に多くみられるように思います。
(9) 建物・建具の被害
身体被害(低周波音症候群)以外に被害はありませんか?
低周波音は普通の音と違って振動的な要素が強いですから、音圧が大きければ、家屋の柱や壁のひび割れや瓦のずれなど、建物の被害が出ます。ただし、原因が空気振動なのか、地盤振動なのか、あるいは両方なのか、区別しにくい場合が多いようです。
航空機であれば地盤振動はありません。自動車や列車の場合ですと、平面を走っている場合はまず地盤振動を考えますが、高架橋の場合は低周波音の役割の方が多くなると思われます。
こうした建物の被害よりもっと多くみられるのは、建具(戸・障子・窓ガラスなど)や器具類が、細かくガタガタ鳴るという徴振動の被害です。70デシベル以上位になると、このガタガタ音が発生するとされます。
このガタガタ音で、夜寝られない。したがって頭が痛い、肩がこる、などなど。それを克服するため睡眠薬を多用することになり、それで昼間だるくて、ぼんやりする。こういった筋道で、自分の被害を解釈している被害者がいます。二次的騒音被害です。
個人差がひどいですから、純粋にそういう場合があってもよいでしょうが、本当は低周波音による直接の身体被害であるのに、ガタガタ音による二次的騒音被害と思い込んでいる可能性があります。
そのガタガタ音を止めてくれさえすればよいということなら、対策は割合簡単ですが、対策後に直接の身体被害である低周波症候群が残って困ったことになる恐れがあります。
(10)個人差
低周波音害は個人差がひどいと聞きましたか?
低周波音公害には個人差が著しく、そのことが被害者の悩みの種になっています。家族の中で、被害を訴えるのは一人だけということもしばしばです。よそから来た第三者ならなおさらわかってくれません。そこで、「神経質なのではないか」「気にするからだ」などと、被害者が逆に悪者にされたりします。
奥さんが症状を訴え始め、次第に苦しむようになってから実に4年後に、ご主人が妻の訴えていることがわかったというケースがありました。「わかったら地獄」というのが、ご主人の実感です。
この場合もそうですか、奥さんは低周波音公害現場の家にずっといますが、ご主人はあまり家にいないという環境条件の差を越えて、どうも中年婦人が鋭敏な場合が多いようです。もちろん例外は多々ありますが、一般に、男、若い人、老人はにぶい傾向です。
あちこち低周波音害の被害現場を訪れましたが、私の妻は初めから大変敏感で、被害者とよく話が合います。それに対し私は終始極めて鈍感で、承り役専門です。したがって、もともと個人差があるのは明らかです。「他の人がなんともないのに、うるさく言うのはおまえだけだ」と被害者を責め立てるのは、おかど違いです。
どうしてこんなに個人差があるのでしょうか。低周波音は日常の言葉などに不必要な音の領域ですから、トレーニングを受けることなく、ほとんど生まれたままに放置されているため、その差が大きいのではないかと考えています。
(11)鋭敏化
低周波音も時間が経てば慣れるのではありませんか?
騒音には慣れという現象がよく見られますが、低周波音には慣れはまずありません。それどころか、時間の経過とともにどんどん鋭敏になって、苦痛が強くなるのが普通です。
1979年のことです。西名阪自動車道の香芝高架橋で発生した低周波公害が問題になり、環境庁の交通公害対策室長が現地を訪れました。その時高架橋直下の試験家屋で、被害住民たちと1時間以上も話し合いが行われ、住民の中には苦しくなって途中逃げ出す人もあったほどでしたが、感想を求められた室長の「音は想像していたより静かでした」という言葉に、住民は挙って激怒しましたが、実は室長の発言は正直な感想であったと思われます。住民にこれ程よくわかる苦しさが、室長にはわからなかったのでした。
低周波公害にもともと鋭敏な人がこの地域に集中して住んでいたとは考えられませんから、低周波音のひどい高速道路の沿線に数年間住んでいるうちに、地域住民の多くが集団的に鋭敏になっていったと考えられます。つまり、無意識のうちに強制された形で、学習効果、訓練効果が上がったものと思われます。
昭和53年度環境庁委託業務結果報告書によりますと、低周波空気振動の感覚域値の研究では、鋭敏化した被害者は、一般の人より10~20デシベルあるいはそれ以上鋭敏であることが明らかにされました。また東大・斎藤正男教授のご研究では、一般の人も訓練によって鋭敏化することが明らかになりました。
(12)感覚異常者
他の人がなんともないのに、一人だけ被害を訴えたりするのは、その人が感覚異常者なのではありませんか?
工場から100メートルも離れた家の主婦が、工場の音がうるさくて眠れないと言い出しました。騒音測定では基準以下、近くの人も家族も平気、工場の人がその家に一泊したが、うるさい音など何も聞こえなかったということから、行政から“感覚異常者”にされてしまいました。
感覚異常者にしてしまえば、悪いのは異常感覚を持った被害者であって、工場は悪くないことになり、工場も行政もなにもしなくてよいことになります。こんな楽なことはありません。
でも、被害者はどうなるのでしょうか。(低周波)騒音被害の上に、感覚異常者という辱めを受け、すべてから見放されたのです。
わが国には、多数者=正常者、少数者=異常者という差別の図式が、抜きがたく存在しています。
公害とは弱者の被害であるというのが、私の基本的主張です。住民全部がやられるなら、それは公害ではありません。事件です。低周波音に弱い人がやられ、強い人は平気。それが公害の姿です。
大気汚染の場では、老人や子供のような常識的に弱者と納得される人が被害を多く受けました。低周波公害では、元気なはずの中年婦人が被害をうけやすいだけの違いです。四日市・西淀川の物凄くひどい大気汚染の場でも、実際に被害を受けるのは、全体からみれば常にほん少数者なのです。
(13)聞こえない騒音か
低周波公害は聞こえない騒音と表現されることがよくありますが、本当に聞こえないのですか?
低周波音の被害者のほとんどは、騒音被害の訴えから出発しております。不定愁訴だけ訴えている被害者でも、尋ねますと聞こえると答えます。山梨大学の山田伸志教授は、聞こえることが被害の出る必要条件だとしておられますが、事は単純ではありません。
① 聞こえる、聞こえないには、周波数だけでなく、音圧も関係しています。普通聞こえないとされる超低周波音でも、20ヘルツ以下なら聞こえないとはっきり一線を引けるわけではなく、音圧が十分大きければ聞こえるとされます。
② 聞こえている音と被害を与えている音と、同じ音であるとは限りません。低周波音で被害を受け、それよりもっと周波数の高い音を聞き取っている可能性があります。
③ 低周波音で被害を受けていても、そもそも聞こえなければ、外から被害を受けていることがわからないのではないか。公害ではなく、自分の固有の疾患と思いこんでいる可能性があります。
④ 被害を受け入れるルートは、耳からが主体と考えられますが、もっと直接的に、脳自身をはじめ、肺や心臓や胃腸その他の身体諸臓器に影響を与えていると考えられます。
普通の音は非常に振動数が多いので、耳という特別の感覚器で感じ取るようになっているわけですが、低周波音なら、普通の細胞が感じ取ってもよい振動数なのです。
(14)発生源
低周波音の発生源には、どんなものがありますか?
あらゆる機器から大小様々な騒音や低周波音が発生します。その際、ひどい騒音を出す機器はすぐに改善されますが、低周波音の改善はいつもその後に取り残されます。騒音源対策として音の大きさを下げることが困難な場合には、周波数を下げればよいとしていた時代が、最近まであったのです。
周波数の違う純音で30デシベル(A)を比較した場合、それは、1000ヘルツ・30デシベル≒31.5ヘルツ・70デシベルどちらも30ホンだから静かなもんだというのはおかしいのです。
低周波音を発生する機器は、三大別することができます。
① 工場の機器 エンジン、コンプレッサー、コンベヤー、ポンプ、ボイラーなど
② 輸送機器 自動車、電車、船舶、航空機など(自動車では走行音よりふかし音の方がきつい)
③ 家庭の機器 特に冷暖房機(エアコン)、家庭用給湯器
要するに、ほとんどすべての機械、装置から低周波音が発生します。しかもこれらの機器はどんどん増えていますから、今後とも、低周波公害は増えていくことでしょう。そしてこれまで切り捨ててきた“聴覚の暗部”を狙い打ちしているのです。
低周波音は自然現象として昔から存在していました。地震、雷、風、波(特に津波)、火山の噴火など、恐ろしいものばかりです。被害症状の中の心理的な部分は、これに由来するのでしょう。
(15)遠くまで伝わる
低周波音は遠くまで伝わるのですか?
和歌山県岩出町に高野山の流れを汲む根来(ねごろ)寺という大きなお寺があります。「ねんねん根来の子守歌」で知られています。
その根来寺に伝わる里謡に、
ねんね根来の よう鳴る鐘は 一里聞こえて 二里ひびく
尾道に行きますと、有名な千光寺があります。
音に名高い 千光寺の鐘は 一里聞こえて 二里ひびく
この下の句は、随分全国で歌われているようです。
ここで言う「聞こえる」は普通の音、「ひびく」は空気を伝わる振動ですから低周波音のことです。昔から、普通音より低周波音の方が遠くまで届くことが、経験的に知られていました。
音源から離れるにつれ、音は小さくなります。これを距離減衰といいます。低い音ほど減衰は小さく、高い音ほどよく減衰します。
また音源の面積が大きければ大きいほど、距離減衰は小さくなります。ですから、巨大な工場全体が振動して低い低周波音を出しているような時には、この低周波音は驚くほど遠くまで到達する可能性があります。そうなりますと、どこから来ているのか、はっきりわからない場合もあるわけです。
1980年当時、同志社大学の野田純一先生が国道43号線で測定されたデータでは、道路沿いから40メートル離れると、A地点での減衰は 騒音13ホン、低周波音1デシベル、B地点での減衰は 騒音13ホン、低周波音6デシベルでした。











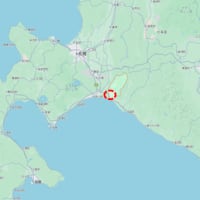
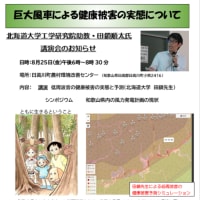
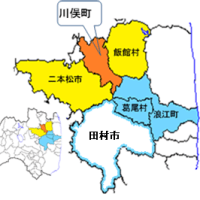
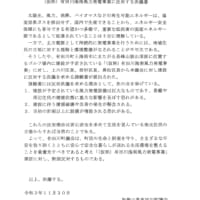
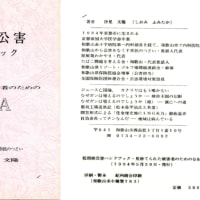




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます