───────────────────────────────────
●「今日の言葉」
~不安な時代だからこそ「覇術」ではなく「王道」を語る珠玉の言葉を~
───────────────────────────────────
“そうじて言葉というものは、単に外側からながめている程度では、決して
その真相の分かるものではありません。
すなわち言葉の真相は、どうしても、自分の体をそれにぶつけてみない
ことには、真の意味という味わいは分からないものなのです”
(森信三『修身教授録 一日一言』(致知出版社)より抜粋)
……IISIA代表・原田武夫のコメント:
─神社に行くと必ず「手水」がある。
柄杓に水をすくって左手をまず洗う。
─そして右手を洗うのだが、次の手順がある。
それは「口をすすぐ」ということである。
─なぜ「口をすすぐ」のか。
その理由は祈りに必要なのは「言葉」だからだ。
─したがって祈る前に口を清めておく。
そのために手水というものがあるといっても過言ではない。
─それくらいに「言葉」とは大切なものなのである。
古来、人はそのことを知っていた。
─そして「言葉」が体現しているものは「意味」である。
しかしこの「意味」をとらえる言葉のやり方が言語によって異なるのだ。
─一般に私たちは辞書に書いてあるとおり、外国語と日本語が
一位対応であると思ってしまう。確かにそういう単語もある。
─だが、それぞれの風土における体感に裏打ちされた言葉は、決して日本語と
それ以外で同じではないのだ。その結果、ずれが生じてきてしまう。
─外国語習得を極めれば極めるほど、逆にこのずれ・ギャップが気になって
しまう。「英語にしてしまえばよい」などという問題ではないのだ。
ここに安易な「グローバル化」がそもそも虚妄である理由がある。
肌感覚での「意味」を体をもって知ること。
それが無い限り、「言葉」の習得はあり得ないし、
そのためにはかなりの年月が必要なのだ。
やれ「円高だからグローバル化」というわけにはいかない。
我が国に暮らす私たちはそれほどまでに言葉は鋭く、清いものであることを
かつて知っていた。だから「手水」を使い、言葉を大切にしていた。
だが、ケータイ文化=20文字文化=絵文字文化の中では果たしてどうなのか。
はなはだ心もとない。
いや、率直にいってそうした体感としての日本語は失われているといって
良いだろう。これに昨今の「グローバル化」が拍車をかけている。
現下の状況で私たち日本人が為すべきこと。
それは己に立ち返り、その「言葉」を再び身を持って体感することである。
そうでしかない、と私は強く思う。
(メールマガジン 2012年9月25日号 より)
http://archive.mag2.com/0000228369/index.html













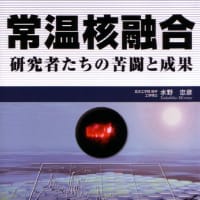





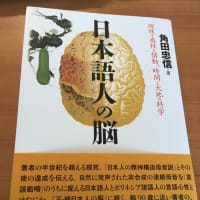
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます