今日はちょっと変わってこんな問題を取り上げてみます。
裁判員裁判って意味がないじゃないかと思われることが昨日ワイドショーで放映されました。
その事件とは
2009年10月、千葉県松戸市のマンション2階で火災が発生し、焼け跡からこの部屋に住む千葉大学園芸学部4年の女子大生(当時21歳)が全裸のまま遺体で見つかった。
遺体を調べた結果、刃物による傷があったため、殺人事件として警察は捜査。
その結果、事件後に現金自動預け払い機の防犯カメラから女子大生のカードで現金2万円を引き出す男の姿が映っていた。
警察はこの男の洗い出しを進め、すでに別の強盗・強姦事件で逮捕されていた住所不定・無職の男(当時48歳)が強盗殺人並びに現住建造物放火などの容疑で逮捕された。
被告は1984年と2002年にそれぞれ強盗や強姦事件により懲役7年の判決を受けて、2009年9月に刑務所を出所してからわずか1か月半だった。強盗傷害などと合わせて起訴された。
この事件一審の裁判員裁判で、殺人の前科のない被告に、1人の殺人で死刑判決が出ました。
2013年10月8日、東京高等裁判所で一審が破棄され、無期懲役の判決が下されました。
検察と弁護側双方が上告するも、2015年2月3日に最高裁は、
「一審判決は死刑がやむを得ないと認めた具体的、説得的根拠を示していない」として上告を棄却し、無期懲役判決が確定しました。
日本において死刑判決を宣告する際には、永山則夫連続射殺事件で最高裁(昭和58年7月8日判決)で示した死刑適用基準の判例を参考にしている場合が多い。そのため永山基準と呼ばれ、第1次上告審判決では基準として以下の9項目が提示されている。
1.犯罪の性質
2.犯行の動機
3.犯行態様、特に殺害方法の執拗性、残虐性
4.結果の重大性、特に殺害された被害者の数
5.遺族の被害感情
6.社会的影響
7.犯人の年齢
8.前科
9.犯行後の情状
以上の条件のうち、たとえば4項では「被害者2人までは有期、3人は無期、4人以上は死刑」といった基準があるようにいわれるが、実際の判例では事件の重要性などに鑑みながら決定している(詳細は日本における死刑#死刑の量刑基準を参照)。
3人以上殺害した場合は、死刑の可能性が高い。
2人殺害した場合は総合的に判断し、死刑か無期刑か有期刑か量刑判断が決まる。
1人殺害した場合は、無期刑や有期刑の可能性が高い。
先例重視の姿勢で、裁判員裁判の死刑破棄した村田均裁判長
これで2度目です。
裁判員制度は司法の場において民意を取り入れるためにはじめられたのではなかったのでしょうか?
被害者の思い、そして残された遺族の思いと「先例」を守ることのどちらに重きをおいているのでしょうか
被害者の母親は判決後、
「司法への期待を裏切られました。1人殺害だから死刑を回避するとはよく言えたものです」とのコメントを発表しました。
裁判員裁判の結果を簡単に破棄し「先例を守る」というなら裁判員制度は必要ない、意味がないということです。
裁判員に指名されたとしても、これなら行く人がいなくなるのでは?
なんだかワイドショーを見ていて複雑な思いでした。

ぽちっとプリーズ m(_ _)mお願いします

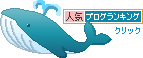 人気ブログランキングへ
人気ブログランキングへ
 にほんブログ村
にほんブログ村

やっぱりJAL ぜんぜんちがう!JALに乗って世界を旅しよう~
1回のショッピングで2回マイルがたまる!




JALのホームページが新しくなりました。








裁判員裁判って意味がないじゃないかと思われることが昨日ワイドショーで放映されました。
その事件とは
2009年10月、千葉県松戸市のマンション2階で火災が発生し、焼け跡からこの部屋に住む千葉大学園芸学部4年の女子大生(当時21歳)が全裸のまま遺体で見つかった。
遺体を調べた結果、刃物による傷があったため、殺人事件として警察は捜査。
その結果、事件後に現金自動預け払い機の防犯カメラから女子大生のカードで現金2万円を引き出す男の姿が映っていた。
警察はこの男の洗い出しを進め、すでに別の強盗・強姦事件で逮捕されていた住所不定・無職の男(当時48歳)が強盗殺人並びに現住建造物放火などの容疑で逮捕された。
被告は1984年と2002年にそれぞれ強盗や強姦事件により懲役7年の判決を受けて、2009年9月に刑務所を出所してからわずか1か月半だった。強盗傷害などと合わせて起訴された。
この事件一審の裁判員裁判で、殺人の前科のない被告に、1人の殺人で死刑判決が出ました。
2013年10月8日、東京高等裁判所で一審が破棄され、無期懲役の判決が下されました。
検察と弁護側双方が上告するも、2015年2月3日に最高裁は、
「一審判決は死刑がやむを得ないと認めた具体的、説得的根拠を示していない」として上告を棄却し、無期懲役判決が確定しました。
日本において死刑判決を宣告する際には、永山則夫連続射殺事件で最高裁(昭和58年7月8日判決)で示した死刑適用基準の判例を参考にしている場合が多い。そのため永山基準と呼ばれ、第1次上告審判決では基準として以下の9項目が提示されている。
1.犯罪の性質
2.犯行の動機
3.犯行態様、特に殺害方法の執拗性、残虐性
4.結果の重大性、特に殺害された被害者の数
5.遺族の被害感情
6.社会的影響
7.犯人の年齢
8.前科
9.犯行後の情状
以上の条件のうち、たとえば4項では「被害者2人までは有期、3人は無期、4人以上は死刑」といった基準があるようにいわれるが、実際の判例では事件の重要性などに鑑みながら決定している(詳細は日本における死刑#死刑の量刑基準を参照)。
3人以上殺害した場合は、死刑の可能性が高い。
2人殺害した場合は総合的に判断し、死刑か無期刑か有期刑か量刑判断が決まる。
1人殺害した場合は、無期刑や有期刑の可能性が高い。
先例重視の姿勢で、裁判員裁判の死刑破棄した村田均裁判長
これで2度目です。
裁判員制度は司法の場において民意を取り入れるためにはじめられたのではなかったのでしょうか?
被害者の思い、そして残された遺族の思いと「先例」を守ることのどちらに重きをおいているのでしょうか
被害者の母親は判決後、
「司法への期待を裏切られました。1人殺害だから死刑を回避するとはよく言えたものです」とのコメントを発表しました。
裁判員裁判の結果を簡単に破棄し「先例を守る」というなら裁判員制度は必要ない、意味がないということです。
裁判員に指名されたとしても、これなら行く人がいなくなるのでは?
なんだかワイドショーを見ていて複雑な思いでした。

ぽちっとプリーズ m(_ _)mお願いします


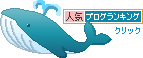 人気ブログランキングへ
人気ブログランキングへやっぱりJAL ぜんぜんちがう!JALに乗って世界を旅しよう~

1回のショッピングで2回マイルがたまる!


JALのホームページが新しくなりました。















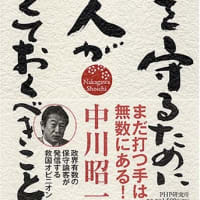




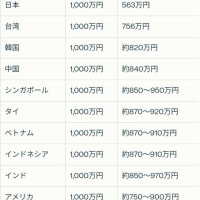





裁判員制度も被害者家族のケアもこれから良くなる方向へ向かうといいですね。
人を裁くのは大変むづかしいことですから。
とにかく悲惨な事件事故が減ることを祈ります。